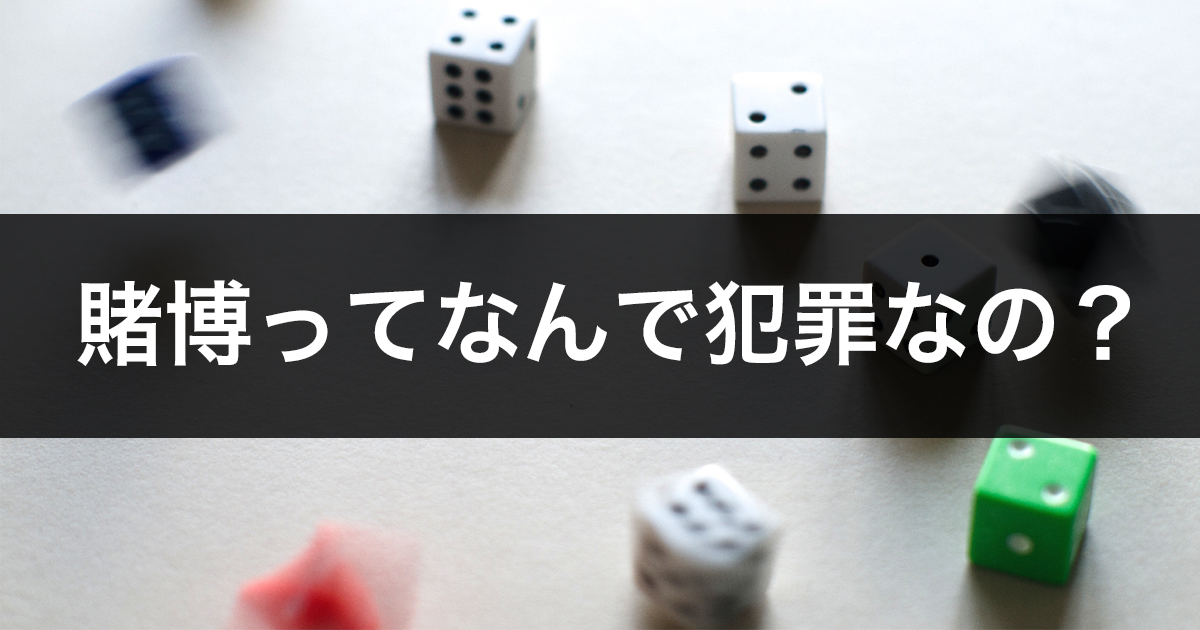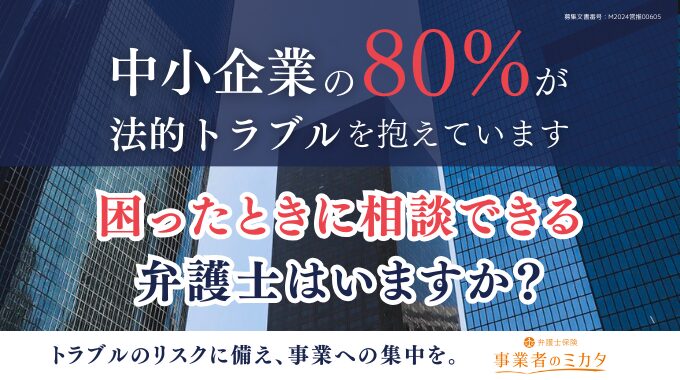2022年、大相撲・木瀬部屋の英乃海と紫雷の力士が違法賭博店を利用したとして、単純賭博容疑で書類送検されました。
過去にも、2016年4月にバトミントン男子の桃田賢斗選手も以前違法カジノ店に足を運び賭博行為を行っていたとして話題を集めたりと、芸能人やスポーツ選手の賭博がニュースになることも少なくありません。
この勝負事についてお金を賭けて楽しむ「賭博」(とばく)という行為、実は日本では刑法で定められた犯罪なのです。
これを聞いて
「えっ友達と賭け麻雀して遊ぶのも犯罪なの?」
「じゃあパチンコや競馬はどうして犯罪じゃないの?」
「公営カジノを作ろうとしている話はどういうことなの?」
「そもそもなんで賭博は犯罪なの?」
と疑問に感じた方も多いと思います。
そこで今回は「そもそもなぜ賭博は法律で禁止されているのか」について考えてみます。
記事の内容を動画でチェック
こんな疑問にお答えします
Q.宝くじ・競馬・パチンコは違法にならないのに、なぜ賭博は違法行為なの?
競馬・競艇・競輪・オートレースや宝くじ・スポーツ振興くじは一般的に「公営ギャンブル」と呼ばれ、それぞれに監督省庁が存在しています。
これらは国庫などの収入源の一部となっているため、違法に当たりません。パチンコ・パチスロ店に関しては、一般に「三店方式」と呼ばれる営業形態のため、違法にはなりません。
一方、現行の刑法で賭博行為は刑法第185条・第186条で禁止されるため、犯罪とみなされます。
賭博行為の捜査がはじまると、大なり小なり刑事責任を問われます。捜査に不安を持った場合は、ただちに弁護士に相談することをおすすめします。
賭博行為は戦前から処罰の対象だった
現行の刑法では、賭博行為は刑法第185条・第186条で禁止されています。
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
185・186条に相当する行為はそれぞれ「単純賭博罪」「常習賭博罪」(どちらも時効は3年)と呼ばれています(186条2項は「賭博開帳図利罪」とも呼ばれています)。
旧刑法の185条には「偶然ノ輸贏(意味:勝ち負け)ニ関シ財物ヲ以テ博戯又ハ賭事ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス」とあることから、現刑法の「賭博」とは「偶然で決まる勝負事についてお金を賭けて楽しむ行為」だと考えられています。
昭和25年の最高裁の判例は、賭博を処罰する根拠として、賭博が「諸国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめる」こと、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害する」こと、「暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発」すること、そして「国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」があること、を挙げています。(昭和25年11月22日、最高裁)。
ただし、この最高裁判断が下された昭和25年当時はまだ敗戦から間もなく、現代と比べて社会が混乱していた時代でした。
賭ける額が大きくなるほど上記のように懸念されたトラブルが起きる可能性も高くなることを考えると、法律によって賭博行為自体を規制する必要があったのかもしれません(旧刑法185条が施行されたのは明治15年でした)。
宝くじ・競馬・パチンコの類はなぜ違法ではないのか
刑法で賭博行為が処罰対象となっている一方で、日本には競馬・宝くじ・パチンコ等の公に認められている賭博行為があります。
三競オート(競馬・競艇・競輪・オートレース)と宝くじ・スポーツ振興くじ(toto)は一般に「公営ギャンブル」と呼ばれています。
それぞれに監督省庁が存在し、国庫などの収入源の一部となっています。
これらはそれぞれに特別法が定められており、刑法185・186条の対象外となっているのです(刑法187条では「富くじ発売の罪」が定められており、無許可で富くじに加担することは犯罪となっています)。
また、パチンコ・パチスロ店は一般に「三店方式」と呼ばれる以下のような営業形態で刑法185・186条に抵触することを回避しています。
2.客が景品を換金所(1.のパチンコ店とは別法人)に持って行って、現金と交換する
3.問屋が換金所から景品を買い取り、パチンコ店に卸す
換金所がパチンコ店と別法人である理由は、風俗営業法第23条で「客に提供した商品を(遊技場営業者が)買い取ること」が禁止されているからです。
だから賭け麻雀は違法です
麻雀は多少の実力も伴いますが、偶然の勝敗にあたるゲームです。
そして、宝くじ・競馬・パチンコのように公営ギャンブルでもなく、刑法185・186条を回避していない賭け麻雀は違法にあたるのです。
そして、麻雀店が勝敗によって景品を提供することも違法にあたります。(景品の出るような麻雀大会では参加者から財物をもらっていないので賭博罪にはあたりません。)
同じ理由で、野球賭博も違法となります。
野球賭博とは、ある試合でどちらのチームが勝つかにお金を賭け、勝ちに賭けた側の人間には賭け金以上のお金が渡されるというものです。
2023年9月に、プロ野球の公式戦に際して野球賭博をし、京都市に住む男性2人が逮捕されています。
逮捕容疑がかけられたのは2022年8月。試合の勝敗を別の男性に予想させ、合計7,180万円を賭けさせました。
こうした逮捕事例は多く、野球の勝敗や点差、個人の成績といった野球に関するさまざまな賭博が行われているも事実です。
近年摘発が相次ぐ「オンラインカジノ」って?
近年、国外で開設されたインターネットサイトに国内の自宅やネットカフェからアクセスして賭博行為を行う「オンラインカジノ」が問題となっています。
賭博開帳の仕組みの立証が難しく、賭博罪での摘発が難しいのです。
賭博行為を行なったインターネットサイトが海外サーバー上にあったとしても、賭博行為の一部が国内にて行われた場合は刑法185条の賭博罪が成立しますし、賭博場開張行為罪の一部が国内にて行われたことが明らかになった場合には同186条2項の賭博場開張図利罪が成立します。
つまり、現行の法律ではオンラインカジノも犯罪なのです。
2023年12月、鹿児島市のアパートの1室でオンライン上で違法なバカラ賭博を行っていたとして、オンラインカジノ店の従業員とその客合わせて8人が逮捕されました。オンラインカジノで売り上げた金額は、今年だけで1億3,000万円にのぼったとされます。
バカラ賭博とは、「バンカー」と「プレイヤー」という2つのカードを配り、どちらが勝つかを予想するゲームのこと。勝つと予想する方にお金を賭ける立派な賭博行為で、もちろん日本では違法です。
賭博罪で捕まったら?逮捕後の流れ
では、賭博罪で警察に逮捕されると、どのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか。
警察に身柄を拘束される
まず、賭博罪で逮捕されると同時に留置場で身柄を拘束されます。その後は取り調べを受け、逮捕後48時間以内に検察へ送致されます。
この時点で、帰宅はおろか、仕事にも行けなくなります。さらに、証拠隠滅を防ぐために、携帯電話やその他私物も没収され、電話やメールなどの連絡は絶たれます。
余罪がある場合は最大20日間の勾留
勾留される間に余罪があると判断された場合は、引き続き留置場に留まります。この場合、最大で20日間勾留されることになります。
賭博の場合、グループ単位で行っているケースが多く、共犯者の逮捕も急がれます。そうなってしまうと、たとえ家族であっても原則として面会は禁止。引き続き、外部との接触はできません。
起訴・不起訴の判断へ
勾留の満期が近づくと、起訴・不起訴の判断が下されます。
不起訴となった場合、釈放され自由の身です。前科もつかないため、その後の生活に大きな影響はないでしょう。
起訴と判断された場合は刑事裁判に移行し、有罪となる可能性が高くなります。有罪が確定すると刑罰を受け、前科がつきます。
日本で公布・施行された「カジノ法」の扱いについて
カジノとは、客が金銭を賭けてポーカーやルーレットなどのゲームを楽しむ場所です。
海外でカジノが合法化されている国は北中米・ヨーロッパ・東南アジアを中心に120カ国以上あり、カジノが非合法である日本はどちらかといえば少数派です。
日本では、2016年12月に統合型リゾート(IR)整備推進法案が公布・施行されました。正式名称を「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」といい、通称「カジノ法」「カジノ解禁法」「カジノ推進法」とも呼ばれています。
統合型リゾートと聞いて、気になるのはカジノがどう組み込まれているかでしょう。この施設におけるカジノの立ち位置は、ホテルや劇場、映画館やショッピングモール、スパ、会議場といった施設の中に、カジノが含まれているとイメージすれば分かりやすいかもしれません。
カジノ法というイメージが大きくなってしまいがちですが、実際にはファミリーで楽しめるリゾート施設なのです。
しかし、この法律は未だ賛否両論で問題視する声は多いもの。たとえば「ギャンブル依存症が増えてしまう」「治安の悪化につながるのでは」と、カジノに対する懸念の声があがっています。
このリゾート施設、実はすでに開業地が2023年4月に決定しています。その地域に選ばれたのが「大阪府大阪市」。開業目標を2029年として進められています。ギャンブル依存対策として、入場制限が設定されると予想されていますが、今後の動きに注目しておきましょう。
捜査の対象となりそうであれば弁護士へ相談を
いかがでしたでしょうか。
賭博罪が制定された当時と比べて賭博をめぐる社会情勢は大きく変わりましたが、賭博行為のもつ悪影響に対する懸念はいまだ世の中に根強く残っています。
東京五輪開催が近づくにつれて盛んになってきたカジノ解禁議論をきっかけに、賭博との付き合い方について社会全体で見つめ直すべきかもしれません。
とはいえ、賭博行為は犯罪にあたる行為であり、大なり小なり刑罰が科せられると想定されます。
もし、賭け麻雀など賭博行為に関わってしまっていたのであれば、ただちに弁護士へ相談するようにしてください。
弁護士へ相談することで、次のようなメリットがあります。
- 違法性が低い場合は、検察官に不起訴の主張をしてもらえる
- 不起訴の可能性が高い場合は、早期釈放を期待できる
- 不起訴処分に向けて刑罰を軽減を主張してもらえる
賭博行為で捜査の対象となりそうであれば、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士の選び方や詳しい相談窓口については、以下の記事で解説しています。参考にしてみてください。
関連記事
-
-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q.そもそもどうして賭博は違法行為なの?
A.現行の刑法では、賭博行為は刑法第185条・第186条で禁止されています。
賭博を処罰する根拠は、「諸国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめる」こと、「健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風(憲法二七条一項参照)を害する」こと、「暴行、脅迫、殺傷、強窃盗その他の副次的犯罪を誘発」すること、「国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」があること、とされるためです。
Q.宝くじ・競馬・パチンコの類はなぜ違法にならないの?
A.三競オート(競馬・競艇・競輪・オートレース)と宝くじ・スポーツ振興くじ(toto)は一般に「公営ギャンブル」と呼ばれ、それぞれに監督省庁が存在しています。国庫などの収入源の一部となっているため、違法に当たりません。パチンコ・パチスロ店に関しては、一般に「三店方式」と呼ばれる営業形態のため、違法にはなりません。
何か事件を起こしたりして法を犯し、その後逮捕され、裁判において有罪になるとその人には前科がつきます。
また、前科と似た言葉で、前歴というものが存在することはあまり知られていないかもしれません。
有罪は免れて、前科がつかなかった場合であっても、前歴はついていた…なんてことは大いにあり得ることです。
それでは、前科と前歴はいったいどう違うのでしょうか。
そして、前科がつくと、その後の生活ではどのような影響が出て、何が不利になるのでしょうか。
今回は、それらを詳しくみていきましょう。