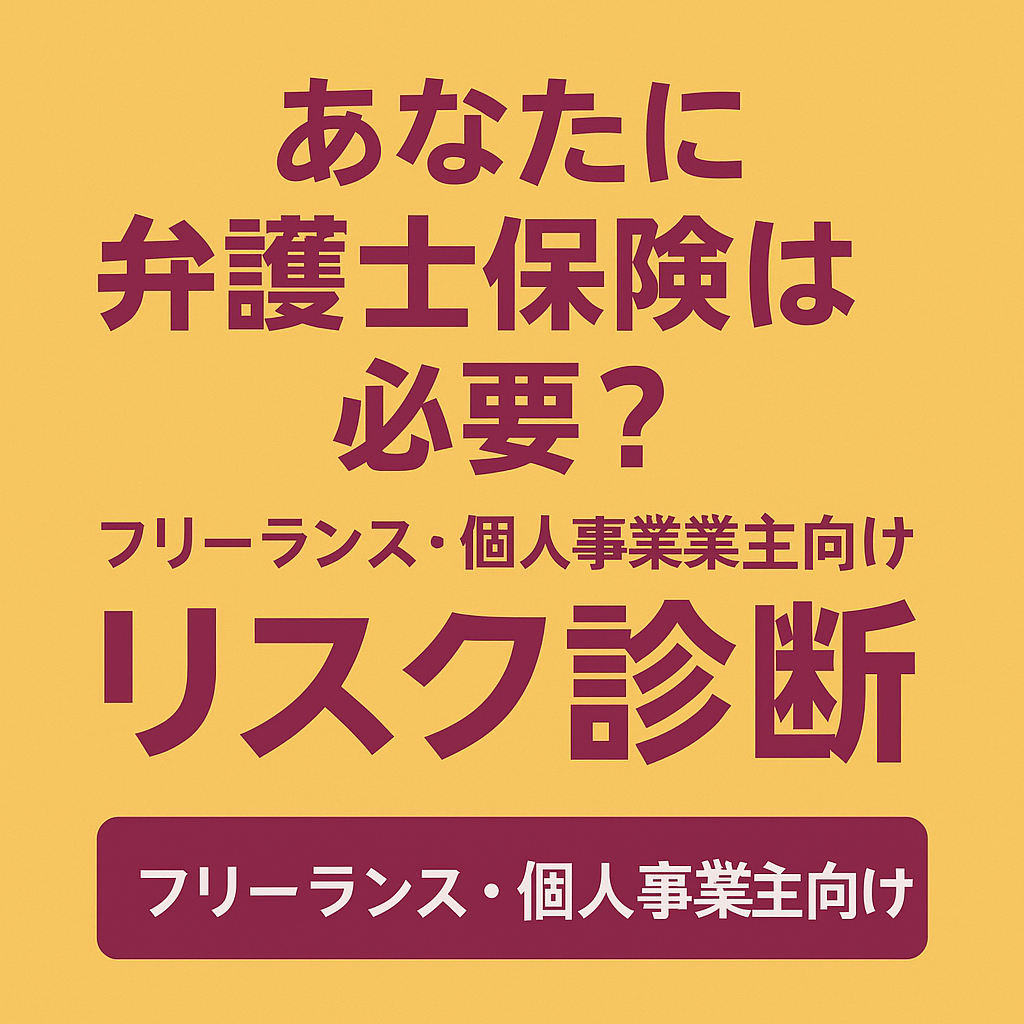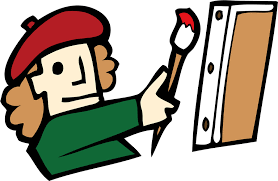
フリーランスとして働くイラストレーターが増えるに伴って、さまざまな法律トラブルに巻き込まれる事例が増えています。
会社に雇用されているイラストレーターの場合であれば、法律トラブルがあったとしても担当部署や上司などが対処してくれるケースが多いでしょう。
ただ、フリーランスの場合には、そのような対応も含めて自己責任になり、場合によっては自身で法的な対処も必要になるケースがあります。
特に、イラストレーターの場合には、著作権問題にかかわるリスクが高いため、法的トラブルが発生した際には適切な対処が必要です。
ここではイラストレーターに多い法律トラブルについて、いくつかの事例をご紹介します。
独立して働くイラストレーターだからこそ知っておきたい法律を分かりやすく解説していきます。
こんな疑問にお答えします
Q:イラストレーターが弁護士に相談後、著作権侵害者に対してできることは?
A:弁護士保険の教科書編集部の回答サマリー
- 著作権侵害行為の差し止め
- 著作権侵害物の廃棄など
- 損害賠償請求
- 告訴
イラストレーターのトラブル例

- 賃金未払い
- 契約関係
- 著作権問題
特にフリーランスのイラストレーターに多い法律トラブルは、上記3つにまとめることができます。
事例も交えながら、どのようなトラブル内容が多いのか、どのように対処すべきなのか、詳しく解説していきましょう。
賃金の未払い

イラストレーターに限らず、フリーランスに多い法律トラブルとして、「賃金の未払い」があります。
与えられた作業をやり終え、納品やクライアントによるチェックも澄ませ、速やかに請求書を発行したにもかかわらず、約束した期日に賃金の支払いが確認できないというものです。
フリーランスとして独立し、さまざまな依頼を受けることは本当に有難いものではありますが、残念ながら未払いのケースは少なくありません。
ただ、ひとことで未払いといっても、さまざまなケースが考えられるために、適切な対処が必要になると言えます。
高額だとしても連絡すればすぐに対処してもらえるケースもあれば、少額だからと賃金を踏み倒してしまう悪質なものも、そこには含まれているからです。
担当者が支払いを忘れていた、担当部署に請求書を回し忘れていた
フリーランスのイラストレーターに依頼するクライアントは、積極的にアウトソーシングに取り組む企業が多いです。
企業と言ってもさまざまで、担当者がいろいろな業務を掛け持ちで行っている場合や、大企業のように役割に応じて細かく部署が分けられている場合も少なくありません。
クライアントである企業の担当者が、自社の業務だけでなく、多くのイラストレーターのディレクション業務を行っているような場合には、その管理も同時に行わねばなりません。
しっかりと管理しているつもりでも、うっかりと抜けてしまっているようなことがあるかもしれません。
また、大企業の場合には、支払いは総務部など経理担当部署が行うことがほとんどですが、担当者が請求書を担当部署に渡し忘れてしまうと、未払いになってしまいます。
まずは、メールや電話などで賃金が未払いになっていることを伝えるようにします。
ほとんどの企業は、その連絡によって何らかの対処をしてくれるはずです。
そもそも支払いの優先順位が低い
財政状態の悪いクライアントからすれば、フリーランスのイラストレーターに対する支払いの優先順位はかなり低いと言えます。
そのため、さまざまな言い訳によって、支払いを先延ばし、もしくは免れようとします。
「支払いを忘れていました。来週には支払います。」
「経理担当には伝えたのですが…。確認しておきます。」
「先日納品してもらったイラストですが、上司のチェックが済んでいません。」
クライアント側からすれば、財政状態が良くないために、自社に影響の大きな支払い先にだけ澄ませようとします。
そして、フリーランスのイラストレーターに対しては、支払いを先延ばしにしようとしたりして、作品に対する不満などを理由に支払いを拒否しようとすることがあるのです。
まずは契約書を整えること
フリーランス全般に言えることですが、口約束での契約が多く見受けられますが、契約書を交わしておくことがとても重要です。
約束事を契約書に含めることができ、その約束事が行われないのであれば、それは契約違反となるからです。
フリーランスのイラストレーターは、どうしても立場が弱くなってしまうことから、クライアントからすれば面倒な契約を省略しようとすることが少なくありません。
しかし、口約束だとどうしても「言った・言わない」のトラブルになりがちです。
どうしても、契約書が交わせない状態であるならば、メールのやり取りなどで、業務内容や支払いに関することなどを含めておくべきです。
当初交わしていた契約と違う、契約書トラブル

イラストレーターに多いトラブルとして、契約にまつわるものがあります。
契約が口約束だけということも珍しくなく、また契約を交わしていたとしても、クライアントが用意した契約書をよく確かめずにサインしたということも少なくないでしょう。
また、契約内容を修正してもらおうと依頼しても、「当社としてはとりあえずこれでお願いしたい」と言われるようなことがあるかもしれません。
ただし、このような契約によって、イメージしていた契約とは異なってしまうことも珍しくないのです。
賃金と支払い時期、納品時期
そもそも口約束のような場合、賃金に関することが曖昧になっていることがあります。
依頼に沿ってイラスト描いたとしても、「試し」「テスト」などを理由に支払いを拒まれたり、割引を迫られたりしてしまうことがあります。
出版社や広告代理店などがクライアントであれば、そのようなケースも少ないかもしれませんが、フリーランスに対するアウトソーシングの場合ではそのようなトラブルも数多く見受けられます。
そのため、料金はいくらで、納品に対していつ支払いをしてもらえるのか、などということを明確に定めておかねばなりません。
修正対応について
イラストを受注する際には、どのような作品が求められているのか、クライアントと打ち合わせをしながら決定していきます。
そこで、完成品のイメージをしっかりと共有しておかないと、思わぬ修正対応を求められてしまうことがあります。
また、作品を納品した後に、クライアントの求めに応じて修正対応が必要になることもあるでしょう。
しかし、あまりにも何度も作り直しを求められてしまうと、その手間だけで料金に見合わないという事態にもなってしまいます。
イラストは芸術作品であるがゆえに『完成形』を示すことが難しいために、どの段階で改正とするのかについて、しっかりと定めておかねばなりません。
例えば、契約上に修正対応の上限回数を定めておくことや、修正内容によって追加料金を定めておくことも必要になります。
著作権関係について
クライアントから依頼のあった作品について、納品後に著作権をどうするのか定めておく必要があります。
例えば、イラストをどのように活用するのか、転載はどこまで認めるのか、改変は可能なのか、という問題です。
もちろん、会社のロゴマークやマスコットキャラクターなどであれば、会社のサイトやパンフレットなどに使用されることになりますから、それほど問題にはなりません。
ただ、個人利用を目的に提供した作品が商用利用されてしまったとか、意図していないアダルト用などに活用されてしまったというケースが起きています。
場合によっては、使用の差し止めを請求しなければならない可能性がありますし、また、損害賠償請求など法的なトラブルになってしまう可能性も考えられます。
そのため契約によって、著作権が制作者に残る「利用承諾」なのか、クライアントに著作権を譲ってしまう「譲渡」なのか、明確にしておかねばならないのです。
勝手に自分のイラストを利用されていた

フリーランスのイラストレーターは、ポートフォリオの一環などとして、自身のブログやSNSなどにおいて作品を公開している掲載しているケースも多いでしょう。
そのポートフォリオをクライアントが閲覧して、発注を検討することも多いからです。
多くのケースでは、「無断使用禁止」などと記載されてはいますが、無断に使用され、中には商用で利用されているような悪質な著作権侵害も起きています。
このような著作物の無断使用は、イラストレーターの利益を奪ってしまう悪質な行為であることは間違いありません。
ただ、どのように対処すればいいのか分からない、というイラストレーターが多いのも実情です。
本当に著作物が侵害されているのかどうか
イラストレーターの作品は、個性を発揮した独創性の高いものであるために、基本的には著作物性が認められることになります。
そのため、ありふれたイラストのような場合には、著作物として認められないようなこともあります。
また、作品がトレース(元の作品をそのまま活用されている行為)されているような場合であれば、著作権侵害として認められていますが、完全に模倣している訳ではなく似たようなイラストを活用しているような場合には認められない可能性もあります。
著作権侵害を認定するには、どの程度、同一性が認められるかが大きな問題となり、侵害者がどのように模倣したのかも重要になります。
例えば、ブログに掲載している作品をそのままコピー・ペーストしているような場合には著作権侵害と認められますが、自身が真似してイラストしたのであれば場合によっては認められない可能性もあるのです。
著作権侵害者に対して行為を止めてもらうように求める
イラストレーターがブログやSNSで公開しているイラストを無断で使用されているような場合、著作権侵害者に対して行為を止めてもらうように申し出ることができます。
例えば、著作権侵害者が運営しているブログやSNSで無断使用されているような場合には、ブログに記載されている連絡先、あるいはSNSでのDMなどで伝えることが可能です。
その申し出に対して、すぐに削除するなど対処してもらえる可能性もありますが、連絡が付かないようなことも少なくありません。
そのような場合には、弁護士に相談して、著作権侵害者が誰なのか、調査してもらう必要があります。
著作権侵害者にできることは
- 著作権侵害行為の差し止め
- 著作権侵害物の廃棄など
- 損害賠償請求
- 告訴
イラストレーターが弁護士に相談後、著作権侵害者に対してできることは上記の通りにまとめることができます。
著作権侵害であると認定できる場合であれば、まずは差し止めと、無断使用しているサイトやパンフレットなどの削除や廃棄を求めることができます。
さらに、著作権侵害によって被った損害に対して、著作権侵害者に損害賠償を請求することが可能です。
多くのケースにおいては、弁護士によって差し止めや廃棄などを求めた場合、求めの通りに対処してもらうことができることが多く、最終的には損害賠償金の支払いによって和解することが一般的です。
ただし、和解に応じないようなケースであれば、告訴の検討が必要になります。
著作権侵害についての刑事責任については、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科すると定められています。
ただし、このような著作権侵害者に対するトラブルは、なかなか個人のイラストレーターが対処できるものではないと理解できるのではないかと思います。
そのため、普段から法的トラブルを意識して、弁護士の利用を前向きに考えておかねばならないのです。
いざとなった場合の弁護士保険

イラストレーターが直面する法的トラブルについて、事例に基づいて実際のトラブル内容をご紹介しました。
特にフリーランスの場合であれば、自身が責任を持って対処しなければなりませんから、どのようなトラブルが起きるのか、またどのように対処すればいいのか、普段から意識しておく必要があります。
ただ、日々の作業を行いながら法的トラブルに対処していくのは、実際のところ、難しいのが実情ではないでしょうか。
そのため、安心して取り組むために、法律のプロである弁護士への相談体制を持っておくことをお勧めします。
ただ、弁護士を利用するとなると、
- 費用が気になる
- どの弁護士に依頼すればいいのか分からない
- 敷居が高い
と感じる方も多いでしょう。
そこで、お勧めしたいのが法人・事業者向けの弁護士保険です。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
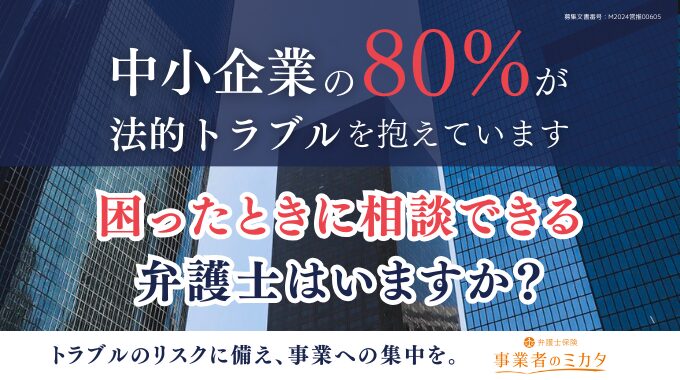
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
ぜひうまく活用して、トラブルの回避に努めてください。