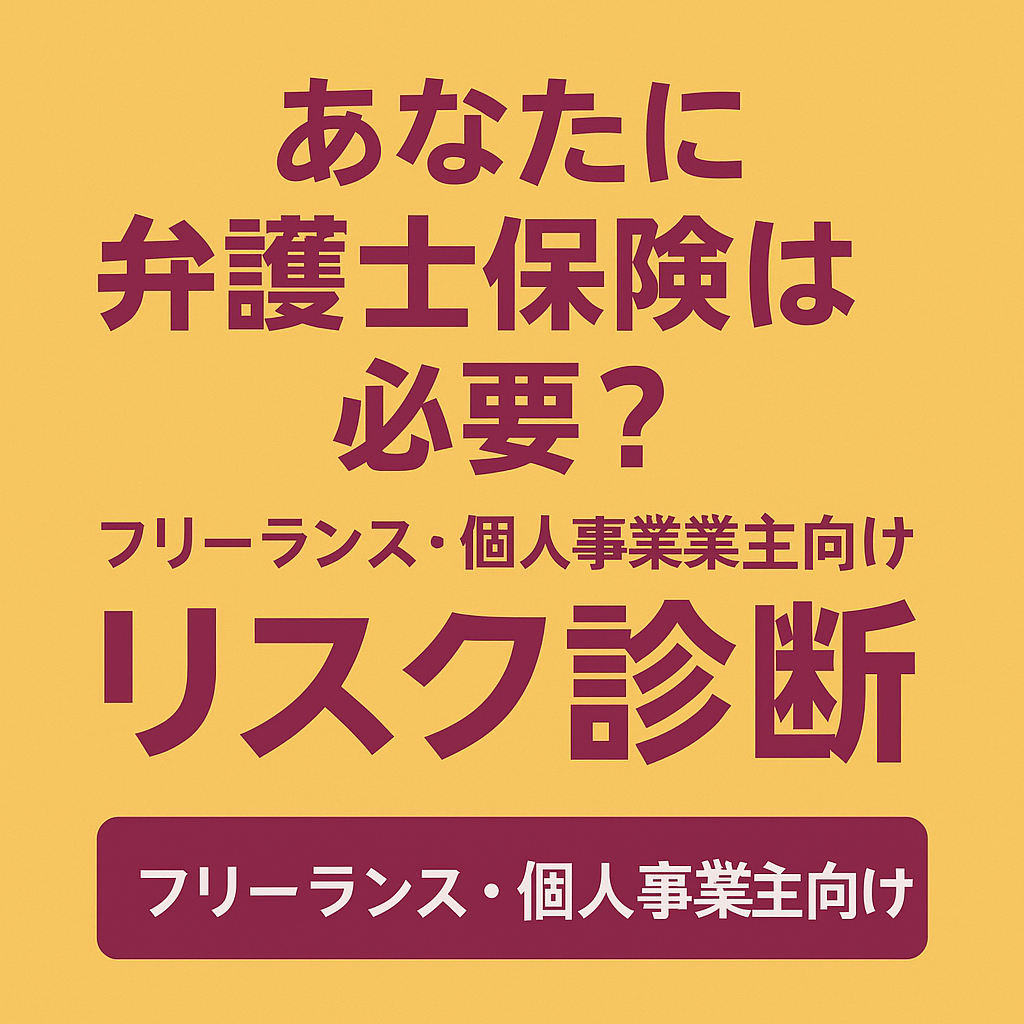不動産オーナーは、家賃を支払ってくれない『家賃滞納問題』をはじめ、さまざまな法律トラブルに直面します。
不動産賃貸においては賃貸借契約書を締結していますので、定められている条件に違反しているような場合には、その相手方に対して何らか対処することができます。
中にはそれでも違反を継続するようなこともあり、「契約を解除したい」と考えるケースも珍しいことではないでしょう。
しかし、不動産賃貸における賃貸借契約においては、契約違反だからと言って、ただちに解除することが認められないケースも存在します。
そこでここでは代表的な法的トラブルをご紹介し、その回避法についてもお伝えしていきます。
こんな疑問にお答えします
Q:不動産オーナーが直面しやすいトラブルには何がありますか?
A:弁護士保険の教科書編集部の回答サマリー
家賃滞納トラブル、無断譲渡・無断転貸、用法遵守義務違反などがあります。
家賃滞納トラブルの例と回避法
不動産オーナーが遭遇する法律トラブルと言えば『家賃滞納問題』です。
そのまま滞納していると、どんどん滞納額が増えてしまうことになり、回収が難しくなってしまいます。
そのため、家賃滞納が始まったら、早い段階で何らかの対処をしなければなりません。
では、家賃を支払ってくれない場合には、すぐに賃貸借契約を解消して、不動産を明け渡してもらうことができるのでしょうか。
家賃の支払いを請求する権利について
不動産賃貸借において賃借人が家賃を滞納しているケースにおいては、賃貸借契約で賃料の支払いについて明記されている以上、賃借人に請求する権利を有していることになります。
家賃滞納における賃料を回収する手続きは、一般的に次のような流れになります。
①督促状の送付(本人や連帯保証人)
②内容証明郵便の送付
③訴えの提起
まずは、本人や連帯保証人に督促状を送付し、それでも支払いされない場合には内容証明郵便を送付し、支払いを督促することになります。
その時点で賃借人が素直に請求に応じてくれるのであれば問題にはなりませんが、内容証明郵便を送付しても滞納し続ける場合には、もはや交渉の余地がなく、裁判を起こさざるを得ない可能性があります。
家賃を何ヶ月も滞納した場合には、ますます支払いが難しくなります。
そのため、家賃滞納が生じたら、速やかに督促状を送付することがポイントとなります。
督促しても連絡が取れないようなケースであれば、法的な手段を意識づけできる内容の促状や内容証明郵便を送付することが必要でしょう。
賃貸借契約を解除することはできるのか
そもそも、家賃を支払ってくれない賃借人とは賃貸借契約を解消して、新しい賃借人と契約したいと考えるでしょう。
家賃を1か月でも滞納してしまうと、賃貸借契約上において賃借人の義務違反となりますので、民法540条以下の規定に基づいて契約をすぐに解消できるようなイメージをお持ちの不動産オーナーも多いのではないでしょうか。
ただ、わが国の判例によりますと、賃貸借契約のように継続的な契約においては、信頼を破壊するようなものでない限りは解除できないとしています。
これを「信頼関係破壊理論」と呼ばれていますが、家賃1か月の滞納では、信頼関係を破壊したとまで言えず、賃貸借契約の解除は無効だとしているのです。
滞納の目安として直近の裁判例では、「3か月分以上の滞納」がある場合には解除を有効と認めるケースが見られます。
ただし、民法上の規定がある訳ではなく、あくまで滞納によって賃貸借契約義務違反の程度が大きく、賃貸人の不利益が大きい場合に信頼を破壊していると判断できる、としています。
賃貸借契約解除後の原状回復義務について
家賃の滞納によって賃貸借契約が解除される場合においては、設置してある家財道具などを取り除いてから部屋を返還する『原状回復義務』が求められています。
ただし原状回復義務は、「契約前の状態に戻すべき義務」と解釈されがちではありますが、時間の経過と共に劣化や消耗などが生じるのは当然で、それら自然の劣化や消耗による価値の低下については賃貸人によって負担すべきであると考えられています。
しかしながら、賃借人の責任によって損傷したのであれば、その修復は賃借人が負担すべきとも言われます。
そう考えると、具体的にどこまでが原状回復義務に含まれるのか、なかなか容易に判断できるものではないのです。
そのため、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を公表し、原状回復をめぐるトラブルの防止と解決のためにルールを示しています。(※公表当時は建設省であった。)
とは言え、賃貸借契約にはさまざまな法律問題が含まれていますので、家賃滞納のトラブル、原状回復義務の問題などについては、法律のプロである弁護士に相談して解決を目指していくことをおすすめします。
無断譲渡・無断転貸の例と回避法
不動産オーナーが直面しやすい法的トラブルとして、賃借人による無断譲渡や無断転貸があります。
例えば、店舗を賃貸していたものの、無断で第三者に使用させているようなケース。
このような場合においては、どのような対処法が考えられるのでしょうか。
考えられる2つの解決方法
- 賃貸借契約の解除によって不法占有している第三者に明け渡しを求める
- 第三者と協議し、新たな条件のもとで賃貸借契約を締結する
基本的に、賃借人による無断譲渡や無断転貸は、特段の事情がある場合でなければ、賃貸借契約の解除理由とできます。
そのため、賃貸借契約を解除したうえで、不法占有状態となっている第三者に明け渡しを求めることは問題ではありません。
また、もとの賃借人と賃貸借契約を解除し、第三者と新たな条件のもとで賃貸借契約を締結することも可能です。
このような無断譲渡や無断転貸を防ぐために、一般的には賃借権の無断譲渡および転貸の禁止、無断譲渡や無断転貸をした場合には契約解除となる条項が定められることが多いです。
それでも無断譲渡や無断転貸をした場合には契約解除となるのは当然ですが、しないようにするための抑止力にもなっています。
ただ、仮にそれらの条項を定めないとしても民法には「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。」(民法第612条1項)と定められています。
また、その2項には「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」とあることから、それらを根拠として契約解除を行うことも可能となっています。
賃貸借契約の解除によって不法占有している第三者に明け渡しを求める際の注意点
上記において、民法上に賃借人による無断譲渡や無断転貸は契約の解除要件となるとの見解をお伝えしましたが、注意すべきポイントがあります。
それは、判例のうえでは不動産オーナーの解除権には制限があるということです。
家賃滞納トラブルの章でもお伝えした通り、賃貸借契約のように継続的な契約である場合には、当事者間での信頼関係が基礎にあるため、単なる契約より強い拘束力があるとされています。
その根拠となる判例には、「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、同条の解除権は発生しない(最判昭和28年9月25日)」としています。
つまり、「背信的行為と認めるに足らない特段の事情」があるならば、民法第612条2項を根拠に契約の解除はできないのです。
例えば、無断譲渡や無断転貸があったとしても、その相手が親族であるような場合で、それほど問題なく物件が使用されているような場合には、解除が認められない可能性があります。
それは「背信的行為と認めるに足らない」とされてしまうかもしれないからです。
もちろん背信的行為と認められるような場合においては、賃貸契約を解除して、第三者に対して物件の明け渡しを求めることができます。
応じないような場合には、訴訟を提起し、解決を図ることも可能になります。
第三者と協議し、新たな条件のもとで賃貸借契約を締結する
上記でお伝えした例のように、無断譲渡や無断転貸があるものの、その相手が親族で、物件が問題なく使用されているような場合であれば、その第三者に賃貸する選択肢が考えられます。
その場合には、
- 占有している第三者への譲渡や転貸を認めてしまう
- 占有している第三者と新たな賃貸借契約を締結する
という2つの方法があります。
「占有している第三者への譲渡や転貸を認めてしまう」とは、前賃貸借人との契約を解除せず、契約をそのまま維持する方法を言います。
そのため、家賃など条件は何も変わらずに契約内容が継続されます。
「占有している第三者と新たな賃貸借契約を締結する」とは、今までの賃貸借契約とは異なった内容で新たに契約を締結するという方法です。
例えば、新たに敷金や保証金を求めることや、新たな賃料を設定することも可能になります。
ただし、無断転貸の場合には、従前の賃貸借契約が残っているために、二重に契約を結んでしまうことになります。
そのため、新たに賃貸借契約を結ぶ場合には、無断転貸を理由に契約を解除したうえで、新たな契約を結ぶようにしなければなりません。
このようなことから、無断譲渡や無断転貸がある場合においてもさまざまな法律問題が含まれていますので、法律のプロである弁護士に相談して解決を目指していくことが不可欠でしょう。
用法遵守義務違反の例と回避法
不動産の賃貸借契約の締結においては、家賃だけではなく、使用目的においても定められることになります。
例えば、居住用の不動産であれば、居住のために使用し、それ以外の目的での使用を認めないと定めることができます。
また、ペットの飼育を禁止するといった特約を定められることもあります。
さらに、店舗である場合であれば、飲食店としての利用を禁止するなど、業種を限定することも可能です。
契約においてそのように定められている場合であれば、それらの諸条件を守らない場合には、契約条件を守るように伝えることができます。
しかし、それでも条件を守らない状態が続いたとしたら、契約を解除することはできるのでしょうか。
冒頭から何度もお伝えしている通り、「信頼関係破壊の法理」という重要な考え方が解除できる大きなポイントとなります。
そこでこの章では、事例をもとにして、その対処法や回避法についてご紹介していきましょう。
賃借人が動物の飼育を禁止する特約に違反した場合
事例として、賃貸借契約に「動物の飼育を禁止する特約」があった場合についてお伝えしていきましょう。
ペットと言っても、小さなかごでハムスターを飼育しているような場合もあれば、人間ほどの大きさがある大型犬を飼っているケースもあります。
いずれも、「動物の飼育を禁止する特約」があった場合には、契約違反となるのは間違いありませんが、違反だからと言って解除できるものでしょうか。
例えば、小さなかごでハムスターを飼育しているような場合、鳴き声も小さく、近隣の住民に迷惑をかけるということがないかもしれません。
また、きちんと世話をしており、衛生上にも問題がないのであれば、不動産オーナーに重大な不利益が生じているとまで言えません。
そのため、解除までは難しいと考えられます。
では、人間ほどの大きさのある大型犬を飼っているケースであればどうでしょう。
鳴き声や遠吠えがかなり大きく、室内や外溝などに毀損など被害のおそれがある、あるいは近隣住民に頻繁に吠えているような場合には、周りに大きな迷惑をかけていると言えます。
そうなると、上記のハムスターのケースと比較しても、明らかに不動産オーナーに重大な不利益が生じていると言えます。
上記でもお伝えしている通り、契約を解除するためには、信頼関係を破壊したと言えるのかどうかがポイントとなります。
上記のハムスターのケースであれば解除を認めることは難しく、大型犬であれば認められる可能性があると言えます。
つまり賃貸借契約の解除は、契約違反があったとしても事案ごとに判断されるものなのです。
契約上の使用目的が住居であったのに事務所として使用していた場合
賃貸借契約において不動産の使用目的が居住用であるにもかかわらず、事務所として使用されているようなケースも少なくありません。
例えば、居住を目的としていたものの会社を立ち上げて事務所と兼用にしているケースや、そもそも居住の意思はなく最初から事務所として活用しているケースなどです。
そもそも、なぜ不動産が「居住用」「事業用」などに分けられているのかと言うと、それぞれに電気の許容量が異なり、またオフィス機器などによる重量の問題があるからです。
事業によっては大きな容量のオフィス機器が活用されることもありますので、居住用の場合では電力消費に耐えられず、ブレーカーが落ちてしまうような可能性があります。
また、オフィス機器やスタッフの人数が多くなると、最悪の場合には床が抜けてしまうことも考えられるでしょう。
ただ、個人で会社を立ち上げ、パソコン一台で事業活動しているエンジニアのような場合であれば、それほど大きな問題となることはありません。
近隣に対する迷惑も考えにくいことから、不動産オーナーに重大な不利益が生じているとは言えない可能性があります。
最初から事業目的としているような場合には、多くのオフィス機器を導入しているならば電気や重量の問題があり、さらにスタッフの出入りによって近隣も迷惑されていることでしょう。
そのため、解除要件を満たしていると認められる可能性があります。
このようなことから、契約違反となる使用目的が発覚したとしても、解除できるのかどうかは個別のケースによって判断されることになります。
その判断はとても難しいものになることから、法律のプロである弁護士に相談して解決を目指していくことが不可欠でしょう。
不動産オーナーはトラブルが起きやすいので、弁護士保険に入って相談できる体制を持つのを推奨
冒頭から、「家賃滞納トラブル」「無断譲渡・無断転貸」「用法遵守義務違反」という3つの事例をもとにして、回避法をお伝えしてきました。
これらは賃貸借契約においてよくあるケースであるため、安心して不動産賃貸業に取り組むためには、弁護士への相談体制を持っておくことをお勧めします。
3つの事例に共通することとして「信頼関係破壊理論」があり、賃貸借契約のように継続的な契約においては、信頼を破壊するようなものでない限りは解除できません。
契約違反だからといっても、解除できるのかどうかは個別のケースで判断されることになりますから、どうしても弁護士の力が必要になるのです。
弁護士に格安に相談でき、必要に応じて適切な対処が可能な『弁護士保険』の加入をお勧めしています。
弁護士保険「事業者のミカタ」なら1日わずか155円から相談体制を構築できる
弁護士に相談するとなると費用が気になりますが、弁護士保険「事業者のミカタ」を活用すれば、1日わずか155円から相談体制を構築することができます。
顧問弁護士サービスを導入しても、相場は月額30,000円から50,000円程度であり、中には100,000円を超えるような弁護士事務所も存在します。
しかし、1日わずか155円からといったわずかな費用でも、
- 弁護士直通ダイヤルで気軽に初期相談ができる
- 不動産賃貸業でのトラブルをカバー
- 日本弁護士連合会との協定による安心感がある
- 日本全国で対応が可能
といったメリットがあります。
そもそも、弁護士は費用が気になるだけではなく、どの弁護士に頼めばいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
弁護士保険「事業者のミカタ」であれば、いつでも直通ダイヤルに連絡でき、しかも回数制限もなく、必要に応じて対処してもらうことも可能です。
賃貸借契約書に関する内容について相談することや、家賃の滞納や無断譲渡、用法遵守義務違反の相談することも可能で、解除を求める場合にはいち早く対処してもらうこともできます。
相談だけではなく、訴訟やトラブル解決を依頼するような場合でも、着手金など一部負担のみで済みます。
名刺やホームページなどに掲載しておけば、トラブルを未然に防ぐこともできるでしょう。
弁護士保険であれば、「事業者のミカタ」の活用がおすすめです。
ぜひうまく活用して、トラブルの回避に努めてください。
【おまけ】個人事業主の弁護士保険が販売されています
個人事業主向けの弁護士保険として、ミカタ少額短期保険(旧社名:プリベント少額短期保険)より「事業者のミカタ」(個人事業主・フリーランスの方の詳細はこちら、法人の方の詳細はこちら)、エール少額短期保険より「コモンBiz+」(詳細はこちら)が販売されておりますのでご参照下さい。