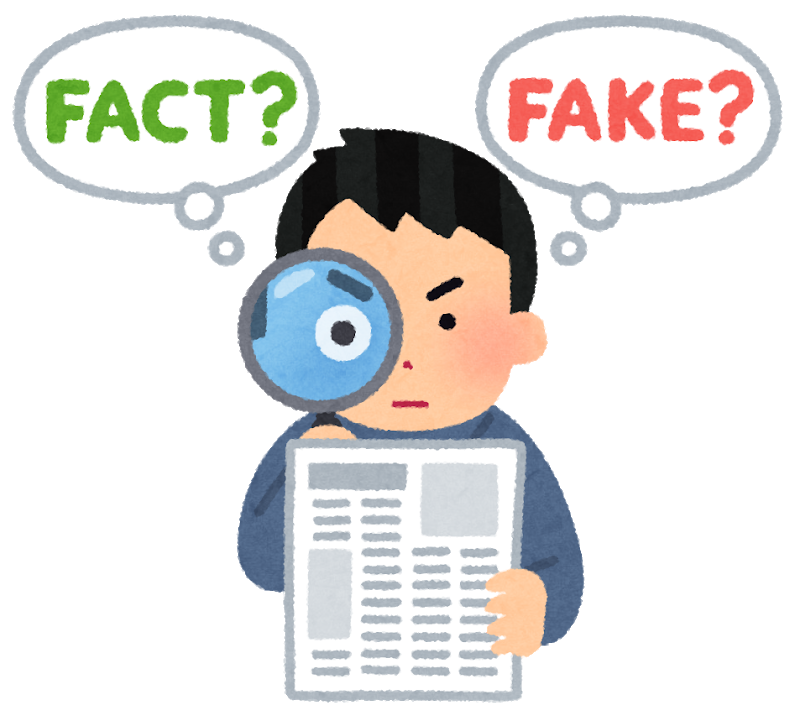スマートフォンの普及に伴って、私たちは日常においてインターネットで情報を掴むことが当たり前となりました。
コミュニケーションにおいてもSNSを活用することが多くなりましたし、SNSで友人や知人の近況を知るようなことも多いでしょう。
しかし、そのように身近になったインターネットでは、正しい情報だけではなく、間違った情報、いわゆるフェイクニュースが流れてくることもあります。
また、悪気がないとしても間違った情報をSNS上に投稿してしまうことによって、関係者が被害を被ってしまうようなケースも多くなっています。
コロナ禍で発生したトイレットペーパーの買い占め騒動は、あるSNSの投稿が発端になっていると言われます。
便利な世の中だからこそ、ネットリテラシーを持ち合わせておくことはとても重要なことでしょう。
ここでは、デマをSNSに流してしまった大学生に損害賠償命令が出た判例について詳しくお伝えしていきます。
【事例で学ぶ】デマ流した大学生に30万円の損害賠償命令~大学教授の虚偽発言をSNS投稿したケース
大学生が大学教授による虚偽発言をSNSに投稿したことによって、社会的な信用が下り、精神的な苦痛が生じたとして、30万円の損害賠償命令が出たという判例をご紹介します。
ケースの概要
このケースは、原告である大学教授が講義中に「阪神タイガースが優勝したら無条件で単位を与える」と言ったとして大学生がツイッターに投稿、かなり広く拡散されてしまったがために精神的苦痛が生じたとして損害賠償の請求を行ったというものです。
その投稿には「阪神タイガースがリーグ優勝した場合は、恩赦を発令する。また日本シリーズを制覇した場合、特別恩赦を発令し、全員合格とする。」と記載された、大学教授が作成したパワーポイントのスライドを撮影した画像も添えて投稿されています。
しかし、大学教授は「かつてはそういう教授もいた」と説明するためのスライドであり、そのような趣旨の発言はしていないと主張。
投稿の内容は虚偽であり、そのような情報が真実のようにSNSで拡散されたために、権利侵害や損害が発生したとされています。
投稿した大学生側は、大学教授が発言した内容をそのままツイッターに投稿しただけ、という主張を行っています。
被告の大学生のほかにもスライド画像をツイッターに投稿した学生がいることから、この投稿が権利侵害や損害を与えたという因果関係はないとしています。
判決は、 慰謝料20万、弁護士費用10万の合計30万円の支払いを命ぜられています。
争点となった内容
本件において、争点となった内容には3点あります。
- 投稿の内容は虚偽だったのか
- 虚偽情報の拡散と権利侵害や損害の因果関係
- 権利侵害による損害額は妥当なのか
1つ目の「投稿の内容は虚偽だったのか」という点において、双方の意見が食い違っています。
大学教授は「かつてそういう教授もいた」という旨を説明していた、大学生側はスライドを示しながら本件の発言を行ったと主張しています。
2つ目の「虚偽情報の拡散と権利侵害や損害の因果関係」については、大学教授は権利侵害や損害を受けた、大学生側は投稿との因果関係はないと主張しています。
3つ目の「権利侵害による損害額」については、大学教授は精神的苦痛に対する慰謝料として200万円を請求しています。
それに対して大学生側は、内容をそのままツイッターに投稿しただけなので、精神的苦痛が生じたとは思えないと主張しています。
損害賠償請求に至るまでの経過
本件には損害賠償を請求するに至るまでの経過があります。時系列で説明していきましょう。
本件は平成26年4月14日の講義によるもので、大学生はスライド画像と共に「阪神が優勝したら無条件で単位くれるらしい」とツイッターに投稿しています。
この投稿が複数のまとめサイトで紹介され、各種ネットニュースで取り上げられることになり、話題となってしまいました。
大学教授がこの投稿が広がっていることに気付き学部長などと相談、大学生との話し合いの場を設けられることになりました。
大学教授に迷惑をかけたと謝罪し、サイトやブログなどに対して削除依頼をするということなどで話はまとまっていました。
しかし大学生は、削除依頼に対する内容を大学教授に報告することがなく、大学教授が依頼した弁護士からの求めに対しても拒否や報告しないことが続きました。
そのような不誠実な対応も、大学教授から訴訟を提起される理由となっています。
裁判所の判断について
本件について裁判所は、大学生が行ったSNS投稿は虚偽であったと認定しています。
講義を受けていた大学生からのアンケート結果においては、「かつてはそのようなこともあった」という旨の大学教授の説明通りだと回答されています。
また、成績評価がなされるのは8月初旬あたりであり、阪神タイガースの優勝を成績に反映させることは事実上不可能であるという事情も考慮されています。
本件の投稿が精神的苦痛や損害が生じたという因果関係については、複数のまとめサイトが本件の投稿を引用していると認められたことから、寄与は大きいとされました。
そのため、社会的評価を低下させることになり、慰謝料の支払い義務が生じると認定されました。
また、大学内での話し合い後の対応が不誠実であったことも、大学教授の心労に繋がったとしています。
ただ、投稿を事実として受け取るのではなく、むしろ冗談だろうと受け取った者が多いために社会的評価の低下の程度は低いとも認定。
しかも大学生もほんの軽い気持ちから投稿したという点が考慮され、慰謝料額は20万円、弁護士費用の負担として10万円の合計30万円の負担のみとしています。
デマ拡散とネットリテラシーについて
今回の事件に限らず、SNSでデマが拡散し問題となったケースは後を絶ちません。
問題の大小を問わず、日常的に起きている問題であると言っても過言ではありません。
冒頭でご紹介した「コロナ禍のトイレットペーパー」もその一つで、熊本地震の際には「ライオンが逃げた」といったデマ情報を拡散したとして逮捕者も出ています。
「阪神優勝で大学の単位が与えられる」「コロナ禍のトイレットペーパー」「ライオンが逃げた」というものは、大半の人は虚偽であると捉えることができるものです。
ただ、「阪神優勝」のケースでは、「許せない」と感じる人がまとめサイトに投稿することによってデマが拡散されることになりました。
「コロナ禍のトイレットペーパー」「ライオンが逃げた」というものも、コロナ禍や大地震の状況で、正義感故に拡散されるスピードが早かったということが言えるでしょう。
いずれにおいてもネットリテラシーのなさが、このようなデマを拡散されるもとになってしまうのです。
そのため、情報を発信する側も真実ではない内容を安易に発信することは良くないですし、また受け取る側も情報を鵜呑みにせず、根拠を必ず確かめることが必要でしょう。
 まとめ
まとめ
今回は、虚偽発言をSNS投稿したことによって社会的評価の低下に繋がったというケースについて、判例をもとにしてお伝えしました。
SNSの普及は人との繋がりを容易にし、誰とでも簡単にコミュニケーションが取れる時代になりました。
しかし、上記でもお伝えした通り、虚偽の情報であっても本当のように拡散されてしまい、大きな問題となるケースが増えています。
仮に軽い気持ちで投稿したとしても、社会を巻き込む大問題へと発展してしまうようなこともありますので、ネットリテラシーを持ち合わせておく必要があるのです。
また、本件のような名誉を毀損するような不法行為に困っているときには、弁護士に相談するようにしましょう。
今後の備えとして弁護士保険の利用を検討してみよう
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
今回の記事を参考にして、上手に弁護士保険を利用しましょう。