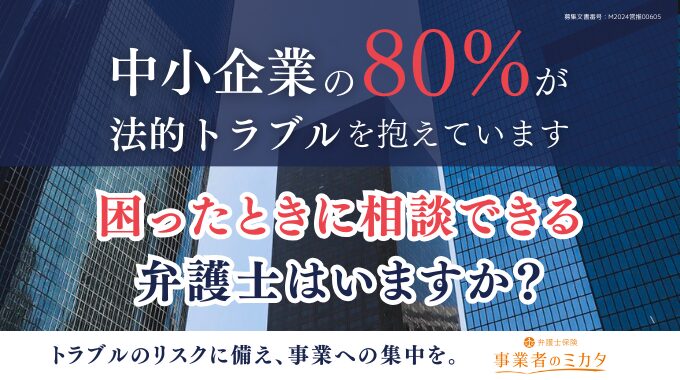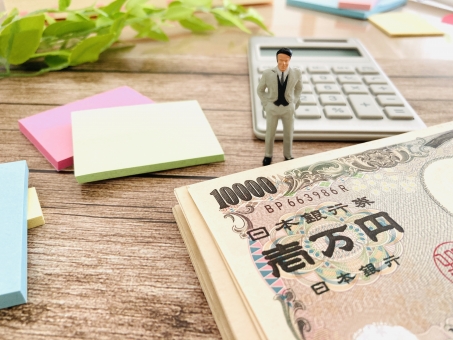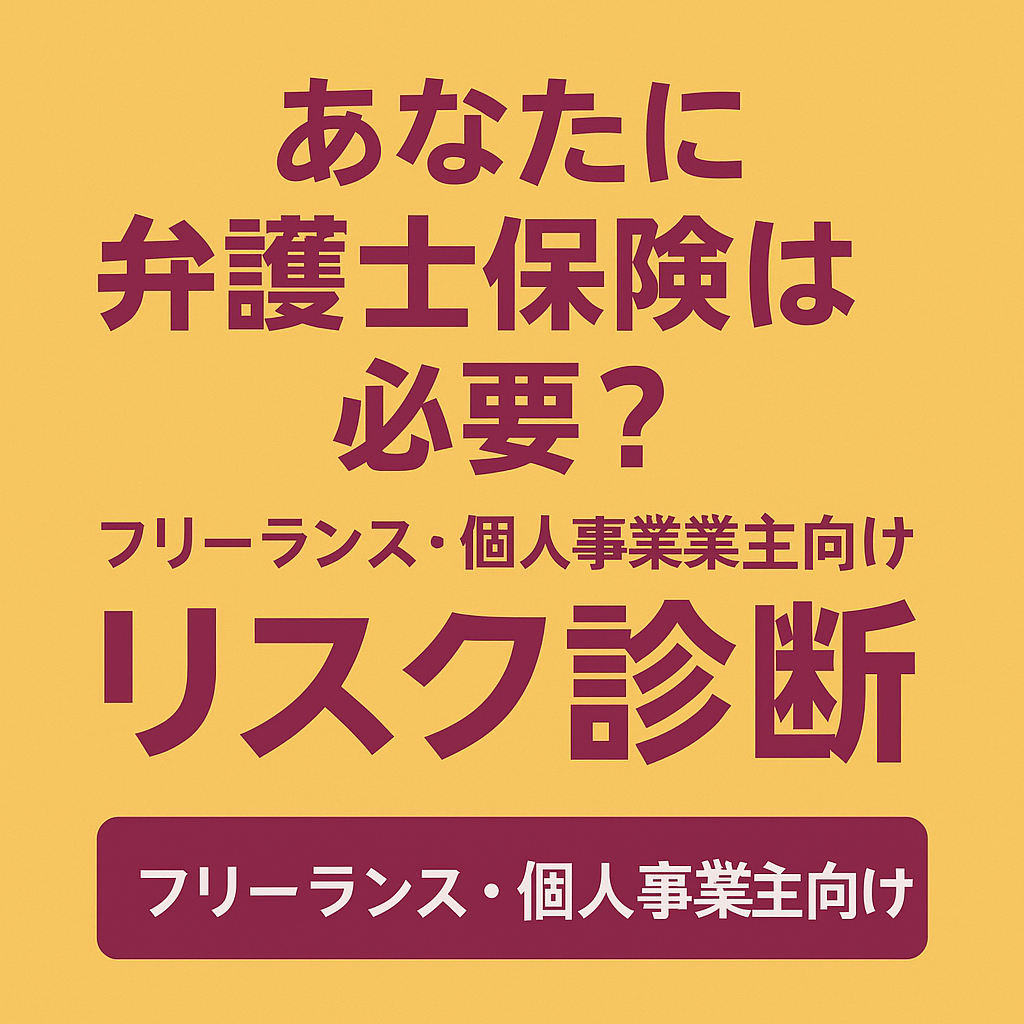ネイルサロン経営者が頭を悩ませることのひとつに「クレーム対応」があります。
- 仕上がりが良くなかった
- 爪を切りすぎて出血してしまった
- メニューの金額より高かった
- スタッフの対応が良くなかった
クレームの多くは、このような内容が多いのではないでしょうか。
スタッフや経営者はしっかりとクレームの内容をお聞きしたうえで謝罪を行い、必要に応じて無料でのお直しや返金対応されていることだと思います。
しかし、謝罪やお直し、返金では済まないようなクレームに遭遇したという経営者も多いのではないでしょうか。
悪質なクレーム、いわゆる「クレーマー」とも感じさせるような、スタッフには身に覚えがないようなことまでクレームを付けてくるようなケースも起きています。
クレームを受けないようにすること、また受けたときにスムーズに解決する方法を店舗スタッフ全員が身につけておくことはとても大切になります。
対処法を間違えてしまうと、多くのお客さまを失ってしまうことや、スタッフの士気を下げて離職を招いてしまうことにも繋がってしまうからです。
ここでは、ネイルサロンでのクレームについて、クレーム対応を受けないようにする方法、適切な対処法、また悪質なクレームの対応方法まで詳しくお伝えしていきます。
こんな疑問にお答えします
Q:クレーム対応で重要なこととは?
A:弁護士保険の編集部の回答サマリー
どれだけ注意していても、クレームをゼロにすることはかなり困難です。そのため、クレームが起きたときにどうするか(ダメージコントロール)、クレーム予防のためにやるべきこと(リスクコントロール)を徹底しておくことが大切です。店舗の全スタッフがどのようなクレームに対しても同じ対応が取れるように、研修などによって徹底して周知させることが重要になります。
クレームとは
「クレーム」にはもともと、「請求」や「要求」「主張」などと言った意味を持つ言葉であり、「苦情」のように「不平」や「不満」と言った要素を持ちません。
ただ、現状では「クレーム=苦情」と捉えられることがほとんどです。
お客さまに対して直接「クレーム」「苦情」と表現できないことから、「コンプレイン」や「ご指摘」などと表現されることが多くなっています。
「クレーム」の多くは、冒頭にもお伝えした通り、スキルの問題や説明不足、スタッフの対応などによるものですから、クレームから顧客満足に繋げるという考え方が正しい受け止め方になるでしょう。
クレームを防止する取り組みによってクレームそのものを減らすというだけではなく、お客さまに満足していただき、安心してサービスを受けてもらうという「サービス向上」に繋がるものなのです。
そのため、クレーム予防には、クレームが起きないようにするためにどうするかという「リスクコントロール」と、クレームが起きたときにどう対処するかという「ダメージコントロール」を持ち合わせておく必要があります。
しっかりと対策に取り組んでおくことによって、お客さまに安心してサービスを受けていただくことはもちろんのこと、スタッフが安心して働ける環境にするという役割があるのです。
ネイルサロンが受ける可能性があるクレーム
ネイルサロンのクレームには、さまざまな内容があります。
まずどのようなクレームが起きているのか、起きる可能性があるのか把握することが大切です。
それは、実際に受けるクレームだけではなく、クレームを言いたくても言い出せないお客さまの方が圧倒的に多いからです。
1件の大きなクレームの背後には、29件の苦情、300件のクレームには至らなかったミスがあるというハインリッヒの法則が存在します。
そのため、クレーム対応のためだけではなく、顧客満足の一環としてクレームを捉えてみることが大切なのです。
仕上がり
「自分が思っていたイメージと違う仕上がりになってる…」
クレームの中でもっとも多いものは、「仕上がり」に対するものではないでしょうか。
ネイルを受けるお客さまは、仕上がりにワクワクしているものですから、自分が感じているイメージと異なった仕上がりになってしまうと、それだけ落胆も大きくなってしまいます。
経験値の低いスタッフが対応している場合、クレームを言い出しにくいお客さまも少なくありませんので、注意して観察しておくことが大事でしょう。
ジェルの混ぜ方、ブラシの使い方、爪への触れ方、パーツの凸凹への扱い方など、お客さまはそのような振る舞いによってネイリストの力量を見抜いています。
クレームになる前に、ネイリストのスキルをしっかりと磨いておかねばなりません。
剥がれや折れ、欠け
「せっかくネイルしたのに、1週間も経たない間に剥がれてしまった…。」
そのようなクレームもよく聞かれます。
プレパレーションと呼ばれる下準備がしっかりとできていない場合には、早く剥がれることになります。
これは、ネイリストのスキル不足が原因です。
ネイリストからすれば、「お客さまにも非があるのでは…」と言いたいところもあるかもしれません。
お客さまが美容師さんなど、水に触れる機会が多い職業の方であったり、爪が痛んでいるような場合には、早く剥がれたり、欠けたりすることが多くなるからです。
しかし、このようなことは、お客さまに対する事前説明によって回避することができますので、クレームとなってしまうのはやはりスタッフの責任であると言えるでしょう。
ケガや出血など施術ミス
施術の際に活用するニッパーなどによってケガをしたり、出血したりすることも、ネイルサロンではよく耳にするミスではないでしょうか。
もちろん熟練のネイリストであれば、そのようなミスはほとんどなく、新人スタッフやインターンスタッフによるものが多いでしょう。
その場で出血が見られるような場合においては、サロン側で何らかの対処が必要になりますが、場合によっては帰宅後にケガが悪化してしまうようなことも考えられます。
ただ、中にはお客さまの指先にあるささくれや手の荒れなどが酷い場合には、そのまま施術を進めることによってアレルギーを引き起こすようなこともあります。
そのため、事前に十分なチェックが必要であるのは間違いありません。
料金に関すること
料金に関する内容として、
- 思っていた金額よりも高くついた
- 仕上がりに満足いかないから返金してほしい
- 新人スタッフでこの料金はちょっと…
などといったものをよく耳にします。
サービスでお金を取る以上、お客さまがイメージしている仕上がり以上の価値を提供しなければならないのは間違いありません。
とは言え、サロン側が提供できるサービスの質と、お客さまが持っている仕上がりイメージとの差をなくす努力は必要です。
事前の料金説明はもちろんのこと、仕上がりのサンプルの提示、新人スタッフ限定の低価格サービスなど、どのようにすればお客さまに満足していただけるのか追求することは大事なことなのです。
接客マナーや態度
接客マナーや態度についてはネイルサロンだけに限定するものではなく、すべてのサービス業に共通するものですが、お客さまにはもっとも目につきやすい部分でしょう。
特に美意識の高いお客さまがいらっしゃるネイルサロンでは、直接的な接客はもちろんのこと、他のスタッフの態度、言葉遣いなど、ほかの業態よりもより注意しなければならないでしょう。
場合によっては、クレームに対処する態度によって、さらに怒りに火を点けてしまうようなこともあるため、スタッフに対するマネー研修は必須であると言えるでしょう。
クレーム対応で意識すべきこと、やるべきこと
どれだけ注意していても、クレームをゼロにすることはかなり困難です。
そのため、クレームが起きたときにどうするか(ダメージコントロール)、クレーム予防のためにやるべきこと(リスクコントロール)を徹底しておくことが大切です。
店舗の全スタッフがどのようなクレームに対しても同じ対応が取れるように、研修などによって徹底して周知させることが重要になります。
クレーム対応で意識すべきこと
- クレームをしっかりと聞く
- 素直で謙虚な姿勢
- お客様に合った対応を心がける
- 返金のタイミングを間違えない
まずは、お客さまのクレームに対して、しっかりと耳を傾けること。
そしてさらに大切なことは、最後までクレームを聞くことです。途中で話を遮るようなことをしてはなりません。
何かを求められたとしても、「はい」「さようでございましたか」と相手を肯定する言葉で返答するようにし、間違っても「でも」「しかし」などと、否定する言葉や言い訳を伝えないようにします。
興奮されて何度も同じ内容を繰り返されることがありますが、それでもただじっくりと最後まで話を聞く謙虚な姿勢が大事なのです。
話を聞いているうちに、怒りが抜けていったことを感じたら、そこではじめてこちらからクレームに対する提案を行うようにします。
クレームの内容は上記でもお伝えした通りですが、基本的に折り合いがつく対応は、
- 謝罪
- ネイルの修繕、やり直し
- ネイル代金の返金
のどれかになります。
スタッフの態度やマナーによるクレームであれば、謝罪を行い、スタッフ教育を徹底することや、接客マナーを見直しすることが大切です。
仕上がりに満足いかないような、スキルに問題がある場合には、ネイルの修繕、やり直しを行うことになります。
それでほとんどのクレームの対処が可能になります。
返金は最終手段であり、基本的には返金しないスタンスを保っておくことが大事でしょう。
返金したところで、クレームが収まるとは限りません。
また、早い段階で返金に応じてしまうと、スタッフからの信頼を失うことに繋がってしまう可能性があります。
クレーム予防のためにやるべきこと
- スキルを磨く
- コミュニケーション能力を磨く
- 接客マナーを見直す
- カルテの同意書を作成する
- 確認と説明の徹底
基本的なクレーム予防としては、上記の3つ、「スキル」「コミュニケーション能力」「接客マナー」を向上させることが大切です。
何より、これらの不足による問題でクレームを生じさせることがほとんどだからです。
どうしても新人スタッフと熟練スタッフにスキルの差が出るのは仕方のないことですが、研修などによって、その差を埋める努力を積み上げるのはとても重要です。
また、クレームから店舗の運営を守るためには、カルテの同意書を作成すること、そしてお客さまへの確認と説明の徹底も重要になります。
デザインの確認、長さ、形、色などの確認をしっかりと行い、爪の状態によっては多少違ったイメージになるようなことも説明しておくようにします。
さらに、爪の状態が悪いお客さまであれば、ネイルの持ちが悪くなってしまうことがあるでしょう。
そのような場合でも、やり直しは行わない、返金には応じないなどを記載した同意書を作成しておくのです。
中には悪質なクレーマーも存在する
ネイルサロンに限らずですが、悪質なクレーマーも一定数存在することを忘れてはなりません。
たとえば、以下のようなケースです。
- 開始時刻から30分遅刻して来店したのにも関わらず、仕事があって急いでいるから早く終わらせてと要求。
- 施術翌日に「やっぱり気分が変わったから無償でやりなおしをしてほしい」と要求。
上記は極端な例ですが、サロン側に責任があるわけでもないのに無理な要求をしてくるクレーマーも存在するのものです。
悪質なクレーマーへの対処についてはこの後解説しますが、あまりにも理不尽な要求を迫られた場合は専門家の力を借りて法的措置をとることも一つの手段でしょう。
いざとなった場合の弁護士保険
上記では、クレーム対応で意識すべきこと、やるべきことをお伝えしましたが、悪質クレーマーの場合であれば、適切な対応をしても理不尽な要求を受けてしまうことがあります。
例えば、「誠意を見せろ」と言われてしまうようなケース。
基本的には、「謝罪」「やり直し」「返金」しか店舗ができる対応はなく、それ以上の誠意というのは「出来かねます」と答えざるを得ません。
もちろん、悪質クレーマーの手にかかってしまうと、それで納得することはなく、いつまでもクレームが続くことになりますので、どうしてもスタッフや経営者が手を取られることになってしまいます。
そのような場合には、法的な解決を目指す、弁護士に対する相談体制を持っておくことが大切なのです。
ネイルサロンが弁護士への相談体制を持っておくメリット
- 理不尽なクレームから守ることができる
- クレームの抑止になる
ネイルサロン側に落ち度があった場合には、もちろん謝罪し、お直しや返金など適切な対応が必要になります。
ただ、理不尽な要求を必要以上に受けているのであれば、もはや自力で解決を目指さずに、弁護士に解決を委ねることが合理的な方法でしょう。
悪質クレーマーは、店舗側が適切な対応をしても受け入れられないことがほとんどで、やり取りの中でさらに新しい要求が生まれるようなこともあります。
「誠意を見せろ」と言われて、理不尽な返金に応じてしまうようなことがあると、それで解決せずに、さらに要求されることも多いのです。
そのようなことに振り回されるくらいなら、対応が難しいと感じた時点で弁護士に対応を任せてしまうことが良いでしょう。
弁護士に相談した時点で、これ以上の要求は難しいと、クレーマーのほとんどは諦めてしまいます。
弁護士への相談体制を持っておけば、店舗やホームページなどで告知することができ、クレームの抑止に繋げることも可能です。
『弁護士保険』の利用がおすすめ
弁護士への相談にメリットが多いとしても、費用面が気になったり、どこにクレーム対応に長けている弁護士がいるのか知らない方も多いでしょう。
確かに、突発的に弁護士にクレーム対応を依頼すると、費用がかなり高額になることも珍しいことではありません。
中には「顧問弁護士制度」として、安価に相談できる体制をサービスとして提供している弁護士事務所もありますが、相場として月額3万円~5万円が必要で、中には10万円を超えるようなケースもあります。
あくまで相談費用ですので、対処が必要な場合や訴訟が必要な場合には、別途費用が必要になるのです。
そこでおすすめできるのが、法人・個人事業主向けの弁護士保険です。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q.ネイルサロンで起こり得るクレームはどのようなものがありますか?
A.クレームの多くは、スキルの問題や説明不足、スタッフの対応などによるものがあります。ただ、サロン側に問題がないにも関わらず理不尽な要求をする悪質なクレーマーも存在します。
Q.クレーム対応で意識すべきことを教えてください。
A.まずは、お客さまのクレームに対して、しっかりと耳を傾けること。そしてさらに大切なことは、最後までクレームを聞くことです。途中で話を遮るようなことをしてはなりません。
Q.クレーム予防のためには具体的に何をすればいいですか?
A.基本的なクレーム予防としては、上記の3つ、「スキル」「コミュニケーション能力」「接客マナー」を向上させることが大切です。