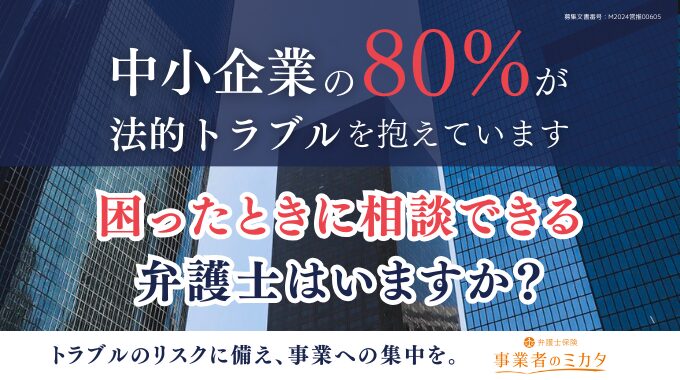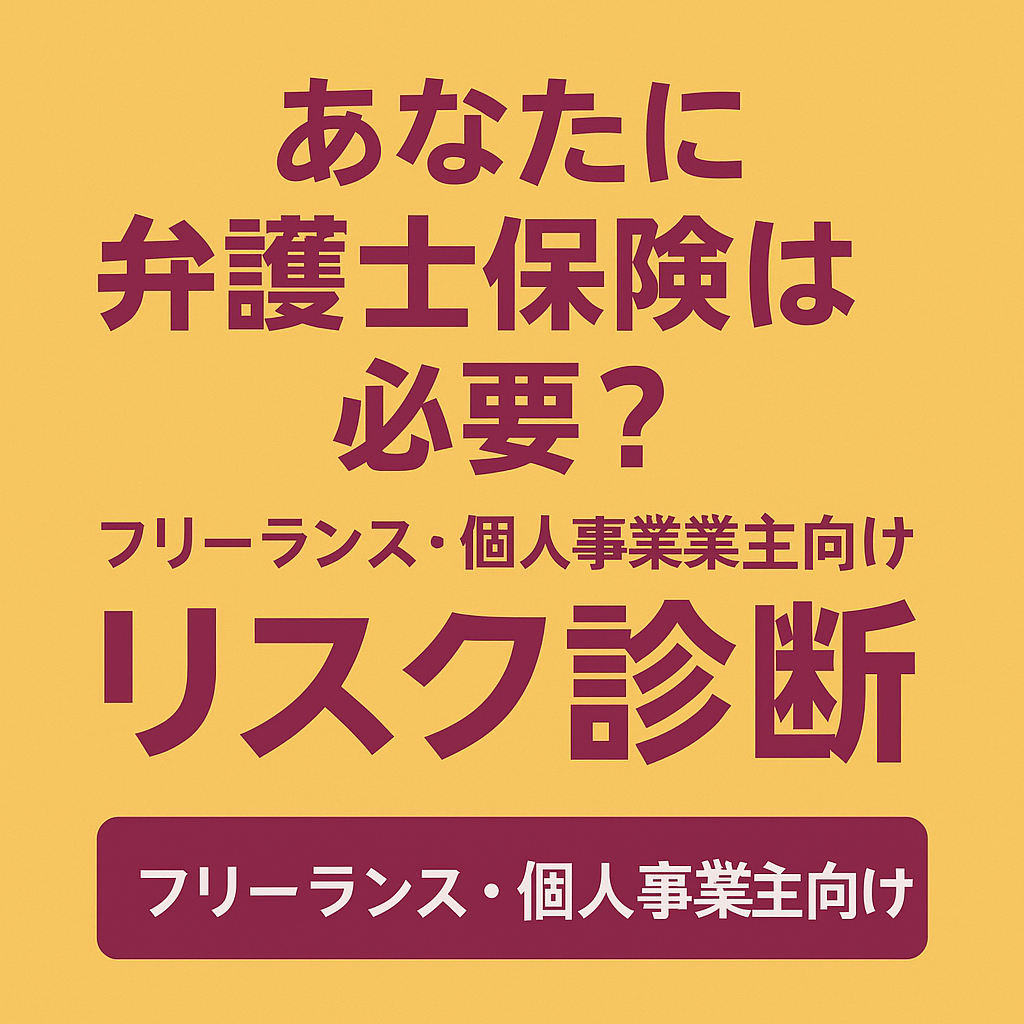多くの児童生徒が利用する『学習塾』。
小中校によっても異なりますが、学習塾を利用する割合は高いことが知られています。
しかし、子どもの数が減少しているのに伴い、生徒の獲得がかなり厳しい状況になっています。
そのため、各学習塾においては広告や無料体験授業、見学会など、集客にさまざまな工夫や努力している現状が伝わってきます。
つまり、生徒を確保するのに、多くの経費を費やさなければならない状況にあるのです。
そのような中で、学習塾の『授業料の滞納』が大きな問題として、注目されています。
学習塾において生徒数確保がたいへん厳しい中で、滞納者が増えてしまうと、経営に大きな影響を与えてしまうことになります。
ただ、滞納と言ってもその理由はさまざまであるため、それぞれに応じた対策を講じておくことが重要になります。
ここでは、学習塾の経営者が知っておくべき法律トラブルとして『滞納』をクローズアップし、その対処法など詳しくご紹介しましょう。

学習塾経営者が直面するトラブルの一つが『滞納金』
学習塾のトラブルとして『滞納金』があるとお伝えしましたが、数あるトラブルの中の一つとして数えられます。
そのため、経営状況を悪化させないために滞納に対する対策は必要ですが、さまざまなトラブルを起こさないようにする、また起こった時に速やかに対処できる対策を講じておくことが大切なのです。
例えば、学習塾の受講料面だけで捉えるとしても、『通塾しても成果が見られない』『志望する大学に合格できなかった』などといった理由で滞納があったり、支払い済みの受講料の返還を求められたり、損害賠償請求されるようなこともあります。
特に、学習塾の性質上、受講料に見合う授業が受けられたかどうか、費用対効果があったのかどうか、といった部分に関しては、経営者側の想いと生徒や親の想いとは違うことも多いでしょう。
実際に消費生活センターには、学習塾に対する受講料に対する苦情も多いことが知られています。
そのようなことから、利用規約・通塾規約をしっかりと整備しておくことはトラブルを未然に防ぐためにとても重要であり、また常に法律の観点から対策を講じておくことが不可欠だと言えるのです。
滞納金がある際に確認しなければいけないことは?
冒頭からもお伝えしている通り、学習塾において滞納は、経営状態を悪化させてしまうもっとも高いリスクのあるものだと言えます。
そのため、滞納が確認でき次第、滞納金を回収したいのは山々だと思いますが、そのためには事前に確認しておくべきことがあります。
法的根拠があるか
滞納金がある際に、滞納金を回収するための法的根拠があるかどうか、確認しておくことが大事です。
というのも、学習塾が法律の定めに従った契約を行っておらず、その法律違反をもとにして滞納しているといったケースも少なくないからです。
例えば、学習塾を利用することに対する親の同意です。
学習塾の受講料は月額数千円から数万円程度、また生徒の学力などに合わせて教材を適宜購入する必要があります。
当然ながらその負担はほとんどのケースで親がするものと考えられますが、そのためには事前に契約を提携しておくことが重要になります。
仮に、親の合意なく子供が勝手に契約したような場合には、滞納があったとしても法的根拠が整っていると言えない可能性があります。
上記でもお伝えした通り、消費生活センターには学習塾に対するさまざまな苦情が少なくありません。
その中には、学習塾の違法行為も含まれていますので、まずは法的根拠が整っているのかどうか、確認することから始める必要があります。
利用申込書や契約書などが整備されているか
学習塾はさまざまな法律に関わっており、それらの法律に基づいた『利用申込書』や『契約書』などを整備しておく必要があります。
関わっている法律の中には、学習塾にもっとも関係する『特商法(特定商取引に関する法律)』、生徒や親の個人情報に対する『個人情報保護法』、塾で活用するプリントなどに対する『著作権法』などがあります。
その中でも『特商法』は、学習塾の長期的な利用契約や一定以上の受講料が必要になることから、ほとんどの学習塾が法律の対象になると考えられます。
『2か月を超える契約』『年間5万円を超える契約』が条件とされていますが、このような条件をみると、ほぼすべての学習塾が当てはまるのではないでしょうか。
対象となっている学習塾は『特定継続的役務提供事業者』として、『利用申込書』や『契約書』と共に、契約の概要を記載した『概要書面』と呼ばれる書面を整備して、契約時に交付しておく必要があります。
『概要書面』とは、費用や支払い時期、提供期間、クーリングオフ、中途解約などといった、契約書に定められている内容を詳しく記してあるもので、契約後には速やかに契約書面と共に渡さねばなりません。
ただし、記載事項の不備を裁判所が認め、契約の解除を認めた判例もあることから、法的な根拠として採用できるものを整備しておく必要があります。
学習塾の中には、契約書を整備していないケースがありますが、そのような場合には契約そのものが無効となってしまうことも考えられます。
最悪の場合、受講料を全額返還しなければならないような事態も考えられますから、注意して整備に取り組んでおくようにしましょう。
実施できることは?
法的根拠のある受講料の滞納がある場合、滞納を回収するための取り組みが必要になります。
学習塾の中には、滞納に対して回収を行うことによって、「評判が悪くなってしまうのでは…」と考えて、強く請求を求められないケースも生じているようです。
ただ、受講料をおさめてすべての生徒が公平に学習塾を利用していることになるため、滞納はむしろ評判を落としてしまう根源になりかねないと理解しておくことが重要です。
とは言え、事業が教育である以上、考慮しなければならないことも多いでしょう。
仮に、裁判や強制執行などといった強制力の高い回収を実施した場合、近隣に情報が広がってしまう可能性もありますから、注意して実施することが必要です。
一般的な滞納の回収方法
一般的な滞納の回収方法は、電話や手紙、訪問などになります。
単に忘れていたようなケースや、忙しくて振り込みにいけなかったようなケースであれば、すんなりと応じてもらえる可能性があります。
また、電話や手紙では反応がないとしても、在宅時に訪問することによって支払ってくれる可能性もあるでしょう。
しかし、滞納が深刻な事態になっているようなケースの場合であれば、支払いに応じてもらえない可能性が十分に考えられます。
ただ、だからと言って、滞納しているまま放置していると、時効が完成してしまうこともありますから、深刻な状況であれば次のような回収方法に取り組めばいいでしょう。
内容証明書
『内容証明書』とは、今回のケースのように滞納している受講料を回収するために利用されるケースが多い郵便サービスのことを指します。
普通郵便とは違い、確実に相手側に内容を伝えることができますので、滞納に対して督促を行ったことを証明でき、時効の完成を止める効果があります。
内容証明書は自身で送付することができますが、弁護士に依頼しておけば、弁護士名で送付できますので、滞納者にとっては心理的なプレッシャーはかなり大きくなります。
弁護士の名前を出すだけで回収できるケースが少なくないことから、かなり有効な回収方法と言えるでしょう。
支払い催促
内容証明郵便を送付しても、支払いに応じてもらえなかったり、返事がなかったりと言うことがありますが、そのような場合には『支払い督促』の手続きが取られるケースが多いです。
『支払い督促』とは、今回のように受講料の滞納が発生しているような場合に、簡易裁判所の書記官に申し立てを行い、裁判所から支払いを命じることができる方法になります。
裁判所に出向く必要はなく、書面によって行われる手続きであり、証拠を提出する必要もありません。
また、手続き費用もリーズナブルで、例えば滞納が100万円である場合に民事訴訟を起こせば、手数料は1万円になりますが、支払い督促の場合には5,000円で済みます。
簡易裁判所で申し立て手続きを行えば、裁判所書記官がその内容を審査したうえで、相手方に対して滞納の支払いを命じる支払い督促を発することになります。
仮に、相手側が支払いを拒み続けているような場合、「仮執行宣言付支払督促」を発して、強制執行を申し立てることが可能になります。
ただし、相手側が異議を申し立て、反論してくるような場合には、民事訴訟に移行することとなってしまいます。
140万円以下の紛争の場合には簡易裁判所で、140万円を超える場合には地方裁判所で行われることになります。
上記のようなトラブルがある際には、弁護士に相談しよう
冒頭から学習塾の経営者が知っておくべきトラブルについてお伝えし、トラブルの中でも特に経営状態に大きな影響を及ぼす滞納についてご紹介してきました。
滞納が生じているということが生徒の中で広がってしまうと、不公平感が高まってしまいますので、きちんと回収しておくことによって公平な運営が可能になります。
ただ、注意点としてお伝えした通り、学習塾側に法的な根拠が整っていないような場合、契約は無効として滞納を回収するどころか、今まで支払いを受けた受講料を返還しなければならない可能性があります。
そのようなことから、トラブルが生じた場合には、法律を十分に理解している弁護士に相談することが適切です。
弁護士を活用するメリット
弁護士に相談すれば、滞納トラブルを解決することはもちろんのこと、契約書の作成をはじめ、さまざまな法リスクに対するアドバイスを受けることができます。
滞納を回収する方法として『内容証明書』『支払い督促』についてご紹介しましたが、これらはリーズナブルに、また手軽に取り組める方法です。
しかし、実際に深刻な滞納トラブルが生じているようなケースでは、なかなかこのような対応でも支払いに応じてもらえないことが多いのです。
そのような場合には、民事訴訟に移行するケースがあり、また強制執行の申し立てなど、専門的な手続きを有するケースが少なくありません。
そのため、弁護士の力を活用することは、学習塾を運営するうえでも、有効な手段となるのは間違いありません。
弁護士を活用するうえでの注意点
弁護士を活用するうえで、考えておかねばならないことは、『弁護士費用』に関することです。
滞納を回収するにあたり、弁護士に依頼する場合には、弁護士に対する費用と回収費用との兼ね合いを十分に考慮しておく必要があります。
場合によっては、手続き費用が回収費用を上回る場合には、弁護士に依頼することが難しいケースも考えられます。
弁護士保険も一つの選択肢
弁護士は学習塾の滞納の防止や回収に、とても有効であることをお伝えしてきました。
ただ、上記でもお伝えした通り、弁護士費用の負担が厳しく、依頼することが難しいケースも多いのではないでしょうか。
また、そもそも学習塾の滞納に精通した弁護士が地域に存在するのか、また十分な経験を有しているのか調べることは困難です。
ただ、このような事情で弁護士への依頼を諦めている方でも、『弁護士保険』の活用によってうまく解決できる可能性があります。
弁護士保険とは
『弁護士保険』とは、割安な費用で加入できる保険サービスで、いつでも無料で気軽に弁護士に相談できる体制を構築できる特徴があります。
さらに、『弁護士保険』の加入を告知することができますので、そもそも滞納を起こさない、トラブルの抑止力とすることができるのです。
さらに、どうしても回収できずに、弁護士によって訴訟対応が必要な状況になったとしても、通常の弁護士費用よりも安価に活用できますので安心です。
そのため、深刻な事態になる前に、対処することが可能になります。
何より、学習塾の経営は、生徒を集め、運営に十分注力しなければならないことから、法的な対処を同時進行させることは困難です。
弁護士保険であれば、冒頭からお伝えしているような法的トラブル全般を補償範囲としているため、安心して学習塾経営に専念することができます。
もし、深刻な滞納トラブルによって弁護士に訴訟や強制執行の申し立てなどの依頼をしなければならない場合であっても保険が適用され、通常費用よりも安価に利用することが可能です。
ぜひうまく弁護士保険を活用して、学習塾を守っていきましょう。
法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。