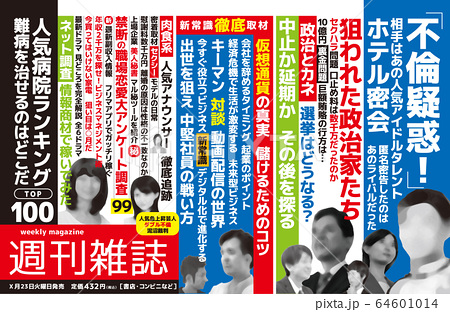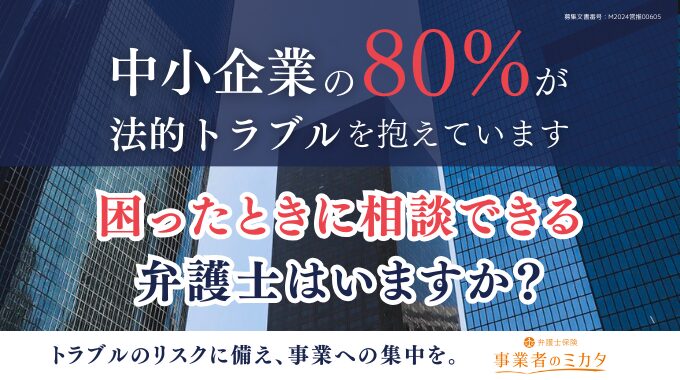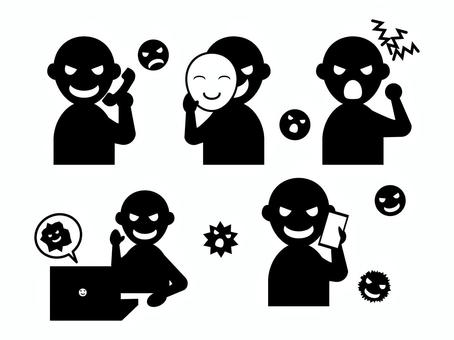一部の週刊誌などにおいて頻繁に、政治家や芸能人などのゴシップが報じられています。
しかし、そもそもこのような報道は名誉毀損に当たるものではないのかと、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、週刊誌「FRIDAY」の紙面およびウェブサイトに掲載された記事によって名誉毀損されたとして、原告である市長が損害賠償を求めた事例をご紹介します。
また、政治家のような公人に対する報道が、どこから名誉毀損として認められることになるのかについてもご紹介していきます。
こんな疑問にお答えします
A.事実の真否を判断して真実であるとの証明があれば、名誉毀損が成立しないことになります。政治家をはじめ、公務員は公人として存在するため公人そのものの名誉よりも国民の利益が尊重されます。しかし、週刊誌による記事で誹謗中傷を受けている場合もあるでしょう。ご自身や家族を守るためにも、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
週刊誌が問われやすい名誉毀損とは
はじめに、名誉毀損とはどのような罪なのか整理しておきましょう。
名誉毀損とは、人前で具体的な事実を述べてけなし、相手の名誉を傷つける犯罪を指します。名誉毀損は「公然」と「事実を摘示」して「人の名誉を下げたこと」を成立要件とします。
週刊誌は基本的に公に出回る出版物であり、記事に具体的な内容が含まれていることが多いものです。その内容が被害者の社会的評価を下げるものであれば、名誉毀損が成立しやすくなります。
名誉毀損は、公然とさらされた内容が真実かどうかに関係なく成立する罪です。
つまり、週刊誌が虚偽の内容を掲載しても正しい事実を述べても、法的処罰の対象になり得るということです。
名誉毀損の成立要件や侮辱罪との違いはこちらの記事をご覧ください。
関連記事
-
-
【図解でわかりやすく】名誉毀損と侮辱罪の要件の違いと慰謝料の相場(悪い・根も葉もない噂を流される場合はどっち?) ※元弁護士作成記事
人に対して誹謗中傷する発言や侮辱的な発言をした場合、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。 これらはどちらも「相手に対して悪口を言った」場合に成立するイメージがありますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょう …
週刊誌は実際に名誉毀損で訴えられているのか?
週刊誌は、実際に名誉毀損で訴えられています。
週刊誌が訴えられるのは決して珍しいことではなく、週刊誌の記者や編集者、さらには発行元の企業に対して損害賠償を請求されています。
週刊誌が訴えられる罪は、名誉毀損以外の不法行為も成立することがあります。
週刊誌が訴えられやすい罪や情報提供者の責任、訴えられても記事が出回り続ける理由についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事
-
-
週刊誌が訴えられないのはなぜ?成立しやすい罪や情報提供者の責任を解説
有名人の不倫報道や私生活への介入など、連日のように個人のプライベートを暴露する週刊誌。騒動の渦中にいる当事者にとっては、今後の人生を左右する大問題に発展することもあるでしょう。 無断でプライバシーを公開された場合「週刊誌 …
次の章では、実際に週刊誌が名誉毀損で訴えられた事例を紹介します。
【事例で学ぶ】週刊誌の疑惑記事が名誉毀損に~市長が損害賠償請求を行った裁判事例
週刊誌「FRIDAY(平成29年4月28日号)」と運営するウェブサイト「FRIDAIデジタル」に掲載、
この内容の記事によって原告は名誉毀損されたと主張し、慰謝料1000万円、弁護士費用相当額100万円の合計額1100万円を求めたケースです。
裁判所は原告の主張を認め、 慰謝料150万円、弁護士費用相当額15万円の合計額165万円の支払いを命ぜられています。
どのような内容の事例なのか、詳しくお伝えしていきましょう。
ケースの概要
週刊誌「FRIDAY(平成29年4月28日号)」と運営するウェブサイト「FRIDAIデジタル」において、「茨城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事を掲載。
この記事は、「守谷市の市長である原告の経営するオーナー企業が、守谷市の公共事業の入札で有利な落札をしているのではないか」という疑惑を指摘した内容となっています。
原告である市長はこの記事に対して、市長および守谷市議会議員である期間内に、企業での経営に関与している事実は存在しないと主張しています。
また、守谷市が発注する際に行われる競争入札において、不公平な形で落札業者を決定するような官製談合を行った事実もないとしています。
そのため、記事内容である「市政運営は真っ黒である」といった事実はまったくないと主張されました。
被告であるFRIDAY側は、「今でもオーナー経営者ではないか」「落札からみると守谷市の入札はゆがんでいるのではないか」という疑惑を指摘した意見、ないし論評であると主張。
守谷市における公共事業の入札を監視し、問題提起するという公益を図る記事であると主張し、原告の主張に反論されています。
争点となった内容
本件において、争点となった内容には4点あります。
- 記事の事実と社会的評価の低下の有無について
- 違法性がないとして処罰されない事情があるかどうか
- これらの損害について
- 名誉回復措置が必要であるかどうか
原告の主張としては、本件の記事は、地方自治法および守谷市の条例に違反するものであり、官製談合を行い、市政運営は真っ黒であるといった事実を適時したものであるために、社会的評価を低下させることは明白であるとしています。
また、証拠もなく、客観的事実に反する記事を掲載したことは極めて悪質であり、公益を図る目的などないと主張。
そのため、被った精神的苦痛の慰謝料は1000万円を下ることはないと主張し、弁護士費用と合わせて1100万円、また、同時に謝罪広告の掲載も求めています。
被告であるであるFRIDAY側は、あくまで「疑惑」として報道しており、読者はすべて事実として捉えていないと主張しています。
記事の内容は公共的関心ごとであるために、問題提起する公益を図る記事であるとしています。
裁判所の判断
今回の記事では「茨城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」という見出しと共に、「地方の殿様の闇」「自らのオーナー企業で市の公共事業を次々と落札」といった文言が記載されています。
その内容からしても、「疑惑」という記述はされているとしても、地方自治法や守谷市の条例に違反し、官製談合などの違反や不正が行われている印象を抱かせるものであるから、社会的評価を低下させるものだと認められるとしています。
FRIDAY側の主張に対しては、地方自治体の首長ないし議員と関連企業との関係性について問題提起することは正当なものであったといえ、守谷市政治倫理条例違反に関する論評については違法性が阻却されると認定されています。
それらの事情を考慮すれば、慰謝料150万円、弁護士費用相当額15万円の合計額165万円の支払いが相当だと認められています。
また、損害賠償義務が認められることによって、名誉回復も想定されることから、謝罪広告の掲載が必要とまでは認められないとしています。
政治家に対する記事や投稿は名誉毀損になるのか
政治家に対する誹謗中傷など、SNS上で見かけるようなことがありますが、それらの投稿や記事は、どこから名誉毀損となるのでしょうか。
デマだけではなく事実であるとしても名誉毀損と認められる可能性が
一般的にSNSなどのネット上においてデマを流すような行為は、名誉毀損として認められ、損害賠償義務が生じる可能性があります。
では、デマではなく事実であれば、名誉毀損として認められることはないのでしょうか。
不倫などのスキャンダルが公になって、社会的評価が低下してしまったという政治家や芸能人は珍しいことではなくなってきたように感じます。
仮にこの不倫が事実であるとしても、名誉を毀損してしまうことは明らかです。それが一般の方だけではなく、政治家や芸能人であっても同じなのです。
刑法230条には次のように定められています。
『公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。』
つまり、SNSなどに投稿した内容が、事実の有無に関わらず名誉毀損として成立すると定められているのです。
政治家に対する名誉毀損は成立するのか
上記でもご説明した通り、名誉毀損について刑法230条で定められていますが、政治家については刑法230条の2の2項において次のように定められています。
『公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。』
つまり、政治家をはじめ公務員は公人として存在していますから、公人そのものの名誉よりも、国民の利益が尊重されているのです。
そのため、事実の真否を判断して、真実であるとの証明があれば、名誉毀損が成立しないことになります。
さらに、虚偽であるとしても、真実であると信じたことについて、相当の理由があると認められた場合においても、名誉毀損は成立しないとされているのです。
冒頭でご説明したケースにおいて、次のような点が争点とされていました。
- 記事の事実と社会的評価の低下の有無について
- 違法性がないとして処罰されない事情があるかどうか
「記事の事実」と「違法性がないとして処罰されない事情」について争点とされていたのですが、これがまさに政治家に対して名誉毀損が成立するかどうかのポイントだったわけです。
「事実の真否」、そして虚偽であるとしても「真実であると信じたことについて相当の理由があるかどうか」ということに注目されたと言えるでしょう。
まとめ
週刊誌に掲載された政治家に対する疑惑の記事が、名誉毀損に当たるとして損害賠償を命ぜられたケースについてご紹介しました。
政治家をはじめとする公務員は、公人であるがために、国民の利益が尊重されることになりますので、名誉毀損に該当しない可能性があります。
もし、誹謗中傷などによってお悩みの場合であれば、実績豊富な弁護士に速やかに相談することをおすすめします。
弁護士への相談方法や窓口は、こちらの記事で解説しています。
関連記事
-
-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
週刊誌による誹謗中傷のトラブルを弁護士に相談するメリット
週刊誌による報道被害の対応を弁護士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 報道被害から相談者を守り、真実を伝えてくれる
- 報道後の風評被害を抑止してくれる
- その他メディアの取材から家族を守ってくれる
誹謗中傷のトラブルは、とにかく迅速な対応が求められます。
ご自身の将来や家族を守るためにも、弁護士のサポートを受けて解決する必要があるでしょう。
弁護士費用に不安があるなら弁護士保険の利用も視野に
弁護士へ相談するにあたり、気になるのは弁護士費用の負担でしょう。そこでおすすめしたいのが、弁護士保険です。
弁護士保険は、日常生活の個人的トラブルや事業活動の中で発生した法的トラブルに対し、弁護士を利用した時にかかる弁護士費用を補償する保険サービスです。
通常、弁護士を通してトラブルを解決しようとすると、数十万から数百万単位の弁護士費用がかかる場合があります。
弁護士保険に加入しておくことで、法的トラブルが発生した場合に弁護士に支払う費用を抑えられます。
誹謗中傷を早期解決するためには、弁護士保険を視野に入れましょう。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q.政治家に対する記事や投稿は名誉毀損になるの?
A.事実の真否を判断して、真実であるとの証明があれば名誉毀損が成立しないことになります。政治家をはじめ公務員は公人として存在するため、公人そのものの名誉よりも国民の利益が尊重されているのです。
Q.そもそも週刊誌は訴えられるものですか?
A.週刊誌は実際に名誉毀損で訴えられています。週刊誌が訴えられるのは決して珍しいことではなく、週刊誌の記者や編集者、さらには発行元の企業に対して損害賠償を請求されています。
Q.週刊誌の記事による誹謗中傷が心配です。家族もいるので被害がないか不安です。
A.誹謗中傷のトラブルは、とにかく迅速な対応が求められます。ご自身の将来や家族を守るためにも、誹謗中傷に詳しい弁護士のサポートを受けて解決する必要があるでしょう。