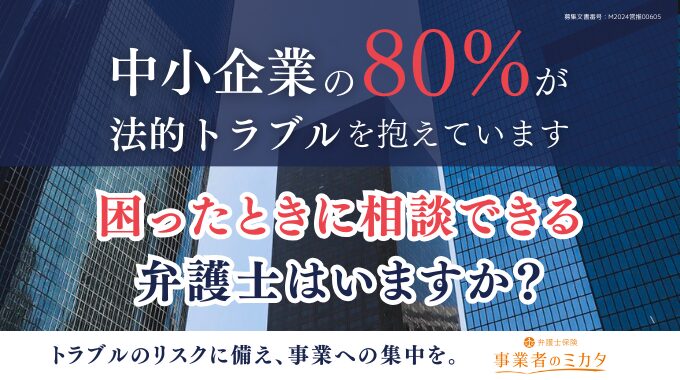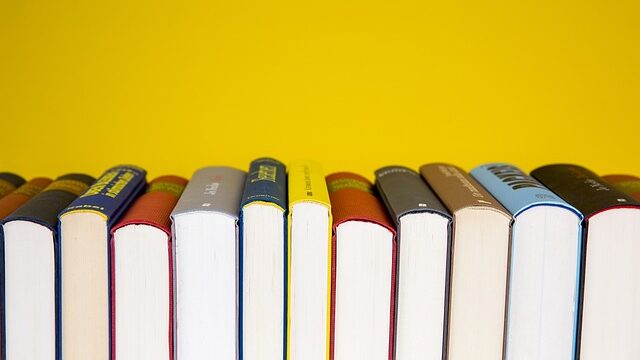SNSを利用する人が多い昨今、被写体の許可をとらないまま動画や写真が公開されてしまうケースが問題になっています。場合によっては、このような行為は「肖像権の侵害」に該当します。
本来、動画や写真を撮影・公開するときは被写体の許可を得なければなりません。
本記事では、肖像権の定義や肖像権の侵害になる基準について詳しく紹介しています。
著作権との違いも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
こんな疑問にお答えします
Q:具体的にどのような行為が「肖像権の侵害」となるのでしょうか?また、肖像権を侵害された場合の対応方法についても教えてください。
A:肖像権侵害となりやすいケースは、以下になります。
- 許可を出していないのに無断で動画や写真を公開された
- SNSなど誰もが閲覧できる場に動画や写真を投稿された
- 自分の顔が明確に映っている動画や写真を無断で公開された
- 自宅内など、私的な空間で過ごす様子を撮影・公開された
肖像権を侵害された際は、以下の方法で対応しましょう。
- 動画や写真の削除を依頼する
- 民事責任を追及する
- 弁護士に相談する
肖像権とは
肖像権の定義
肖像権とは、「無断でみだりに自分の動画や写真を撮影・公開されない権利」です。
法律で定められた権利ではなく、判例によって確立されてきたことが特徴です。
インターネットが普及し誰もが気軽に動画や写真の投稿ができる現在、肖像権の侵害は身近な問題となっています。
著作権との違い
著作権と肖像権は混同されやすい権利ですが、両者には以下の違いがあります。
| 肖像権 | 著作権 | |
|---|---|---|
|
権利の対象 |
人の顔や姿 | 人の著作物 |
|
目的 |
個人のプライバシーを守る |
個人の利益を守る |
|
法律で定められているか |
法律での規定なし |
著作権法にて規定 |
| 侵害された場合の対応 | 民事責任の追及が可能 |
刑事責任の追及が可能 |
上記のように、肖像権と著作権には明確な違いがあることを認識しておきましょう。
肖像権を構成する要素
肖像権を構成する要素は以下の2つです。
- プライバシー権
- パブリシティ権
プライバシー権とは、個人情報などプライベートに関する事柄を守るための権利で、一般の人を含め誰もが持っています。
またパブリシティ権は、経済的価値のある著名人の名前や写真を特定の第三者に帰属させる権利です。特定の第三者とは、ライセンス料を支払っている人になります。
そのため無断で著名人の名前や写真を商用目的で利用すると、パブリシティ権の侵害に該当します。
民事責任の追及は可能である
肖像権の侵害は刑法での罰則がないため、刑事責任を問うことはできません。
しかし、民事責任の追及による損害賠償の請求は可能です。
民事責任を追及する際、不安や疑問点があれば弁護士に相談するのも良いでしょう。専門家の立場からアドバイスをもらえます。
肖像権侵害になる基準
肖像権は法律で規定されていないので、明確な「肖像権侵害になる基準」もありません。
ただし、一般的に肖像権侵害になる基準として以下の4つが挙げられます。
被写体からの許可なく動画や写真を公開した場合
最初に、被写体からの許可なく動画や写真を公開した場合です。
被写体から撮影の許可を得ていても、「公開しても良いか」は別の問題であるため必ず確認をとる必要があります。
反対に、被写体から撮影・公開の許可を得ていれば基本的に肖像権の侵害には該当しません。
動画や写真の拡散性が高い場合
動画や写真の拡散性が高い場合も該当します。
拡散性の高いSNSなどに投稿された場合、その動画や写真は不特定多数の目に触れるでしょう。
公開を希望しない動画や写真が拡散された場合、被写体は大きな苦痛を受けるので肖像権の侵害であると認められやすくなります。
被写体の特定が可能である場合
被写体の特定が可能である場合も、当てはまります。
しかし、ピントがきちんと合っていない場合・写り込みが小さい場合は、肖像権侵害として認められない場合もあります。
私的な場での撮影である場合
最後に、私的な場での撮影である場合です。
私的な場とは、例えば自宅やホテルの個室、病室などが該当します。
一方、道路上や公共施設など公的な場での撮影であれば、肖像権侵害に該当しないケースがほとんどです。
肖像権侵害の判例
ここでは、肖像権侵害の判例を2つ紹介します。
子どもの写真を虚偽内容とともに無断公開されたケース
1つ目は、「夫婦が公開していた子どもの写真を、Twitter上で虚偽の内容文とともに無断転載された事例」です。
投稿内容は、「自分や孫の意思に反して嫁が孫を安保法案反対のデモに連れて行った。そして、孫が熱中症で死んだ。」というものでした。
裁判で被告は、「すでに公開されていた写真であるため肖像権の侵害には該当しない」という旨を主張。しかし、本件では肖像権の侵害が認められ、Twitter社には情報開示が命じられました。
出典:J-CASTニュース2017年02月24日20時04分
無断で写真の撮影と公開をされたケース
2つ目は、「最先端のファッションを紹介することを目的として、街を歩いていた女性の写真を無断で撮影後、被告のサイトで公開された事例」です。
撮影された当日、原告は「SEX」という文字が胸元にデザインしてある海外の有名ブランドの服を着用していました。
そして写真が公開された後は、2ちゃんねるにて原告に対する誹謗中傷が書き込まれ、本写真は複製・拡散までされるという事態に発展。
その後、原告がすぐに抗議したためサイト内から写真は削除されましたが、すでに拡散されていた写真により誹謗中傷は繰り返されました。
裁判所は、本件について「原告の容貌が明確にわかる写真である点」や「SEXというデザイン入りの服を着用した姿を公開された精神的苦痛」を考慮し、肖像権の侵害であることと損害賠償請求を認めました。
肖像権侵害への対応方法
肖像権を侵害された際は、以下の方法で対応しましょう。
動画や写真の削除を依頼する
まずは、早めに動画や写真の削除を依頼することです。
多くのサイトやSNSの運営会社は、削除申請フォームを設けています。削除申請フォームに名前や連絡先、削除依頼理由などの必要項目を入力して申請しましょう。
肖像権の侵害が認められた場合、該当する動画や写真を削除してもらうことが可能です。
インターネット上に動画や写真が投稿された以上は、放置しているとさらに別の場所にも拡散されるリスクがあります。二次的な拡散を防ぐためにも、できるだけ迅速に行動しましょう。
民事責任を追及する
「民事責任の追及」も選択肢です。
動画や写真の投稿者が知人など面識がある人の場合、身元が明らかであるためすぐに民事責任を追及できます。
しかし、匿名の投稿者である場合はまず加害者を特定する作業から始めます。
その際は「発信者情報開示請求の手続き」が必要です。
発信者情報開示請求の結果、投稿者の身元が特定できればそこではじめて民事責任を追及できます。
弁護士に相談する
弁護士に相談するのも良いでしょう。
特に、発信者情報開示請求の手続きを自力で行うとなれば非常に大きな負担が掛かります。初めての手続きに戸惑うことも多く、思うように対応できない場面も出てくるでしょう。
そこで、法律の専門家である弁護士に肖像権侵害への対応について相談すれば手続きを効率的に進められます。
肖像権侵害の加害者にならないためには
最後に、ご自身が肖像権侵害の加害者にならないように注意するのも大切です。
そこで、以下の2点について日頃から気を付けましょう。
被写体を特定できないように加工する
まずは、動画や写真を公開する際、被写体を特定できないように加工することです。
たとえ仲の良い友人であっても、被写体が特定できる状態で動画や写真をSNSなどに投稿するのはやめましょう。
どうしても投稿したい場合は、自分以外の被写体の顔を特定できないようにモザイクやスタンプなどで加工することが大切です。
被写体に予め許可をとる
被写体に許可を得ている場合は、動画や写真をSNSなどに投稿しても問題ありません。
被写体の許可なく投稿した場合、「本当は勝手に載せてほしくないのに」と思われてしまう場合もあります。
トラブルを予防するためにも、投稿前には必ず許可をとるのが必要です。
まとめ
無断で自身の動画や写真を撮影・公開されるのは、多くの人にとって精神的な苦痛となります。
もし、肖像権の侵害に遭った場合は、早急に対応してください。肖像権を侵害された場合、民事責任の追及は可能です。
しかし、加害者が匿名である場合、まずは発信者情報開示請求の手続きから始める必要があります。
肖像権の侵害に関して不安や疑問点があれば、弁護士に相談するのもおすすめです。
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q:肖像権を侵害された場合、加害者へ責任を追及できますか?
A:刑事責任の追及は不可能ですが、民事責任の追及は可能です。
Q:仲の良い友人でも、一緒に写っている写真を公開する際は許可をとるべきですか?
A:許可をとりましょう。もし、許可を得ていないなら被写体を特定できないように加工したうえで公開してください。