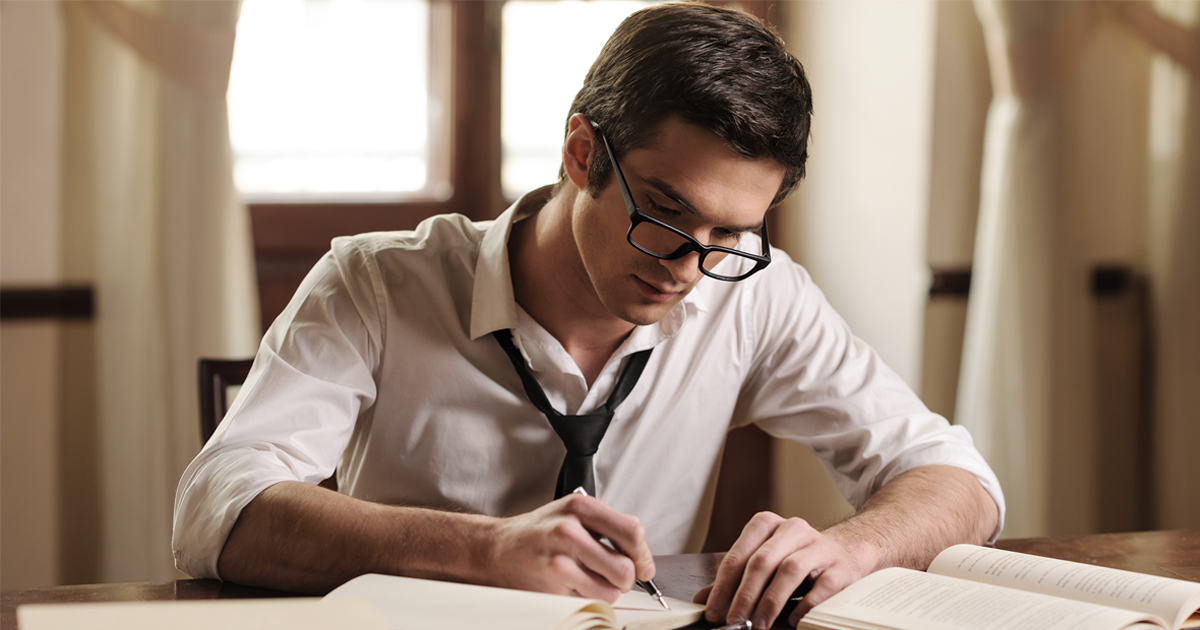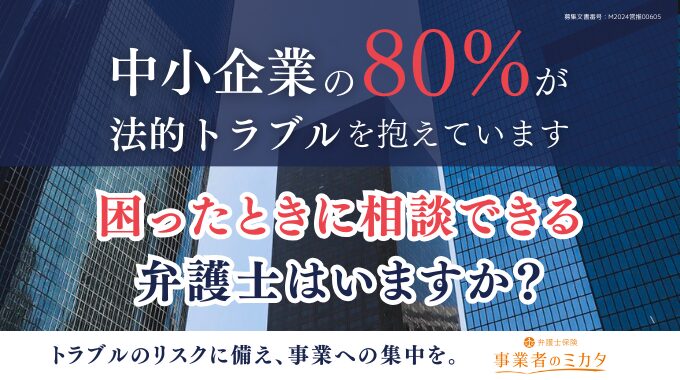弁護士資格を得るには、なにも大学を卒業していなければならないわけではありません。
よって、たとえ高卒であっても、弁護士になることは可能です。
しかしながら、かなり険しい道になることは間違いありません。
高い志がないと、高卒から弁護士資格を得るのはかなり難しいと言えるでしょう。
こんな疑問にお答えします
A.可能です。弁護士になる方法としては、司法試験に合格するという方法がもっとも一般的です。高卒の場合、司法試験の受験資格を得るためには司法試験予備試験に合格する必要があります。ただ、予備試験は非常に難しいため、覚悟を決めて挑むという心構えのもと目指すようにしましょう。
弁護士になる方法
現在、弁護士になる方法としては司法試験に合格するという方法がもっとも一般的です。
その他にも、検察事務官から検事、検事から弁護士といった方法もありますが、あまり現実的ではないため、今回は割愛させていただきます。
つまり、弁護士になるには司法試験に合格しなければならないということです。
これは高卒であっても変わりはありません。
しかし、司法試験を受験するためには、まず受験資格を得なければなりません。
そして、司法試験の受験資格を得るには法科大学院(ロースクール)を修了する方法と、司法試験予備試験に合格するという2つの方法だけが、現在は認められているのです。
したがって、高卒から司法試験の受験資格を得るためには、改めて大学、大学院と進んでいくか、司法試験予備試験に合格するかのどちらかしかないということです。
高卒で弁護士になるメリット
高卒で弁護士になるには、司法試験予備試験にパスすることが必須条件ですが、乗り越えた先には大きなメリットが得られます。
高い年収が期待できる
弁護士になるメリットとして、高い年収が得られるという点です。
法務省が行った弁護士の平均年収の集計結果によると、弁護士は1年目から約568万円(平成27年分)、4年目には1,000万円を超えるとされています。
厚生労働省が発表している高卒の一般的な平均年収は、約354万円です。
高卒で司法試験予備試験に合格して弁護士になると、約1.6倍の年収が稼げる計算になります。
一度弁護士になれば生涯働ける
弁護士には定年がなく、資格更新もありません。
ゆえに、一度弁護士になることで生涯弁護士として働けます。
また、仕事がなくなるというリスクも少ないのが弁護士のメリットでしょう。弁護士の仕事は、人と人の間で起きるトラブルを解決すること。人がいる以上、仕事がなくならないということです。
高卒で弁護士になるデメリット
高卒で弁護士を目指すには、デメリットもあるということを理解しておきましょう。
司法試験予備試験に合格するハードルが高い
まず、司法試験予備試験という壁です。
高卒の人が最短で弁護士になるには、司法試験予備試験に合格することが最低条件です。
司法試験予備試験は非常に難易度が高く、合格するまで最低でも4年以上、場合によっては数年かけての猛勉強が必要です。
さらに、勉強を続けたとしても確実に受かるとも限りません。受からない場合の将来についても考えておく必要があります。
勉強時間の継続に苦痛を感じやすい
勉強時間の継続に苦痛を感じやすいというデメリットもあります。
司法試験予備試験のハードルが高いということは、当然のことながらそれなりの勉強時間を確保する必要があります。
司法試験予備試験に向けての勉強時間の目安は、2つの試験を合わせると最低でも5000〜6000時間といわれ、中には10000時間を超えるという人もいます。
単純計算すると、1日8時間以上の勉強を3〜4年間継続することになります。また、晴れて弁護士になったとしても継続した学習が重要となります。
弁護士を目指すにもなった後も、継続的に学び続けるという覚悟が必要なのです。
高卒で司法試験に合格するには司法試験予備試験を活用しましょう
改めて大学、大学院と進んでいくのであれば、もはや高卒からの弁護士とは言えなくなってしまうため、今回は司法試験予備試験についてご紹介します。
司法試験予備試験は、経済的な理由などから法科大学院にまでいくことができない方に向けて、2011年から始まった制度です。
この予備試験に合格した者は、法科大学院修了者と同等程度の知識量を備えていると判断され、司法試験への受験資格を得ることができます。
予備試験には特に受験資格に制限はなく、誰でも何度でも受けることができるため、もちろん高卒であっても受験することができます。
とはいえ、この予備試験は非常に難しく、予備試験合格を目指すくらいなら法科大学院を修了したほうが早いとも言われているくらいです。
確かに、何度でも受験できるというメリットがありますが、1年に1回しか実施されていないことからも、半端な心構えではまず合格できないと考えておきましょう。
高卒から弁護士になるためのおすすめの勉強法
高卒から弁護士になるためには、独学ではなく予備校や通信講座を利用することをおすすめします。現実には、独学だけで弁護士になったという方もいますが、本当に稀です。
弁護士を目指すのであれば、やはりプロの指導者から直接学び、合格のノウハウを得る方が効果的といえるでしょう。
何度もいいますが、司法試験の難易度は非常に高いものです。高卒から本気で弁護士を目指すのであれば、最初から効率の良い方法で学び始めましょう。
関連記事
-
-
独学で弁護士にはなれるが、現実はそんなに甘いものではない
ここでいう独学とは、予備校に通わないという意味だけでなく、法科大学院での授業を含まないという前提で見ていきましょう。 単に予備校に通わないことだけを独学というのであれば、現実に予備校へ通わずに多くの法科大学院修了者が弁護 …
予備校に通える程度ゆとりは必要
上記のように、司法試験予備試験は簡単に合格できる試験ではないため、仕事をしながら合格できるという方は本当に稀です。
数年間は仕事を辞める覚悟と、予備試験合格のために予備校へと通える程度の経済的なゆとりは、最低限必要なのではないでしょうか。
司法試験予備試験を合格し、司法試験へと臨む受験者のことを「予備試験組」と呼ぶのですが、司法試験における予備試験組の合格率は、法科大学院修了者の合格率をはるかに上回っています。
つまり、法科大学院にまで進み、何年間も法律の勉強ばかりしてきた学生たちよりも、予備試験を合格し、司法試験の受験資格を得た予備試験組のほうが圧倒的に司法試験の合格率が高いのです。
これは、予備試験がどれだけレベルの高いものかを表しているとも言えます。
これだけレベルの高い予備試験に合格しなければならないということは、独学だけではなくしっかりと予備校にも通い、予備試験合格に向けた効率的な勉強が必要になりますよね。
個人的には、仕事を辞めて予備校に通うくらいの覚悟と経済的なゆとりがないことには、司法試験予備試験に合格するのは難しいと考えています。
終わりに
高卒で弁護士になるには、司法試験予備試験の突破が不可欠です。
司法試験予備試験をパスするには、相当な覚悟と努力を必要とすることを理解しておきましょう。
弁護士を目指すには、何事も継続が必要です。
効率のいい勉強方法で、諦めずコツコツと学習し続けましょう。
また、弁護士を目指すのであれば弁護士保険の制度についても理解しておきましょう。
実際に訴訟などになった際の弁護士費用を軽減することが可能です。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
また、法人・個人事業主の方向けには、法人・個人事業主向けの弁護士保険があります。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q.高卒でも弁護士を目指せますか?
A.可能です。弁護士になる方法としては、司法試験に合格するという方法がもっとも一般的です。高卒の場合、司法試験の受験資格を得るためには司法試験予備試験に合格する必要があります。
Q.司法試験予備試験を受験するには回数制限はありますか?
A.ありません。誰でも何度でも受けられます。
1年に1回しか実施されず、難易度も非常に高いです。半端な心構えではまず合格できないと考えておきましょう。
Q.司法試験予備試験に向けて、おすすめの勉強方法はありますか?
A.予備校や通信講座を利用することをおすすめします。現実には、独学だけで弁護士になったという方もいますが、本当に稀です。
弁護士を目指すのであれば、やはりプロの指導者から直接学び、合格のノウハウを得る方が効果的といえるでしょう。