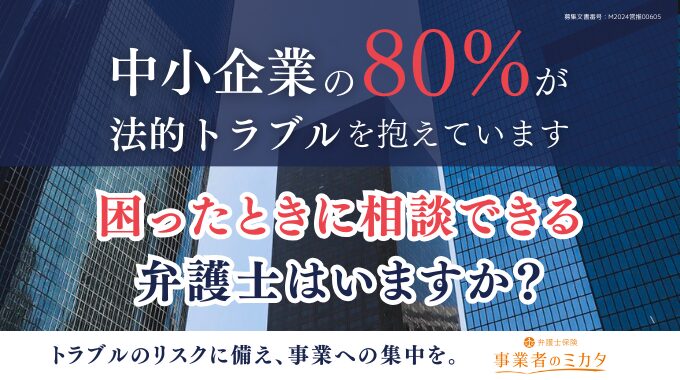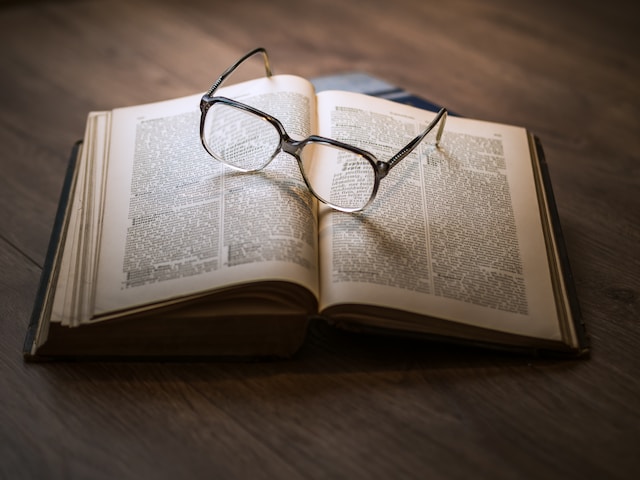セカンドオピニオンとは、現在の主治医以外の医師に第二の意見を求めることです。
これは法律の分野でも求められるケースが多く、実際に何件も法律相談を行われている方も多くいらっしゃいます。
しかし、医療の現場とは違い、弁護士の法律相談というのは、相談者からの情報だけで法的な判断をするだけでなく、そこには客観的な事実関係も必要となります。
いくら相談者が「これが事実だ」と言っても、正しいかどうかの判断は容易ではありませんし、もちろん弁護士が得た情報が異なれば、それぞれの判断も変わってくるのです。
弁護士によるセカンドオピニオンには、このような難しい現実も存在しています。
こんな疑問にお答えします
Q.進行中の相談内容があっても、別の弁護士に相談するのは有りですか?
A.複数の弁護士への相談は問題ありません。現在、弁護士に依頼している方であっても、その弁護士の事件処理に疑問が生じているのであれば、他の弁護士に相談することは可能です。ただ、セカンドオピニオンを得る際はデメリットもあり、相談するうえでの注意点にも気を配る必要があります。
そもそも別の弁護士に相談するのは有り?
冒頭にて弁護士のセカンドオピニオンの現実について触れましたが、そもそも別の弁護士に相談するのは有りなのか?といった疑問をお持ちの方も多いはずです。
結論から言えば、複数の弁護士への相談は問題ありません。
現在、弁護士に依頼している方であっても、その弁護士の事件処理に疑問が生じているのであれば、他の弁護士に相談することは可能です。
しかし、他の弁護士にそのまま依頼するとなれば、委任関係が2つ以上生じることになるため、完全なマナー違反となります。
委任関係の重複を良しとする弁護士はまずいないので、まずは委任関係を解消してからと言われてしまいますし、黙って委任関係を結んでしまうのも良くはありません。
これだけで円滑な事件処理が出来なくなってしまうので、依頼の重複だけには注意しましょう。
弁護士のセカンドオピニオンを必要とするケース
先ほどお伝えしたように、その弁護士の事件処理に疑問を抱いた際は、他の弁護士に相談することが可能です。
具体的には、以下のケースでセカンドオピニオンを必要とすることがあります。
- 依頼している弁護士の方針で問題ないのかどうか確証を得たい場合
- 進行中の方法に安心を得たい
- 依頼している弁護士との信頼関係が構築できそうにない
基本的に、弁護士は相談者の味方です。しかし、「信頼して話せない」「聞きづらい」という場合は、その後の進行に支障が出る恐れがあります。その場合は、ほかの弁護士にあたってみてもいいかもしれません。
弁護士にセカンドオピニオンを求めるメリットとデメリット
ここで、弁護士にセカンドオピニオンを求めるメリットとデメリットも解説します。
弁護士にセカンドオピニオンを求めるメリット
別の弁護士に相談することで、主に以下のようなメリットがあります。
- 相談したいトラブルの解決方法に選択肢が生まれる
- セカンドオピニオンを得ることで、トラブル解決に慎重になれる
- 専門知識を得る機会が増える
依頼済みの弁護士との解決手段が異なる場合は、相談内容をより慎重に検討することができます。一方で、すでに依頼済みの弁護士の意見とセカンドオピニオンの際の意見が同じである場合は、安心感が得られるでしょう。
弁護士にセカンドオピニオンを求めるデメリット
一方で、デメリットを紹介するのであれば、以下のものが挙げられます。
- セカンドオピニオンを得たことによって、依頼済みの弁護士との関係に悪影響が出ることがある
- セカンドオピニオンの相談をすることで新たに相談料がかかる可能性がある
弁護士のひとりの人間ですから、別の弁護士に相談したことが分かってしまった場合に関係が崩れてしまうことがあります。
また、法律事務所によって相談の際の料金が異なります。初回無料で相談を受け付けているところもあるので、セカンドオピニオンを求める際は料金も確認してみてください。
弁護士に掲示する情報は統一させる

まず、弁護士へのセカンドオピニオンが難しい理由の1つが情報の錯綜です。
毎回のように言い方を変えたり、以前は持っていかなかった新たな証拠を持っていったりと、情報が統一していなければ、当然、弁護士の判断も異なってきます。
よって、弁護士へのセカンドオピニオンを求めるのであれば、提示する情報は必ず統一させてください。
毎回違うことを言っていれば、それに対して弁護士は法的判断をしていきますので回答が異なってしまってもおかしくはありません。
また、これでは先に相談した弁護士、後に相談した弁護士、どちらの判断が本当に正しいのかの判断基準にもなり得ません。
さらに、相手方がいる問題であれば、相談者からの主張だけが全面的に正しいかどうかも明確な判断はできません。
相手がいる以上、相手の主張もあります。
相談者からの情報がすべて真実ではないと判断するのは、弁護士として決しておかしなことではないのです。
本当に必要な情報の判断は難しい

しかし、その部分や事情こそが、まさに法的な判断に必要になるということも珍しくはありません。
この弁護士は話しやすいからここまで話してしまった、あの弁護士は話しにくいからこの情報は黙っておこうといったように、弁護士への話しやすさなどを理由に本当に必要な情報を出していない場合があるのです。
これでは弁護士の意見が変わるのも当然です。
また、相談者目線では対して重要ではないから話す必要がないと感じた部分であっても、それこそが本当に必要な情報である場合もあります。
こうした法的に必要かどうかの判断は、素人目にはなかなか出来ることではありません。
おわりに|うまく利用できれば有益になるのも事実
これまで弁護士へのセカンドオピニオンの難しさについて説明してきましたが、うまく利用できるのであれば相談者にとって有益になるのも事実です。
弁護士といっても様々な考えた方を持っていますし、弁護士の数が増えすぎてしまったこともあり、弁護士としての能力やセンスというのも実際問題として存在しています。
中にはおかしな弁護士や、犯罪に手を染めてしまう弁護士だっているのが現実です。
また、1つの問題に対してどの弁護士も同じ判断をするわけではありません。
異なる判断をする弁護士がいるため、最終的には裁判所が介入し、裁判官が是非を判断するのです。
このように、弁護士と一言でいっても様々なので、相談者それぞれが見極め、どういった基準で信頼関係を築き上げるのかを判断していく必要があるのです。
見極めができない、判断ができないといった場合、他の弁護士にその回答を求めるというのは決して間違ったことではありません。
より多くの弁護士に見解を求めてみるというのも、問題解決への1つの方法と言えるでしょう。
セカンドオピニオンをするなら?おすすめの相談窓口
すでに法律相談をされている方もいらっしゃると思いますが、改めて法律相談ができる窓口を紹介します。
弁護士の相談ができる窓口は、以下の5つがおすすめです。
- 弁護士会による法律相談センター
- 法テラス
- 自治体の法律相談
- 弁護士保険
- 各法律事務所
それぞれの詳細について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事
-
-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
弁護士保険の保証内容について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
関連記事
-
-
【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく
「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …
記事を振り返ってのQ&A
Q.進行中の相談内容があっても、別の弁護士に相談するのは有りですか?
A.複数の弁護士への相談は問題ありません。現在、弁護士に依頼している方であっても、その弁護士の事件処理に疑問が生じているのであれば、他の弁護士に相談することは可能です。
Q.弁護士のセカンドオピニオンを必要とするケースは具体的にどんなとき?
A.「依頼している弁護士の方針で問題ないのかどうか確証を得たい場合」「進行中の方法に安心を得たい」「依頼している弁護士との信頼関係が構築できそうにない」という場合において、セカンドオピニオンが有効となります。
Q.弁護士にセカンドオピニオンを求めるメリットとデメリットを知りたいです。
A.メリットは、「相談したいトラブルの解決方法に選択肢が生まれる」「セカンドオピニオンを得ることで、トラブル解決に慎重になれる」「専門知識を得る機会が増える」等です。
一方でデメリットは、「セカンドオピニオンを得たことによって、依頼済みの弁護士との関係に悪影響が出ることがある」「セカンドオピニオンの相談をすることで新たに相談料がかかる可能性がある」等が考えられます。
Q.セカンドオピニオンを求める際の注意点はありますか?
A.弁護士へのセカンドオピニオンを求めるのであれば、提示する情報は必ず統一させましょう。