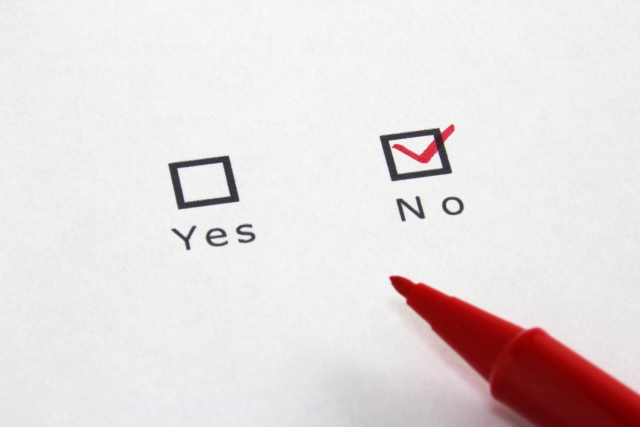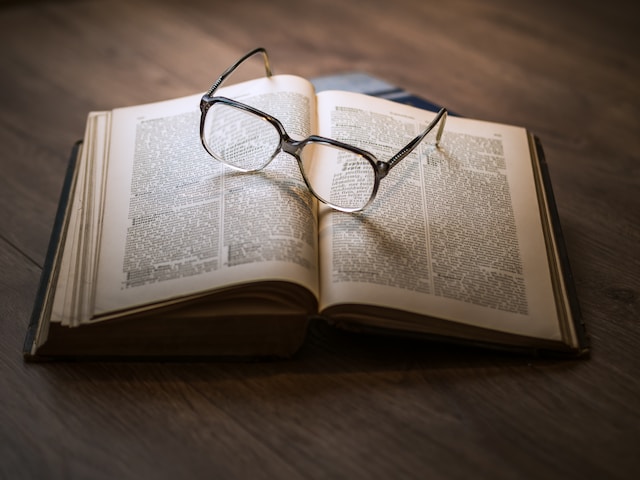もし、クレジットカードを勝手に利用されているのに気づいて、その犯人が自分の子どもだったらどうしますか?
子どもが親に無断でクレジットカードを利用した場合、親に支払義務は生じるのでしょうか。
ここでは実際にあったケースを紹介しながら、どのように対処していけばいいかを紹介していきます。
こんな疑問にお答えします
A.子どもが親のクレジットカードを勝手に利用したというだけでは支払いを拒否することはできません。子どもに限らず家族や同棲相手といった同居人が勝手に使った場合は、免責対象にならないというのが一般的な考え方です。支払い義務については、クレジットカードの管理方法も論点となるので注意しましょう。
子どもにクレジットカードを勝手に利用されたケース
子どもが勝手にクレジットカードを利用することなんてありえない、と思われている方もいるかと思います。
ここでは実際に起きたケースをご紹介します。
Aさんに、カード会社から100万円を超す請求がきました。
買った覚えのないバッグやスーツなどの請求であったため、Aさんはカード会社に連絡をし、これらの買い物をしていないこと、カードは自宅にあるので外で誰かに使われたこともないことを伝えました。
カード会社は事実関係を調べる旨をAさんと約束し、もしも第三者の不正利用によるもので、Aさんに重大な落ち度がなければ、カード保険が適用されると回答しました。
しかし、実際には、これらはAさんの18歳になる息子がインターネットで購入したものだったのです。
息子に確認をしてみると、カードを盗み見てカード番号と有効期限を知り、ネット決済したということでした。
カード会社は、約款に記載してあるとおり、親族が使用した場合には保険は適用されないため、期日までに請求額を支払うようAさんに求めました。
子どもが勝手にクレジットカードを使ったらなぜ支払わなくてはならないのか?
子どもにクレジットカードを勝手に使われた場合、カード会社がいうように親は支払わなくてはならないのでしょうか?
基本的に、クレジットカードは契約している本人しか使えないことになっています。
しかし、子どもに限らず家族や同棲相手といった同居人が勝手に使った場合は契約者本人の管理不足とみなされ、免責対象にならないというのが一般的な考え方です。
さらには、不正利用と見せかけて子どもを使って補償を受けようとしたと疑われてしまうかもしれません。
従って、たとえ親の知らないところで子どもがカードを利用して買い物をしたとしても、親は利用額の支払いを求められる可能性があります。
支払いを拒否する方法とは?
納得が行かないAさんは、支払いを拒絶しました。
インターネットの買い物の場合、カードが手元になくても、カード番号と有効期限がわかれば決済ができてしまいます。
Aさんは、カード番号の入力だけで決済できるとの説明が事前になかったことや、カード番号は郵便物などからでも類推が可能なため盗み見されやすいことなどをあげ、不正利用されやすい決済方法に問題があり、たとえ親族の無断使用は支払いを拒絶できないとの約款があっても、名義人に支払義務はないと主張したのです。
カード会社はAさんを相手取り、カード代金の支払いを求める裁判を起こしました。
裁判所は、カード番号と有効期限さえわかれば決済できるネット決済の仕組みは、暗証番号などによる本人認証を使う場合と比べ、第三者の不正利用を妨げにくいと指摘し、カード利用者の本人確認に不備があると判断しました。
そして、Aさんに対するカード会社の支払請求を退け、Aさんは支払いを免れたのです。
なお、民法では「未成年者契約の取消し」という規定があります。
しかし、子どもが親のクレジットカードを勝手に利用したというだけで支払いを拒否することはできません。
この場合、親がクレジットカードを正しく管理していたかどうかがポイントになります。
クレジットカードを安易に盗まれる場所に放置していた場合などは、親の監督責任を問われ、利用料金の支払義務が生じます。
上記のケースの中で、カード会社は、未成年の息子の親であるAさんは監督義務者として責任を負うとも主張しましたが、裁判所は満12歳から13歳になれば自分の行為の善悪を見定める判断能力(責任能力)があるとして、Aさんには息子の不法行為に対する民法714条の監督責任はないと、カード会社の主張を退けました。
子どもが勝手に利用したクレジットカードの決済を取り消すためには、自らに重過失がないことを証明しないといけません。
自分だけで対処することは難しいため、弁護士や消費者生活センターに相談することが望ましいでしょう。
子どもによるクレジットカードの不正利用を未然に防ぐには?
子どもによるクレジットカードの不正利用を未然に防ぐためには、クレジットカードとはどんなものかということについて、子どもの判断力、年齢に合った説明をすることが必要になってきます。
クレジットカードとはお金と一緒だということ、お財布からクレジットカードを抜いたらお金を取ったのと同じ、クレジットカードを利用したらお金を使ったのと同じと教えてあげることが大事なのです。
また、クレジットカードを安易な場所に置かずにきちんと保管することや、クレジットカードを作成したら管理責任が生じることを忘れないでください。
そして、自分の大事な子どもを犯罪者にしないためにも、自分が傷つかないためにも、クレジットカードは契約者本人以外は利用しないということを守っていくようにしましょう。
まとめ
クレジットカードを発行する際、利用者は、カードの管理を厳重に行うことを約束しています。
子どもが勝手に利用したという理由で支払拒否をすると、カードが利用停止となったり、ローンが通らなくなったり、ブラックリスト入りしてしまうなど、自分に不利な問題が起きてしまいます。
クレジットカードを発行する際は、契約事項をしっかり読み、厳重に管理することが必要です。
また、自分の子どもに限って勝手に利用することはないなどと目を背けず、子どもを守っていくためにも、子どもと一緒にクレジットカードの怖さなど勉強するようにしましょう。
カードの不正利用に遭った場合は弁護士へ相談しよう
今回紹介したケースは、子どもが勝手に不正利用したパターンです。
ただ、同居している家族や子どもによる不正利用であっても、契約者本人にとっては立派な被害でしょう。
勝手にクレジットカードを使われたことによる損害は、弁護士への相談をおすすめします。
不正利用に関する今後の対策は当事者同士の話し合いが必要です。ただ、個人間の話し合いはどうしても感情的になりやすく、家族といえども関係性が悪化することもあり得ます。
弁護士に相談することで、当事者同士で解決を目指すよりも冷静な話し合いができるでしょう。
弁護士へ相談できる窓口
弁護士へ相談するといっても「どのように探せばいいのか分からない」「初めての法律相談で緊張する」といった不安を抱える人も多いでしょう。
弁護士の相談ができる窓口は、以下の5つがおすすめです。
- 弁護士会による法律相談センター
- 法テラス
- 自治体の法律相談
- 弁護士保険
- 各法律事務所
弁護士費用に不安がある場合は、弁護士保険の利用もおすすめです。
保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
それぞれの詳細について詳しく知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
関連記事
-
-
【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく
「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …
記事を振り返ってのQ&A
Q.子どもが勝手に親のクレジットカードを利用したら支払わなくてはならないのでしょうか?
A.子どもに限らず家族や同棲相手といった同居人に勝手に使われた場合は管理不足とみなされ、免責対象にならないというのが一般的です。
Q.支払いを拒否することはできませんか?
A.一般的に、子どもが親のクレジットカードを勝手に利用したというだけで支払いを拒否することはできません。クレジットカードを安易に盗まれる場所に放置していた場合などは、親の監督責任を問われ、利用料金の支払義務が生じます。従って、子どもが勝手に利用したクレジットカードの決済を取り消すためには、自らに重過失がないことを証明しないといけません。
Q.子どもによるクレジットカードの不正利用を防ぐ対策はありますか?
A.クレジットカードを安易な場所に置かずにきちんと保管することや、クレジットカードを作成したら管理責任が生じることを子どもに教えてあげましょう。
近年の日本社会においても未だ無くならない、最も古典的な犯罪である窃盗。
一番イメージしやすいのは手ぬぐいや風呂敷を鼻の下で結んだ、ひげ面の泥棒でしょうか……もちろん、今どきそんなわかりやすい犯人はいません。
しかし、残念ながら、相変わらず窃盗事件はたくさん起きているという事実は存在します。
最近では防犯カメラなどの普及により減少傾向ではあるものの、平成30年の窃盗の認知件数は約58万件にも上ります(令和元年版 犯罪白書)。
これは、交通事故(過失運転致傷)などを除いた一般刑法犯の認知件数のうち71.2%を占めることになります(平成30年)。
日頃、犯罪なんてニュースの中のことだと思っている人も多いかもしれませんが、実は空き巣・万引きといった窃盗の被害は、決して縁遠いものではありません。
では、いざそんな窃盗の被害にあったとき、犯人が捕まれば盗まれた物やお金は戻ってくるのでしょうか。
犯人が盗んだものを売ってしまっていたり、隠し口座に保管してしまっていたら?
はたまた使い切ってしまっていたら?
受刑中の刑務所の中からも返済させられるのか……?
このような様々な疑問について、今回は見ていこうと思います。