 昔は飲食店はもちろんのこと、電車だろうが飛行機だろうがどこでもたばこが吸えたものですが(座席のひじかけなどに灰皿の痕跡がありますね)、現在は公共の場所ではほとんどたばこを吸うことができなくなりました。
昔は飲食店はもちろんのこと、電車だろうが飛行機だろうがどこでもたばこが吸えたものですが(座席のひじかけなどに灰皿の痕跡がありますね)、現在は公共の場所ではほとんどたばこを吸うことができなくなりました。
健康問題もさることながら、一部の喫煙者のマナーの問題もあって、愛煙家の肩身は狭くなるばかりです。
会社においても、デスクでたばこを吸いながら仕事をするという時代ではなくなったものの、頻繁にたばこ休憩をとるとか、ニオイが気になるとかと言われ、喫煙者の評判はあまりよろしくなさそうです。
喫煙者は採用しないという方針を発表して話題となった会社もありました。
今日は、会社でのたばこ問題について考えてみましょう。
こんな疑問にお答えします
A.労働安全衛生法では、労働者の受動喫煙防止の義務があります。これは事業者が労働者の受動喫煙を防止するものを示すものです。しかし、あくまで努力義務といって守らなくても法的な処罰はなく、強制的ではありません。
ただ、におい問題は個人の感じ方が異なるため非常に難しいものです。
タバコ臭だけでなく職場のにおい問題を放置しておくことで、対人トラブルにつながるリスクすらあります。職場の人間関係は働く上で最も重要なポイントです。もし職場の人間関係で悩んだ場合は、労務に精通した弁護士へ相談することも視野に入れましょう。
喫煙をめぐる権利と法規制
まずは、労働法を離れて大きなお話からはじめたいと思います。
わが国では、日本国憲法によって国民に基本的人権が保障されていることは皆さんもご存じかと思います。
憲法には、自由権、社会権、参政権など、さまざまな権利が規定されていますが、より包括的な条項として、憲法13条後段が以下のように定めています。
これを「幸福追求権」と呼びますが、この幸福追求権の一内容として、喫煙権という権利が基本的人権として無制限に認められるものなのかどうかが問題となります。
この点については、最高裁がこんなふうに判断しています。
タバコを1日2箱以上は吸うという愛煙家のXは、とある法律に違反した容疑で逮捕されましたが、未決勾留期間中、看守に喫煙を希望したもののこれを拒否され、さらに、Xは喫煙の許可を求める請願状を提出するも回答されず、結局釈放時まで喫煙を許されませんでした。
Xは、当時
と定めていた監獄法施行規則96条が憲法に違反し無効であると主張して、国家賠償を求める訴えを提起しました。
第一審、控訴審ともXの請求を棄却し、最高裁は、
として、Xの上告を棄却しました(最大判昭45.9.16民集24-10-1410) 。
喫煙権の対になる嫌煙権とのぶつかりあいではなく、あくまで刑事施設の管理や収監の目的との関係で喫煙の自由が制約されるという判断なわけですが、「喫煙の自由は……基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 」という判示はなかなか示唆に富むといえます。
学説上も、喫煙の自由は憲法13条の範囲に含まれるけれど、それを制限することについての合憲性は緩やかに判断されるというのが有力な説のようです。
そもそも社内でタバコを吸わせるような会社の体制は法律的にどうなのか
 労働契約法5条は、使用者が「安全配慮義務」 を負う旨規定しています。
労働契約法5条は、使用者が「安全配慮義務」 を負う旨規定しています。
安全配慮義務とは、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ働けるようにすることを指します。
安全配慮義務の具体的な内容としては、危険作業や長時間労働、うつ病自殺等の場面で会社の責任を問うような状況が一般的ですが、この安全配慮義務からは、使用者が受動喫煙をさせないように職場環境を整備する義務も導き出されます。
受動喫煙との関係では、「健康増進法」という重要な法律もあります。
平成15年に施行された健康増進法は、健康調査や保健指導などを通じて、国民の健康の増進を図ることについて定めた法律ですが、その一環として、第25条が、受動喫煙の防止について以下のように規定しています。
いろいろな種類の施設が列挙されていますが、ここにあるものに限らず、おしなべて「多数の者が利用する施設」については、管理者が利用者などに受動喫煙を防止するような措置をとることが必要とされています。
もちろん「職場」も「多数の者が利用する施設」にあたりますから、施設の管理者である会社は、受動喫煙防止について健康増進法上の義務を負うものといえます。
これに加えて、平成27年6月からは、労働安全衛生法の改正によって、以下のとおり、事業主に労働者の受動喫煙防止の義務を課す条項が加えられました。
条文の内容としては健康増進法25条とほとんど同じですが、「事業者」が「労働者」の受動喫煙を防止する、と、主体を明言したことは画期的だといえます。
ただし、健康増進法25条と労働安全衛生法68条の2の末尾が「……ように努めなければならない」、「努めるものとする」となっているのは多少やっかいです。
これは、「努力義務」といって、守らなくても法的な処罰を受けないことを示す文言なので、法律上、会社が労働者の受動喫煙を防止することについて、それほどガチガチに強制されているわけではないのです。
しかし、努力義務とはいえども、これを守らなかったことによって健康被害などが発生した場合に、会社が損害賠償責任を負わない、という意味ではありません。
健康被害を受けたら責任をとってもらえるの?
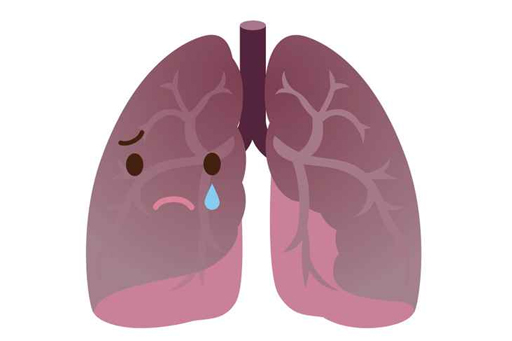 先に述べた安全配慮義務、そして健康増進法・労働安全衛生法との関係から、仮に受動喫煙によって健康被害が発生すれば、会社がその損害を賠償する責任を負うことになります。
先に述べた安全配慮義務、そして健康増進法・労働安全衛生法との関係から、仮に受動喫煙によって健康被害が発生すれば、会社がその損害を賠償する責任を負うことになります。
独立行政法人国立がん研究センターが公表したところによれば、わが国では受動喫煙が原因の肺がん・心疾患・脳卒中などで年間約1万5000人が死亡していると推計されています。(厚生労働省「日本では受動喫煙が原因で年間1万5千人が死亡」)
これは交通事故死の3倍以上にあたるものであり、同センターも「受動喫煙は『迷惑』や『気配り、思いやり』の問題ではなく、『健康被害』『他者危害』の問題である」と警鐘を鳴らしているところです。
しかし、これだけの健康被害が明らかとなっていても、会社の責任を追及するのはちょっと難しいかもしれません。
会社での受動喫煙が長期にわたればそれだけ重い病気にかかる可能性も高くなるといえますが、先ほどあげたガンにしても、喫煙のみならず飲酒や食事、運動などさまざまな原因が考えられるわけで、会社での受動喫煙が原因で病気にかかったものとは必ずしも言い切れなくなるからです。
ただし、副流煙の微粒子による化学物質過敏症については別で、受動喫煙と健康被害との因果関係がはっきりしているので責任追及がしやすく、実際に労働者からの会社に対する損害賠償請求が認められているケースもあります。
平成18年10月のニュース記事ですが、「健康増進法で定められた分煙措置を雇用主が怠ったため、受動喫煙で化学物質過敏症を患ったとして、北海道当別町の会社員が札幌市東区の会社に慰謝料100万円の支払いを求めた調停が札幌簡裁であり、同社が示談金80万円を払うことで調停が成立した」というものがありました。
分煙していてもニオイが気になる!我慢しなければならないの?
 2015年に発表された帝国データバンクの調査によると、職場を全面禁煙としている会社は24パーセントですが、完全分煙を含めると79パーセントにのぼり、職場における禁煙・分煙の措置は急速に進んでいる模様です。(帝国データバンク「従業員の健康管理に対する企業の意識調査」)
2015年に発表された帝国データバンクの調査によると、職場を全面禁煙としている会社は24パーセントですが、完全分煙を含めると79パーセントにのぼり、職場における禁煙・分煙の措置は急速に進んでいる模様です。(帝国データバンク「従業員の健康管理に対する企業の意識調査」)
しかし、分煙レベルでは、流れてくるニオイはどうしても防ぎきれないのが現状ではないでしょうか。私の職場では、オフィスビルの1階ロビーが喫煙所になっているのですが、エレベーターが1基は必ず1階でクチを開けて待っているため、エレベーターに乗っただけで服にニオイが移ってしまうような状態です。
最初に触れた健康増進法に関して、厚生労働省が受動喫煙防止についての通達を出しているところ(厚生労働省「平成22年2月25日健発0225第2号」)、この通達によれば、受動喫煙防止の基本的な方向性としては「原則として全面禁煙であるべき」としています。
この通達に照らせば、会社としても職場を全面禁煙にすることが望ましいといえるわけですが、そこは先ほど述べた「努力義務」にすぎないため、例えば労働者や労働組合などが会社に対して、より効果的な受動喫煙対策を講じるよう申し入れたとしても、会社としてはこれに応じる法的義務まではないということになります。
理論的には、ニオイが服につくなどして非常にストレスを感じたなどとして慰謝料等を請求することもできるにはできますが、高額の損害賠償が認められる可能性は残念ながら低いといわざるを得ません。
職場での受動喫煙について労働者からの慰謝料請求を認めたおそらく最初の事例である江戸川区(受動喫煙損害賠償)事件(東京地判平16.7.12労判878-5)でも、慰謝料として5万円が認められるにとどまっており、最近公刊された裁判例における慰謝料請求はあらかた棄却されているのが実情でした(ただし、ニオイだけでも化学物質過敏症が引き起こされるようなケースはこれには含みません)。
タバコ臭問題について会社に改善を求めてみる
職場においてタバコ臭に関する問題は起こり得るものです。特に、禁煙者にとっては喫煙者の衣服や髪についたタバコの臭いを嗅ぐだけでも気分が悪くなってしまう人もいます。
喫煙者も禁煙者も同じ職場で気持ちよく働くためには、会社側に対策を求めることも一つの手です。
例えば以下のことを会社に改善を求めてみてください。
- 換気を徹底してもらう
- オフィスに空気清浄機を設置してもらう
- 衣服にかける消臭スプレーを使うよう呼びかけてもらう
- 喫煙後にマウスウォッシュを使うように促してもらう
- 喫煙後はエレベーターを使わず階段を使うよう呼びかけてもらう
この他にも、喫煙に関するルールを定めてもらうのもありでしょう。においがきっかけで対人関係が悪化すると職場の雰囲気が悪くなってしまいます。そうならないためにも、会社へ改善を求めてみるのもありです。
タバコ臭や職場のにおい問題での対人トラブルは弁護士への相談がおすすめ
におい問題は個人の感じ方が異なるため、非常に難しいものです。
しかし、タバコ臭だけでなく職場のにおい問題を放置しておくことで、対人トラブルにつながるリスクすらあります。
職場の人間関係は働く上で最も重要なポイントです。もし職場の人間関係で悩んだ場合は、労務に精通した弁護士へ相談することも視野に入れましょう。
ただ、弁護士へ相談となるとハードルが高いと感じる人も少なくありません。
「こんなことで弁護士に相談してよいのか」「バカにされないだろうか」
そのような悩みを抱える人もいるでしょう。
しかし、職場の悩みを抱えた状態は精神衛生上よくありません。弁護士へ相談することで、どのような対処法があるのか、何を講ずるべきなのかアドバイスをもらえます。
悩みが深くなる前に、一度弁護士へ相談してみましょう。
弁護士への相談窓口については、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事
-

-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
おわりに
2016年7月にフィリピン大統領に就任したドゥテルテ氏は、就任後すぐに超過激な「麻薬撲滅戦争」を開始し、世界的に注目を浴びたところですが、今度は国内の公の場での喫煙を全面的に禁止する大統領令を出すなどと報じられています。
ドゥテルテ氏が言い出したということもあってか、この規制も非常に過激なものとして受け止められているフシもありますが、実は公共交通機関や施設などで全面禁煙制度を導入している国は世界50か国前後にも上っており、その意味ではこの大統領令は決して過激なものではないといえます。
むしろ、世界的な受動喫煙防止の潮流からいえば、日本のタバコに関する規制は(特に先進国の中では)非常に後れを取っているわけです。
世界的には受動喫煙はすでに「マナー」の問題では済まされない状況となっており、今後わが国でも職場を含む公共の場でのタバコ規制はもっと厳しさを増していくことが想像できます。
喫煙者にとっては何とも肩身が狭い話ですが、禁煙するなら今のうちなのかもしれませんね。
また、職場のタバコ問題を解決するには弁護士のアドバイスを受けるといいでしょう。
弁護士に相談をする際には、弁護士の費用がかかるケースに備えて、弁護士保険に加入しておくこともおすすめです。
実際に訴訟などになった際の弁護士費用を軽減することが可能です。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』

弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
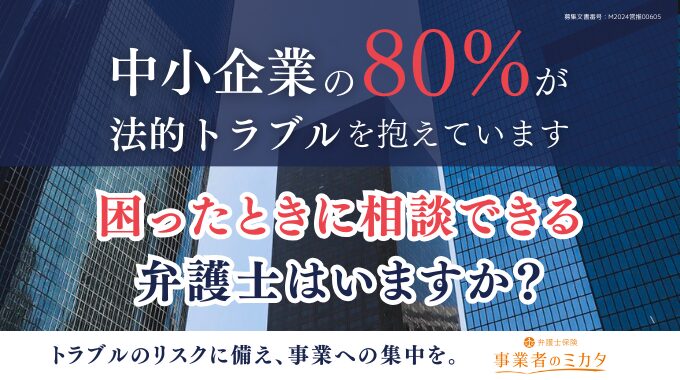
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q.職場のタバコに関する法律にはどのようなものがありますか?
A.労働安全衛生法では、労働者の受動喫煙防止の義務があります。これは事業者が労働者の受動喫煙を防止するものを示すものです。しかし、あくまで努力義務といって守らなくても法的な処罰はなく、強制的ではありません。
Q.職場の受動喫煙で健康被害を受けたら責任をとってもらえるんですか?
A.安全配慮義務、そして健康増進法・労働安全衛生法との関係から、仮に受動喫煙によって健康被害が発生すれば、会社がその損害を賠償する責任を負うことになります。
しかし、健康被害と受動喫煙の因果関係を明確にすることは難しく、会社に責任を追求することができない可能性もあります。
Q.職場のにおい問題を改善するために会社に協力を得るべき?
A.改善を求めるのも一つの手です。例えば、換気を徹底してもらう、オフィスに空気清浄機を設置してもらう、衣服にかける消臭スプレーを使うよう呼びかけてもらう、喫煙後にマウスウォッシュを使うように促してもらうなど伝えてみましょう。





