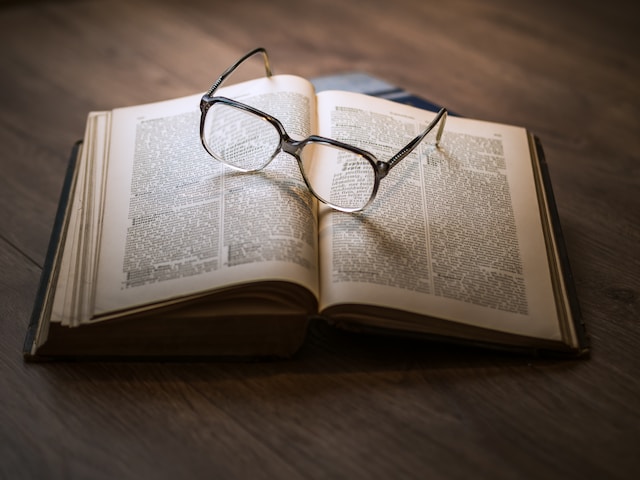親の生前に親の所有している土地に子が家を建てることはよくあることですが、兄弟や姉妹、その他にも親から見て推定相続人となる人がいる場合にはいくつか注意をしておきたいポイントがあります。
例えば、兄弟、姉妹が3人いたとして、そのうちの1人が親の土地に家を建てていたとします。
そして年を重ねていき、親が亡くなった際には相続という手続きが発生するわけですが、この時に1人だけ親の土地(被相続人の財産)に住宅があるということになると他の兄弟、姉妹、さらに被相続人の配偶者がいる場合にはその家が建っている土地に対して遺産分割の請求が出来ます。
家そのものは自分で建てていた場合であっても土地をどのような形で使わせてもらっていたかによって税金の種類から遺産分割の方法までが変化してくるので、親の土地に家を建てる場合には将来的なことも視野に入れながら考えたいものです。
ここでは親の土地に家を建てると決めた場合に相続で揉めないためのポイントなどをいくつか紹介していきます。
こんな疑問にお答えします
A.親の土地に家を建てた場合、揉める点として遺産分割が考えられます。親の土地を「購入した」のか「無償で使わせてもらっている」のか「譲り受けた」のかによって対策が異なるため、家を建てる前に十分に話し合うようにしましょう。相続で話し合うポイントに関しては、詳しい専門家に相談して進めてみてください。
親の土地に家を建てることのメリット
親の土地に家を建てることのメリットは、主に以下の2つです。
- 土地を探す必要がない
- 土地購入費用を節約できる
地域の特性を知ったうえで暮らし始められる
一つ目に、地域の特性を知ったうえで暮らし始められる点です。
家を建てる以上、その土地の住みやすさは必須条件でしょう。
ただ、住みやすいかどうかは実際に住んでみないと分からない部分が多いものです。
近所にどんな人が住んでいるかによっても、住みやすさは変わってきます。
親の土地に家を建てることができれば、利便性や土地勘を知ったうえで暮らし始めることができます。
土地購入費用を節約できる
もう一つのメリットは、土地購入費用を節約できる点です。
親の土地に家を建てるときは、新たな土地を購入する必要がありません。住宅ローンを組むにしても建物の建設費用(土台作り含む)で済みます。
土地にお金がかからない分、家のグレードを上げることも可能です。
親の土地に家を建てることのデメリット
続いて、親の土地に家を建てるデメリットも解説します。
それは、相続トラブルが発生する可能性があることです。
相続に関する詳しい内容は後の章で詳しく解説しますが、親がその土地の名義人であれば、親の相続が発生した際に兄弟間で相続トラブルが起きることが考えられます。
例えば、2人兄弟のうち長男が親の土地に家を建てたとします。
土地の名義は親で、建物の名義は長男となるのが一般的ですが、相続財産が土地のみとなれば、次男からすると親の土地が相続の対象となります。
しかし、その土地に既に長男の家が建っているがゆえに、次男は相続を受けても利用する方法がありません。
このような場合、次男は土地の相続をせずに長男のみが土地を相続し、長男は土地の半分に見合う代償金を次男に渡すという手段も考えられます。
しかし、代償金といっても大きな金額になることが想定されるため、現実的ではありません。
こうしたトラブルが兄弟間で発生する可能性があります。
では、遺産分割についてもう少し詳しく次の章でみていきましょう。
親の土地に家を建てる前に考えたい遺産分割
親の生前であって、他に相続人などがいないという場合であればあまり気にする必要もありませんが、もし親の遺産の大部分が家を建てる土地であった場合には後に先述したような遺産分割協議において揉める可能性が出てきます。
さらに親の土地を「購入した」のか、「無償で使わせてもらっている」のか、「譲り受けた」のか、などによって相続税や贈与税の種類も変化してきます。
単純に親の土地に家を建てるといっても様々なケースがあるわけですから、一概な判断は難しいものです。
親の土地を購入した場合に考えられるケース
親の土地に家を建てる時に親からその土地を購入した場合には2つほど考えられるケースがあります。
- 時価相当の土地代をしっかりと払って購入したケース
- 親の所有している土地ということで時価ではなく格安で購入したケース
1の時価相当の金額を家を建てる後の相続人(この場合は子)が支払っているのであれば、相続において特に問題になることはありません。
なぜなら、親の土地であっても購入した場合にはしっかりと他人扱いとして名義なども含めて変更し、購入代金が生前贈与などにはあたらないからです。
しかし2の格安で購入したという場合には、「贈与税」が課される場合があります。
例えば、時価2,000万円の土地を500万円で売ってもらった、となるとその差額は1,500万円です。
この時に見られるのは、仮に親が他人に土地を売った場合と、どういった差額が出ているのか?
というところになります。
多少の差はあったとしても土地の時価相当を基準に考えると、格安で購入した場合には1500万円は生前贈与とみなされて贈与税の対象になったり、遺産分割において生前贈与の1500万円は家を建てた人がマイナスされる場合があります。
無償で親の土地を使用していた場合は【使用貸借】となる
あまり聞き慣れない言葉ですが、親の土地などを無償で使用していた場合には使用貸借という見解になります。
使用貸借とは無償使用を前提に、あくまでも親から”借りている”という状態です。
しかし、相続が始まったからと言って家だけを移動させることなどは現実的に無理ですので、遺産分割した場合の土地評価に相当する金銭や、被相続人が他に持っている財産に関しては最低限の遺留分は他の相続人に権利が発生します。
また、そのまま土地を相続した場合には借地権の分に応じて「相続税」が増加、発生することがあります。
使用借地にしている場合には基本的に相続税に分類されることを覚えておきましょう。
親から土地を譲り受けた場合
親から土地を文字通り譲られた場合には、贈与となるので「贈与税」の対象となります。
この場合にも他の相続人がいれば最低でも遺留分については相続権利があるので生前贈与とみなされ、土地評価額から遺産分割をしたと仮定した金銭などを相続時に他の相続人に譲るか、他に相続財産がない場合には自分自身で用意しなければいけない場合もあります。
遺言書があっても遺留分は他の相続人に権利がある
遺言書は民法に規定された相続法よりも優先されますが、大前提として遺留分に関しては侵害出来ません。
遺留分に対しての減殺請求がなければ遺言書は認められることもありますが、結果的に揉める原因となりやすいですのでやはり遺留分のことに関しては生前に相談しておくほうが良いでしょう。
また、家を建てる時に上記で紹介したような
相続税にするか、贈与税にするかなどの税務に関しては専門家である税理士に相談してから決めるのが得策です。
他の財産などがある場合であれば税理士に相談しつつ、税金に関しての相談をしておけば他の相続人が受け取る財産に関してのアドバイスももらえるでしょう。
相続の生前対策は専門家のアドバイスを受けよう
親の土地に家を建てる場合は、親からどのように土地を受け取ったかによって税金が変わってきます。
遺産をめぐる争いはできるだけ避けたいものです。家を建てる前に、後の相続をどうするのか細かな条件を決めておく必要があるでしょう。
そのためには、ぜひ税理士や弁護士など専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
特に弁護士であれば、法律がからむ問題点を考慮して、その対策についての提案もできます。
相続の生前対策を弁護士へ相談するメリット
相続問題を弁護士へ依頼するメリットは、以下のとおりです。
- 生前対策のアドバイスを受けられる
- 相続で起こりやすいトラブルを未然に防いでくれる
- 相続に関する的確なアドバイスを得られる
弁護士に相談することで、生前の段階で相続問題を未然に回避することが可能になります。
先ほど、家を建てるときに相続税にするか贈与税にするか事前に決めておくことが重要だとお伝えしました。
相続問題に強い弁護士であれば、家庭の事情や被相続人となる方の意思を考慮したアドバイスが可能です。
弁護士費用が気になる方は弁護士保険も利用がおすすめ
ただ、弁護士へ相談するとなると、費用に関して不安になる方も多いでしょう。
そこでおすすめしたいのが、弁護士保険です。
弁護士保険は、日常生活の個人的トラブルや事業活動の中で発生した法的トラブルに対し、弁護士を利用した時にかかる弁護士費用を補償する保険サービスです。
通常、弁護士を通してトラブルを解決しようとすると、数十万から数百万単位の弁護士費用がかかる場合があります。
しかし、弁護士保険に加入しておくことで、法的トラブルが発生した場合に、弁護士に支払う費用を抑えられます。
弁護士費用に不安を持つ場合は、弁護士保険の利用も検討してみてください。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
弁護士保険の保証内容について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
関連記事
-
-
【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく
「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …
記事を振り返ってのQ&A
Q.親の土地に家を建てるメリットとデメリットを教えてください。
A.親の土地に家を建てることのメリットは、土地を探す必要がないことと、土地購入費用を節約できることです。デメリットは、相続トラブルに発展する可能性があるということです。
Q.親の土地に家を建てた場合、どのような税金がかかりますか?
A.親の土地を「購入した」のか、「無償で使わせてもらっている」のか、「譲り受けた」のか、などによって相続税や贈与税の種類が変化します。相続税にするか、贈与税にするかを決める際は、専門家に相談してから決めるのが得策です。