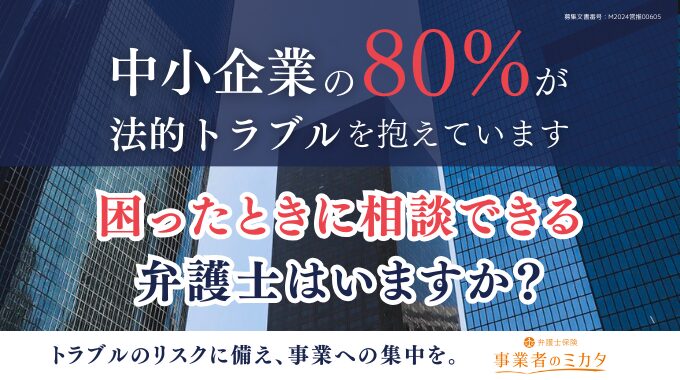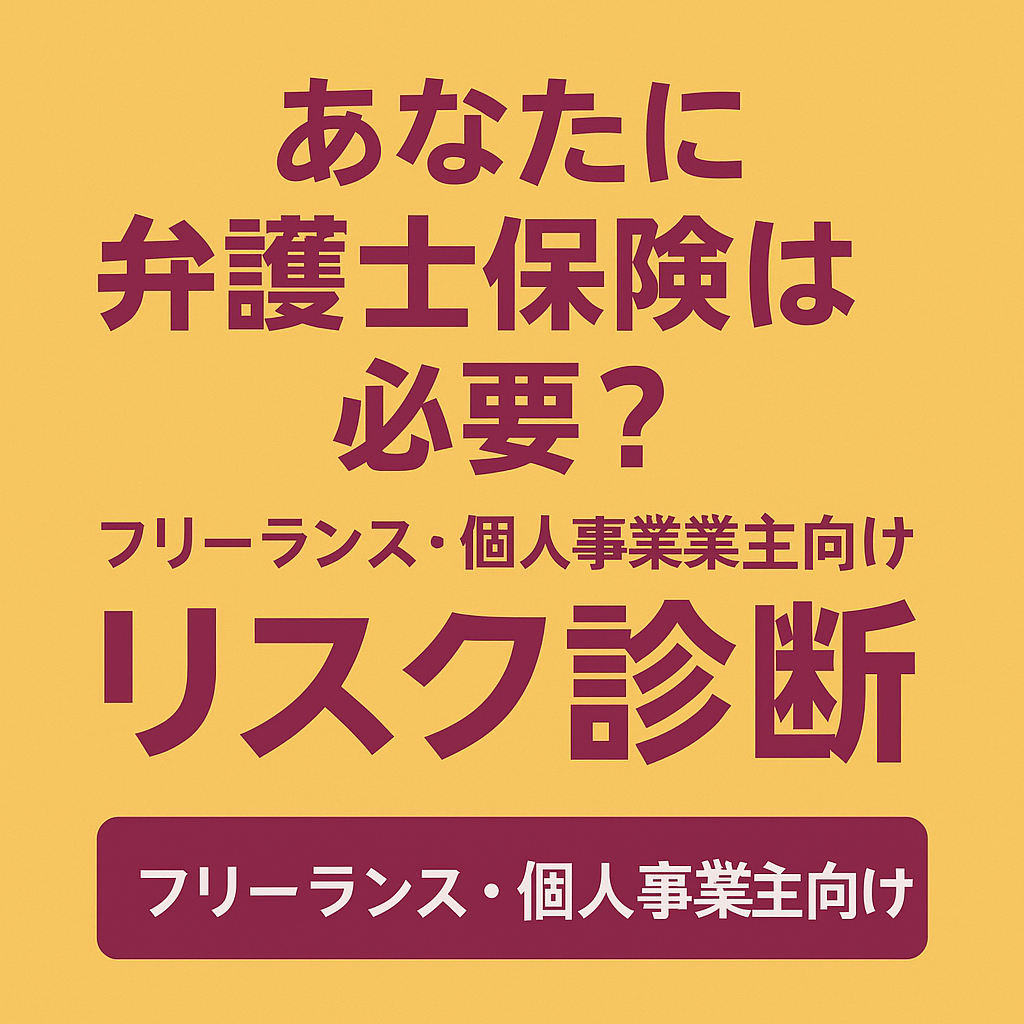企業の運営において、『顧問弁護士』を活用するケースが増えています。
『顧問弁護士』とは、企業の顧問として法務関係のアドバイスを行う弁護士のことで、法的トラブルの対処や業務に潜んでいるリスクを未然に防いでもらうことができます。
また、法律のプロフェッショナルという立場から、事業に対するコンサルティングの役割を担うことも少なくありません。
法的トラブルに巻き込まれてしまった場合、時間や手間、費用など、大きな損害になることは間違いないことから、顧問弁護士の活用を検討している中小企業の経営者は多いのではないでしょうか。
しかし、依頼する弁護士の選択方法やランニングコストなど、注意すべき点がいくつかあります。
そこでここでは、顧問弁護士の活用を考えている方のために、顧問弁護士と弁護士との違い、顧問弁護士のメリット、顧問弁護士を選ぶ基準などについて、詳しく解説していきます。
こんな疑問にお答えします
Q.顧問弁護士と一般の弁護士の違いはありますか?
A.契約期間や相談のしやすさが主な違いです。顧問弁護士は『顧問』という言葉からもお分かりの通り、継続して企業にかかわり、法律に関する相談や対処、その他ビジネス法務全般に対応する役割があります。また、気軽に相談できる、すぐさま相談できるといった点が一般の弁護士と大きな違いです。
継続して関わることからランニングコストが発生しますが、依頼するメリットが大きいといえるので、顧問弁護士に依頼する価値は大きいといえるでしょう。
顧問弁護士とは?
『顧問弁護士』というと、テレビドラマなどに登場する大企業の顧問弁護士のようなイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
企業の法務トラブルに関する場面では必ず登場し、適切なアドバイスによって法務トラブルから企業を救うといったものが、『顧問弁護士』の一般的なイメージでしょう。
ただ、顧問弁護士が担う役割は法務トラブルに限らず、また大企業だけで活用されているものではありません。
ここでは、顧問弁護士は一般的にどのような役割を担っており、どのような場所で活躍するシーンが多いのかご紹介しましょう。
企業の法務全般に関するコンサルティング
顧問弁護士の役割をひとことで言ってしまえば、『企業の法務全般に関するコンサルティング』です。
もう少し具体的に内容をお伝えすると、
- トラブルが発生したときの法的な相談や対処
- 企業のビジネスに対するリスク調査や体制の整備
- 企業に必要な契約書の作成、コンプライアンス研修など
などといったものになります。
一番にイメージするのが、トラブル発生時の相談や対処でしょう。
お客様からのクレーム、ネット上での悪質な書き込み、社内での不祥事、取引先とのトラブルなど、ビジネスでのトラブルの際には顧問弁護士がその相談や対処にあたります。
また、企業が行うビジネスに対するリスクを調べ、未然にトラブルを防ぐのも、顧問弁護士の大きな役割となっています。
特に事業展開を積極的に行う企業の場合では、顧問弁護士によるコンサルティングがとても重要な意味を持つものになります。
その他にも、必要な契約書を作成したり、企業内でコンプライアンス研修を行ったり、資金調達のアドバイスを行ったり、さまざまな場面で専門力を発揮します。
大企業だけではなく中小企業、個人事業でも
ドラマの中では大企業の顧問弁護士が、一般的なイメージであるかもしれませんが、近年では中小企業でも活用するケースが増えています。
さらには、個人事業やフリーランスでの働き方が一般化したことに伴い、個人が顧問弁護士を利用するケースも見られています。
例えば、個人で経営する飲食店や美容室、サロン、あるいはフリーランスとして請負業を営んでいるようなケースで活用されています。
そもそも、ビジネスの場面での法的なトラブルは、大企業やフリーランスにかかわらず生じるものです。
大企業であれば、コンプライアンスを重要視しなければ、どこからどのように指摘されるか分からないですし、個人事業やフリーランスであれば、立場が弱いことから不利益を被るシーンも少なくありません。
そのように考えれば、誰もが顧問弁護士を活用する可能性があると言え、事業に集中して取り組むためにも、顧問弁護士の存在は有益なものになるはずです。
顧問弁護士の費用相場
顧問弁護士の費用相場は、月3〜5万円といわれています。年間にすると36万〜60万円程度です。
ただ、この数字はあくまで相場であるため、会社規模や顧問内容によって異なります。
顧問弁護士に依頼する際は、自社の目的や予算に合ったサービスを受けることをおすすめします。
顧問弁護士と弁護士の違いは何?
基本的には、顧問弁護士だからと言って、一般の弁護士と取り組む業務に違いはありません。
ひとつ言えるのは、契約期間や相談のしやすさが異なります。
契約期間
顧問弁護士は『顧問』という言葉からもお分かりの通り、継続して企業にかかわり、法律に関する相談や対処、その他ビジネス法務全般に対応する役割があります。
一般の弁護士であれば、事件単位で携わることになります。
相談のしやすさ
顧問弁護士は会社との関わりが多くなります。
そのため、気軽に相談できる、すぐさま相談できるといった点が、一般の弁護士と大きな違いがあるのではないでしょうか。
一般の弁護士に相談するとなると、ある程度困っている、解決したいと考えた段階になることがほとんどであるため、『気軽に相談する』といった対象にはならないでしょう。
しかし、顧問弁護士の場合であれば、気になった時点で相談することができるため、大きなトラブルになる前に解決することができます。
また、トラブルに発展した場合には、顧問弁護士に相談しておけばアドバイスをもらうことや対処してもらうことができますので、事業に専念することも可能になります。
一般の弁護士に相談や依頼する場合には、弁護士を選択するところからスタートしなければなりませんので、いち早く解決に導けない可能性があるのです。
顧問弁護士を頼むメリット
- 気になることがあった時点でいち早く相談できる
- 法務トラブルが発生したときに迅速な対応してもらえる
- 事業に必要なコンサルティングを受けることができる
- 法律に関わることを気軽に相談ができる
- 法的な対応が必要になった際に割引制度が適用される
- 法務部門を設置せずに対処が可能になる
顧問弁護士を頼むメリットを、いくつかのポイントでまとめてみました。
ビジネスで生じるトラブルは、迅速に対応すればそれだけ速やかに解決することが少なくありません。
顧問弁護士を活用している場合には、いつでも気軽に相談できる体制が整いますので、気になることがあった時点ですぐに相談することができます。
その時点で適切なアドバイスをもらうことができますので、適切な対処を取ることができ、また法務トラブルとしての対応が必要である場合にはいち早く対処してもらうことも可能なのです。
相談ひとつで、トラブルに対処できるのですから、安心を得るためにも大きなメリットがあると言えるでしょう。
また、取り組んでいる事業の中にも、法的なリスクが潜んでいることが少なくありません。
事業展開でのリスク、取引先とのトラブル、顧客からのクレーム、従業員によるトラブルなど、考えればキリがありません。
しかし、顧問弁護士を活用していれば、事業に潜んでいる法的リスクを調査してもらうことができ、必要なアドバイスを受け、対処してもらうことも可能なのです。
法的な対処が必要となるトラブルが発生した場合、一般の弁護士に依頼すれば、着手料から成功報酬など、莫大な費用が必要になるケースも少なくありません。
顧問弁護士を利用している場合には、それらの費用も割引制度を活用できますので、コストを抑えることができるのです。
さらに言えば、大企業にみられる法務部門を設置せずに、法的な対処が可能になることは、かなり大幅な経費削減策となります。
顧問弁護士に依頼するデメリットはあるの?
メリットがある一方で、デメリットもあるのでしょうか?
顧問弁護士に依頼するデメリットを挙げるとすれば、ランニングコストでしょう。
現在、顧問弁護士を雇うかどうか迷っている方は、以下のような理由があるのではないでしょうか?
- 「契約しても顧問料を払ってまで相談することがあるのか?」
- 「そもそも法律に関わるトラブルに巻き込まれることはないんじゃないか?」
- 「自社で解決できるトラブルばかりで雇う意味があるのだろうか?」
顧問弁護士に依頼すると、相談件数が少なくても顧問料が発生することになります。
ただ、これまでトラブルが少なく順調に運営できていた会社でも、問題点自体に気がついていないケースも少なくありません。
顧問弁護士に依頼してはじめて問題があることに気がついたということもあるものです。
そのため、ランニングコストがかかっても、費用が無駄になることはないといえます。
健全な会社運営をするうえで顧問弁護士の存在はメリットが大きいといえるでしょう。
顧問弁護士を選ぶとしたら何がおすすめの基準になるのか?
顧問弁護士を活用してみようと考えたとしても、どのように選べばいいのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は顧問弁護士選びは、これから事業に取り組んでいくにあたって、とても大事な成功要因になってきます。
そのため、これからお伝えする3つのポイントを参考にして、選ぶようにするといいでしょう。
自社への理解
上記でもお伝えした通り、顧問弁護士の役割は企業の法務全般にかかわり、アドバイスや対処していくことにあります。
そのため、自社の事業内容に精通し、的確な法的なアドバイス・対処ができる顧問弁護士でなければ意味がありません。
法律は多岐に及び、またかかわるビジネスも幅広いために、専門特化した弁護士に顧問を依頼する必要があります。
もちろん、そのような法的な経験値の高さだけではなく、企業に寄り添い、事業展開に理解を示してくれる弁護士である必要があるでしょう。
引き受けてくれる顧問弁護士が、自社にあった人物なのか、事業を成功に導いてくれるスキルを有しているのか、しっかりとした洗い出しが必要になります。
レスポンスの早さ
法的トラブルについては、いち早く対処することが、もっともダメージが少なくて済む方法であると言えます。
顧問弁護士は、法的リスクを軽減させることを目的として活用するものですから、すぐに相談ができ、迅速にアドバイスが受けられることが大きなメリットとなります。
しかし弁護士はたくさんのクライアントを抱え多忙にしていることが多いため、連絡したときにいつでも、すぐに対応できない可能性もあります。
とは言え、すぐに相談でき、迅速に対応してくれる顧問弁護士でなければ、顧問弁護士としての価値が下がってしまうことになります。
そのため、できる限りレスポンスの早い弁護士を選んで依頼することが重要なのです。
相談がしやすいかどうか
顧問弁護士としての経験やスキル、またレスポンスの早さはとても重要ではありますが、相談しやすさや人柄のよさも大事な視点になります。
顧問弁護士を活用するということは、事業を共に取り組んでいくパートナーであるからです。
そのため、顧問弁護士を依頼するにあたっては、ネットなどでの口コミや評判なども参考にしてみることも大切です。
また、実際に面談してみる中で、自身がどのような印象を持つかについても、重要な指標となるでしょう。
顧問弁護士以外の選択:法人向け弁護士保険という選択も
冒頭から顧問弁護士を活用する意味やメリットなどについてお伝えしてきましたが、『法人・事業者向け弁護士保険』を選択するという方法もあります。
法人向け弁護士保険とはどのようなものなのか、メリットにはどのようなものがあるのか、詳しくお伝えしましょう。
法人向け弁護士保険とは
法人向け弁護士保険とは、弁護士に気軽に相談できる体制を構築でき、また費用負担を抑えることができる保険サービスです。
企業や個人事業者、フリーランスにおいては、法的な課題を抱えながら事業に取り組んでいるケースが多くみられます。
また弁護士に気軽に相談できる体制を持っていないために、困ったときでも泣き寝入りしているようなケースも少なくないのです。
そのような状況を打開し、身近に弁護士の存在を感じられるようにつくられた保険が『法人・事業者向け弁護士保険』です。
法人・事業者向け弁護士保険をおすすめする理由
顧問弁護士には多くのメリットがある反面で、どうしてもネックになるデメリットも存在します。
例えば、
- どの顧問弁護士を選べばいいのか分からない
- 継続的なコストが必要になるので活用が難しい
などといった問題です。
上記で、顧問弁護士を選ぶ基準についてお伝えしましたが、イチから自身で探すとなると、かなり大変な作業となります。
また、顧問弁護士契約を結ぶにあたって、継続的に月額費用が必要になります。
当然ながら、相談などがなかった場合でも費用は発生することになりますので、特に個人事業やフリーランスにとって大きな負担となるのは間違いありません。
そのような顧問弁護士のデメリットを克服したものが、法人・事業者向け弁護士保険と言えるのです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
Q.顧問弁護士とは何ですか?
A.顧問弁護士の役割をひとことで言ってしまえば、『企業の法務全般に関するコンサルティング』です。「トラブルが発生したときの法的な相談や対処」「企業のビジネスに対するリスク調査や体制の整備」「企業に必要な契約書の作成、コンプライアンス研修」などを行います。
Q.顧問弁護士のサービスは個人事業主でも利用できますか?
A.利用できます。個人で経営する飲食店や美容室、サロン、あるいはフリーランスとして請負業を営んでいるようなケースで活用できます。
Q.顧問弁護士と一般の弁護士の違いはありますか?
A.契約期間や相談のしやすさが主な違いです。顧問弁護士は『顧問』という言葉からもお分かりの通り、継続して企業にかかわり、法律に関する相談や対処、その他ビジネス法務全般に対応する役割があります。また、気軽に相談できる、すぐさま相談できるといった点が一般の弁護士と大きな違いです。
Q.顧問弁護士に依頼するメリット・デメリットを教えてください。
A.メリットは、以下のとおりです。
- 気になることがあった時点でいち早く相談できる
- 法務トラブルが発生したときに迅速な対応してもらえる
- 事業に必要なコンサルティングを受けることができる
- 法律に関わることを気軽に相談ができる
- 法的な対応が必要になった際に割引制度が適用される
- 法務部門を設置せずに対処が可能になる
デメリットを挙げるならばランニングコストがかかることでしょう。
Q.顧問弁護士を選ぶ基準はありますか?
A.下記の3つがポイントです。
- 自社への理解
- レスポンスの早さ
- 相談がしやすいかどうか