
離婚をする際に子供がいた場合、当然子供をどちらが引き取るのか?という点が問題になります。
これは「親権と監護権」の問題です。親権や監護権の内容やそれらの決め方を知っておかなくてはいけません。
未成年者の子供がいる夫婦が離婚する場合は、どちらかを親権者としなければならないようになっています。
通常、子供の親というのは、父母ともに子供の親権者(法定代理人)として法律行為などを行えるとともに、子供の身上を監護する(しなければならない)という権利義務を持っています。
しかし、夫婦が離婚をしてしまった場合、両者が子どもの親権者として法律行為を行うことはできませんし、もちろん両者が身上監護することもできません。
どちらも親権が欲しいと主張する場合や、どちらも親権者になりたくないと主張する場合は家庭裁判所にて親権者を決める形になります。
そこで、夫婦の離婚時には、子供の親権者の指定とともに、監護権者を個別に指定することが可能となっています。
一般的には、親権と監護権を分離することは好ましくはないのですが、夫婦の話し合いによって分離することも可能とされています。
しかし、これには様々な問題点も含まれているのです。
そこで今回は、親権と監護権を分離する場合のメリットと問題点についてご説明していきます。
こんな疑問にお答えします
Q:親権と監護権は結局どっちが強いのですか?
A:一概に「どっちが強い」とは言い難いです。
「子どもの財産管理を行うこと」や「子どもが一定の行為をする際に許可を出すこと」ができるのは親権を持つ側です。
一方、子どもと共に生活できるのは監護権を持つ側です。
それぞれの役割が明確に異なることを押さえておきましょう。親権と監護権(養育権)を別々の親が持つ場合、どちらが有利なのかという疑問をもつ方もいらっしゃるかもしれません。
親権と監護権(養育権)は異なる意味なので、単純に有利か不利かは比較できませんが、子どもと一緒に暮らすことを重視するなら監護権を取得することになるでしょう。
法定代理権は親権者がもつので、各種契約などの時には親権者の同意が必要となり、離れて暮らしている場合は少々面倒かもしれませんが、それでも子供と一緒に暮らす意義の方が大きいのではないでしょうか。
※弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
そもそも親権と監護権の違いとは?

まず、親権と監護権の分離について触れていく前に、そもそも親権と監護権にはどういった違いがあるのかを見ていきましょう。
この仕組みを理解するためには、「親権」がどういったものなのか理解するのが近道です。
親権とは?
まず、親権というのは、未成年者の子を監督保護するために子供の父母に認められた権利であり、義務であるとされています。
そして、冒頭でも触れたように、親権は父母共同で持っているのが原則です。
しかし、父母が離婚してしまった場合、一方のみしか親権者になることができません。
離婚届にも、どちらが親権者になるのかを記載しなければ受理されることはありません。
少し考えてみればわかることですが、子供の監督保護というのは、離婚してしまった父母が共同で出来ることではないのです。これには親権の中身が深く関わっています。
親権の中身
親権の中身というのは、未成年者の子の身上監護や教育を受けさせること、子の財産管理をすること、子の法律行為の代理をすること等があります。
これらは、父母が婚姻状態であるが故、成すことができる内容であって、離婚となればそうはいかなくなります。
よって、父母が離婚したとなれば、いずれか一方を親権者として指定しなければならないのです。
また、妊娠中に離婚をした場合は母親が親権者になるのが一般的とされています。
監護権とは?
しかし、例外的に親権の中でも身上監護のみをもう一方に任せることが認められています。
これが「監護権」と呼ばれるものです。
つまり監護権とは、子供を身上監護する権利義務のことで、本来的には親権の一部ではあるものの、父母が離婚した際に切り離すことができるというもの。
しかし、親権と監護権を分離させると、以下のような不都合が生じることになるのです。
関連記事
-

-
離婚調停1回目で聞かれることは?準備しておくべき3つのこと
何事においてもそうですが、初めての離婚調停で緊張しているのであれば、まずは落ち着いてイメージトレーニングをしておくことが重要です。 ほとんどの方にとっては家庭裁判所に行くこと自体、初めてなのではないでしょうか。 裁判所と …
注意したい「権」の意味とは
親権や監護権には、権利の「権」という漢字が使われています。
ただし、実際は権利のみならず「義務」も伴うことを忘れてはいけません。
例えば、子どもが親戚などからお金をもらった場合、親権者はその財産を適切に管理する義務があります。子ども本人のためにその財産を使うことは許されますが、親権者個人が手を付けてはいけません。
また、監護者は子どもが病気になった際に看病をする、病院へ連れて行く義務があります。
親権と監護権を分離するとデメリットが生じることも

冒頭でもご説明したように、親権と監護権というのは子どもの両親がどちらも持っているものです。
初めから個別に指定されている権利ではありません。
よって、多くの場合でこの2つの権利が個別になっていることを想定していないため、ただ日常生活を送っているだけでも下記のような様々な不都合が生じることがあります。
子供が交通事故に遭った場合
たとえば、子供が交通事故に遭ってしまった場合、親権者から手術の同意を求めるシーンがあったとしましょう。
通常は、父母どちらであっても一方さえ同意をすれば問題はありませんが、夫婦が離婚をし、親権者と監護権者が個別になっていたとなれば、普段子どもの監護している側の同意だけでは足りず、離れて暮らす親権者からの同意がなければならないのです。
親権者の意向を無視して勝手に手術をすることは、よほどの緊急時でも無い限り、医師も敬遠しがちなので、迅速さに欠けてしまうというのは間違いなく否めません。
子供と苗字が異なってしまうことも
その他にも、離婚時に監護権者となった母が、もし以前の苗字に戻してしまった場合、子どもと苗字が異なるといった、見た目としての不都合も生じ得るでしょう。
こういった場合、子供の苗字の変更が不可能ということはありませんが、親権者の合意がないことには変更が認められることはまずありませんので、異なる苗字に人目が気になってしまうといったことも想定されます。
これを回避しようと思うと、離婚後も自身が婚姻時の苗字を名乗り続けなければならないのです。
関連記事
-

-
子の引渡し調停(子の監護に関する処分)の注意点
子の引き渡し調停とは、離婚後に親権者以外の者が子どもを親権者のもとから連れ去っていった場合に、子どもを取り戻すために利用する家庭裁判所の手続きの1つです。 正式には、「子の監護に関する処分(子の引き渡し)調停事件」と言い …
一定の行為には親権者の許可が要る
子どもが一定の行為を行う際は、親権者の許可を得なければいけません。
一定の行為とは、例えば以下を指します。
- 子どもの預金口座を開設する
- 子どもの入学手続きをする
- 子どもがパスポートを取得する
共に生活をしているのは監護権者でありながら、このような行為に対しては親権者の許可が不可欠になるのです。離婚時よりも関係が悪化している場合は、元夫婦間で連絡を取り合うこと自体も敷居が高くなりやすいでしょう。
そのため、離婚後も「事務的な連絡は取れる関係性」を築くことが重要です。
再婚相手との養子縁組にも親権者の許可が要る
監護権者が再婚する際、監護中の子どもと再婚相手を養子縁組させる場合は親権者の許可が必要です。
スムーズに許可がもらえれば問題ありませんが、感情のもつれなどがある場合は一筋縄ではいかないケースもあります。
親権と監護権を分離する場合のメリット
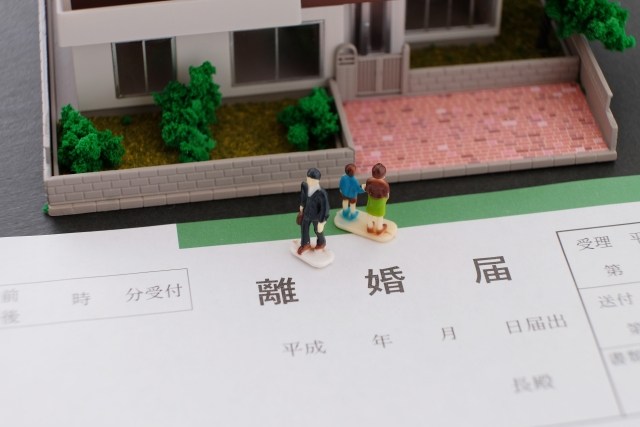
上記のように、親権者と監護権者を分離してしまうと、監護権者はわざわざ親権者から同意を得なければならない場面が生じることからスムーズに進まないことがあるのです。
では、親権と監護権を分離することに一体どのようなメリットがあるのでしょうか?
一見すると分離すること自体に不都合が生じやすいため、あまりメリットがあるようにも見えませんが、強いて挙げるとすれば、子どもに与える安心感と、離婚の話し合いがスムーズに進むきっかけになるといったところでしょうか。
子供に与える安心感
夫婦が離婚をするということは、夫婦が別々に暮らすということ。子供からすれば望ましいことではないと言えます。
しかし、一方が監護権者、一方が親権者となれば、どちらの親とも繋がりを感じることができるため、安心感を与えることが可能となります。
いくら親子の絆は切れないと伝えたところで、形式上のなにかがあるとないとでは大きな違いがあると言えるでしょう。
子供としても、監護権者・親権者の意味を完全には理解できないまでも、離婚後も自身に関わってくれているということは理解できるはずです。
離婚の話し合いがスムーズに進むきっかけにも
次に、離婚の話し合いがスムーズに進むきっかけになることもあります。
親であればわが子が可愛いのは当然のこと。
親権だけは譲りたくないと主張するのは決しておかしなことではありません。
しかし、離婚において親権者というのは必ず指定していなければならないため、親権者争いが激しくなると、いつまで経っても離婚が成立しないなんてことにもなりかねないのです。
そこで、親権者と監護権者を分離することによって、どちらにも納得のいく形で離婚を成立させられる可能性が出てきます。
たとえば、普段から仕事をしていて子供の面倒が見られない側を親権者として指定し、仕事はほどほどに(またはせずに)子供のとの時間を多く作れる側を監護権者として指定する、といった方法も可能となるのです。
関連記事
-

-
焦ってはダメ!離婚調停で相手が嘘ばかりつく時の対処法
法律問題を扱っていると、相手方が真っ赤な嘘を繰り返す場合があります。 そもそも当事者同士の見解がまったく異なるからこそ、法律問題にまで発展しているわけですから、あまり驚くことではありません。 ですが、これが家庭内の問題と …
養育費の支払いが保証されやすい
互いに親権・監護権という子どもに関わる権利を持つことにより、養育費の支払いが保証されやすくなります。
子どもと生活を共にするのは監護権者ですが、もう一方が親権を持つことで「自分も、子どもの親である」という意識が高まるためです。
一方の適性がない場合に対応しやすい
例えば、子どもの養育自体には問題がなくても浪費癖が強く財産管理は任せられないというケースもあるでしょう。
そのような場合、親権と監護権を分離する方が子どもの利益になります。
親権と監護権を分離する際の注意点

親権と監護権を分離する場合は、「親権と監護権の分離」を書面に残しておきましょう。
親権と監護権を分離した事実を書面に書き記すことで、後々のトラブルを予防できます。
離婚届や戸籍には親権者名を書く必要がありますが、監護権者名を書く欄はありません。したがって、監護権者であることの公的証明を残したい場合は自発的に作成する必要があります。
双方が合意した文書に監護権者の氏名も記載しておきましょう。
親権と監護権の分離は子供の利益を優先しよう
親権と監護権の分離する場合のメリットと問題点については以上です。
ここでもっとも大切といえるべきなのは、やはり子供の利益を優先することです。
裁判離婚の際、親権者の決定において、最も優先されることは子供の幸せです。
そのため、
父、母の事情(監護を継続できるか、子供と十分な時間が取れるかなど)
子の事情(子供は双方の親に対してどの程度愛情を持っているか、心身の状況、環境の変化があるのかなど)
実際に子を監護してきたか(監護補助者となる親族がいるかなど)
といった事情などが主な判断基準となります。
そうした上で、もちろん親権を監護権の分離が子どもの利益につながることもありますし、そうならないこともあります。
これはまさに夫婦と子どもごとにケースバイケースと言えますので、どちらが自分たちには合っているのか、子どもにとってはどちらが利益になるのか、といったことを優先しながら検討されると良いでしょう。
離婚調停や離婚訴訟においては、辛い記憶が蘇ったり、お互い感情的になってしまい、思うようにスムーズな話し合いができないケースが多く見られます。
弁護士が代理人に就くことにより、十分な相談、打ち合わせの上で裁判に臨むことが可能となります。
そのため、相手から想定していなかったことを言われた場合や、自分では上手く説明できない事柄などを弁護士が代わりに説明や反論、助言を受けることができます。
一度、弁護士に相談の上、協議を進められることをおすすめします。
今後の備えとして弁護士保険の利用を検討してみよう
弁護士に相談をする際には、弁護士の費用がかかるケースに備えて、弁護士保険に加入しておくこともおすすめです。
実際に訴訟などになった際の弁護士費用を軽減することが可能です。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』

弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
今回の記事を参考にして、上手に弁護士保険を利用しましょう。
記事を振り返ってのQ&A
Q:親権と監護権の大きな違いは?
A:親権者には子どもの財産管理を行う権利や一定の行為を許可する権利があります。
監護権者には子どもと生活を共にする権利があります。
Q:親権と監護権を分離するメリットは?
A:以下がメリットになります。
- 子供に安心感を与えられる
- 夫婦がスムーズに離婚できるきっかけになる
- 養育費の未払いを防ぎやすい
- 財産管理に適さない監護権者の場合、親権者が肩代わりできる
Q:親権と監護権を分離するデメリットは?
A:以下がデメリットになります。
- 子供が交通事故に遭った場合、親権者でなければ手術の許可を出せない
- 監護権者と子どもの苗字が異なってしまうこともある
- 子どもが一定の行為をする際に親権者の許可が必要になる
- 再婚相手と子どもを養子縁組させる際にも親権者の許可が必要になる




