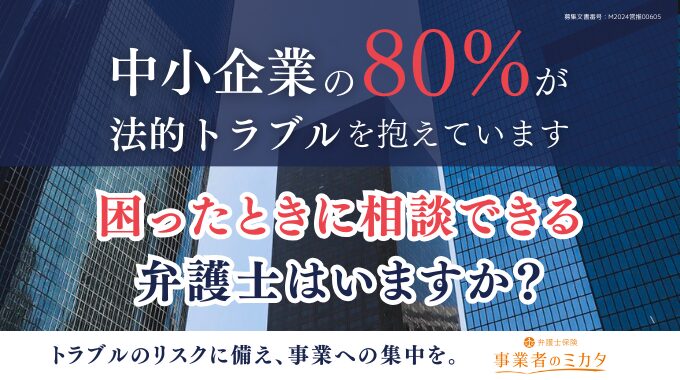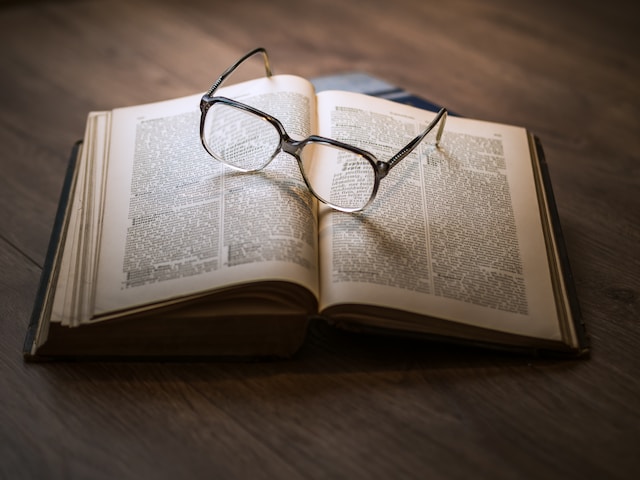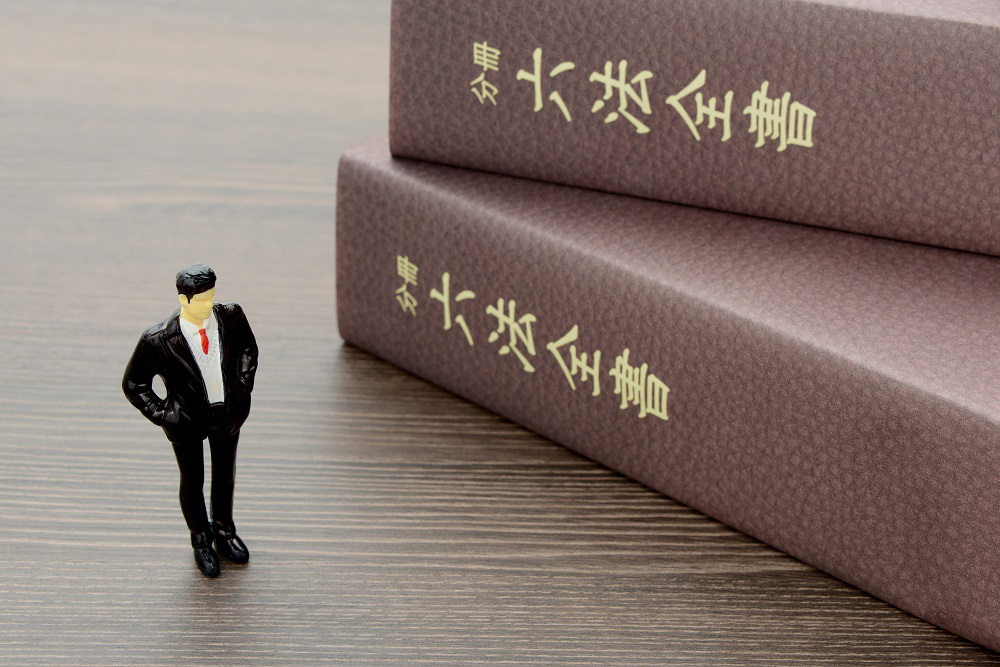
「不法行為」とは、事件や事故によって損害が生じることです。
実は、私たちの日常生活には、交通事故やケンカや不倫など、不法行為に巻き込まれる危険が潜んでいます。
被害者となる可能性だけでなく、不法行為の「加害者」となるリスクもいたるところに存在しています。
つまり、日常生活を平和に送る上で不法行為のルールを知っておくことは、とても大切なのです。
そこで今回は、「そもそも不法行為とは何か」について具体例を交えて解説した上で、不法行為が成立する要件や時効についても分かりやすく解説します。
不法行為のルールは、2017年5月に改正されたばかりです。
新しいルールは、2020年4月から始まっています。
「不法行為について勉強したことがある」という方も、今回の記事をきっかけに、新しいルールを確認しておきましょう。
こんな疑問にお答えします
A:田中靖子(元弁護士) 不法行為の被害者は、加害者に対して「事件・事故によって生じた損害を回復すること」を請求できます。このような請求のことを、法律用語では「損害賠償請求」と呼びます。
そもそも「不法行為」とは?
そもそも「不法行為」とは、どのようなものなのでしょうか?
法律上の定義では、不法行為とは「故意や過失によって誰かに損害を与えること」です。
故意(こい)とは「わざと」という意味です。
過失(かしつ)とは「うっかり」という意味です。
つまり、不法行為とは「わざと誰かに損害を与えたり、うっかり誰かに損害を与えてしまうこと」です。
不法行為の具体例
具体的には、どのような行為が不法行為となるのでしょうか?
日常生活で生じる不法行為の具体例を見てみましょう。
交通事故
不法行為の代表的なケースは、交通事故です。
脇見運転をして歩行者を轢いてしまうことや、酔っぱらい運転によって前方車に追突することは、不法行為です。
インターネット上の誹謗中傷
インターネット上の掲示板やSNSで他人の名誉を害する書き込みを行った場合は、不法行為に該当します。
他人のプライバシーを侵害する書き込みをすることも、不法行為です。
他にも「死ね」「家に火をつけてやる」のような脅迫文を投稿することも、不法行為に当たります。
なお、このような行為は、不法行為に該当するだけでなく、刑法上の名誉毀損罪や脅迫罪などの犯罪行為としても罰せられます。
-
-
【図解でわかりやすく】名誉毀損と侮辱罪の要件の違いと慰謝料の相場(悪い・根も葉もない噂を流される場合はどっち?) ※元弁護士作成記事
人に対して誹謗中傷する発言や侮辱的な発言をした場合、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。 これらはどちらも「相手に対して悪口を言った」場合に成立するイメージがありますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょう …
-
-
【判例つき】脅迫罪はどこから?脅迫罪の成立要件・構成要件、脅迫罪になる言葉、慰謝料、証拠について
他人を脅すと脅迫罪が成立しますが、具体的にどのようなケースで脅迫罪が成立するのかについては、正確に理解されていないことが多いようです。 たとえば、どのようなことを言ったら脅迫罪になるのか、電話やメール、ネット上の投稿など …
既婚者との不倫
妻子ある男性と浮気や不倫をすることは、不法行為です。
法律上結婚している夫婦には「平穏な結婚生活を送る権利」があります。
既婚者と不倫をすることは、この権利を害する行為であるため、不法行為に当たります。
-
-
慰謝料請求の内容証明書き方テンプレ|不倫・浮気相手への請求方法とは?
配偶者が不倫や浮気をしていることが判明すると、誰しも大変なショックを受けるものです。ショックの末、離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。 離婚するにしてもしないにしても、不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求したいと希望され …
ケンカ・乱闘
ケンカをして相手にケガをさせることは、不法行為です。
街なかで乱闘騒ぎを起こして、通りすがりの人物を巻き込んでケガをさせた場合にも、不法行為の責任を負います。
学校でのいじめ
学校でのいじめは、不法行為に当たります。
ただし、いじめを行った子どもがまだ幼い場合には、法的責任を追及することができません。
法律用語では、このような子どもには「責任能力がない」といいます。
いじめをした子どもに責任能力がない場合は、その親(親権者)が子どもに代わって法的責任を負います。
不法行為が成立するための4つの条件

1つでも欠けた場合には、不法行為は成立しません。
故意・過失があること
被害者を傷つけるつもりで「わざと」その行為をした場合や、加害者が「うっかり」していた場合には、不法行為が成立します。
反対に考えると、加害者がわざとその行為をしたわけではなく、うっかりしていたわけでもない場合には、不法行為は成立しません。
例えば、週刊誌がきちんと取材を行わないまま、根も葉もない記事を掲載すると、不法行為となります。
-
-
根も葉もないありもしない悪口を言いふらされた!嘘をいいふらされたら罪になるのか?名誉毀損で慰謝料をとれるかも?
私たちが日々生活していくうえで、切っても切れないご近所付き合い。 ご近所さんが集まると、ついつい噂話や悪口……なんてこともあるでしょう。 もしかしたら、ご近所さんからのいわれない陰口に悩まされている、なんて人もいるかもし …
しかし、取材をする人が、関係者に詳細な聞き取り調査を行ったうえで、裏付けとなる証拠を十分に集めたのであれば、たとえその記事が間違いであっても、不法行為は成立しません。
きちんと取材を行っている以上、「故意も過失もない」からです。
何らかの損害を受けたこと
不法行為の責任を追求するためには、何らかの「損害」が生じたことが必要です。
例えば、交通事故によって車のフロントガラスが割れた場合は、「車の修理代金」が損害となります。
足を骨折した場合は、「治療費」や「通院のための交通費」が損害となります。
しかし、交通事故で車同士が接触したにも関わらず、車に傷が生じておらず、運転者も同乗者も誰もケガをしていない場合は、「損害がない」状態となります。
なお、「損害」とは目に見える損害に限りません。
加害者の行為によって精神的なショックを受けた場合は、その「心の傷」そのものが損害となります。
例えば、夫が職場の女性と浮気をした場合、妻はその浮気行為によって精神的なショックを受けます。
この「精神的な苦痛」が、不法行為の損害となります。
因果関係があること
因果関係を分かりやすく言えば「加害者の行為が原因となって、その結果として損害が生じたこと」という関係性のことです。
例えば、いじめに悩んだ子どもが自殺した場合は、いじめをした子どもに対して、子どもを自殺に追いやったことの責任を追及することができます。
しかし、いじめられていた子どもがたまたま白血病にかかって死亡した場合は、いじめが原因となって死亡したわけではないため、死亡といじめとの因果関係は否定されます。
違法行為であること
加害者の行為に、「違法性があること」が必要です。
この点が問題となりやすいのは、スポーツ中の事故です。
基本的には、スポーツのプレー中に発生した事故には違法性はありません。
例えば、野球をしているときに、体が接触してチームメイトにケガをさせてしまうことがあります。
この場合、野球のルールに従って常識的なプレーをしていたのであれば、不法行為にはなりません。
しかし、野球の試合に負けて腹を立てて、八つ当たりでチームメイトにボールを投げつけた場合には、もはや野球のルールを逸脱する行為ですので、不法行為となります。
つまり、加害者が常識的に行動した結果であれば、たとえ被害者が損害を被ったとしても、不法行為は成立しません。
合理的な範囲を逸脱した場合に限り、不法行為となります。
不法行為が成立しないケース
ここまで、不法行為が成立する要件を解説しました。ただ、すでに紹介してきたように、スポーツ中の事故や故意・過失がない場合は不法行為が成立しないこともあります。
このほかにも、不法行為の要件を満たしていても成立しないケースがあります。
精神上の理由により責任能力がないと判断される場合
精神上の理由により、自身が行った行為に対して責任能力に欠けると判断された場合は、不法行為の損害賠償責任を負う可能性が低くなります。
たとえば、精神上の障がいを持っていることが挙げられます。
正当防衛の必要があった場合
正当防衛をする必要がある場合も、不法行為が成立しない可能性があります。
正当防衛とは、相手から急な暴力や不正を受けたときに自分を守るためにやむを得ず相手に害を与えることです。
たとえば、自分を殴ろうとした相手の隙を狙って相手の脚を蹴って倒した、家族に襲いかかろうとした加害者を後ろから押さえつけた、などです。
自身の行為が正当防衛と判断されると、法的責任を問われることはありません。
緊急避難的行為を要する場合
緊急避難的行為を要する場合も、不法行為が成立しない可能性があります。
ここでいう緊急避難的行為とは、差し迫った現在の状況から生命や身体を守るために、やむを得ずにした行為を指します。その結果、他人のものを破壊してしまったとしても、不法行為にはならない可能性があります。
たとえば、クマに襲われて他人の家に逃げ込んだ際に、塀や扉を壊してしまったケースです。
現在起きている危険を避けるためにやむを得なかった行為であれば、緊急避難が成立し責任を問われることが低くなるでしょう。
不法行為の法的責任
不法行為が起きた場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか?
不法行為の被害者は、加害者に対して「事件・事故によって生じた損害を回復すること」を請求できます。
このような請求のことを、法律用語では「損害賠償請求」と呼びます。
具体的には、どのようなことを請求できるのでしょうか?
下記では、具体的なケースを交えて考えてみましょう。
交通事故
まず具体例として、交通事故のケースを考えてみましょう。
交通事故によって車が壊れた場合は、「車の修理代金」が損害となります。
よって、損害賠償請求として車の修理代金を支払うように、相手に請求することができます。
交通事故によって足を骨折した場合は、病院の入院費や治療費、通院のための交通費などを加害者に請求することができます。
-
-
【内容証明の書き方】交通事故の相手への損害賠償請求
交通事故に遭ったとき、加害者が任意保険に入っていたら保険会社が示談交渉に対応しますが、加害者が無保険の場合、被害者が加害者本人と示談交渉を進めなければなりません。 そのようなとき、加害者が被害者からの請求に応じなかったり …
インターネット上の誹謗中傷
インターネット上で誹謗中傷をされた被害者は、不快な思いをするものの、金銭的な損害を受けるわけではありません。
このような場合は、「辛い思いをしたこと」そのものを損害として請求します。
裁判になった場合は、「どのくらい辛い思いをしたか」を金銭的に評価したうえで、相手に請求します。
このようなお金のことを「慰謝料」と呼びます。
慰謝料とは、「精神的な苦痛を緩和するために支払われる金銭」のことです。
不法行為の時効

それでは、不法行為が生じた場合、一体いつまで加害者の責任を追及をすることができるのでしょうか?
「時効」とは
不法行為の被害者となっても、永遠に加害者の責任を追及できるわけではありません。
被害者が権利を行使することができる期間には制限があります。
この期間制限のことを、法律用語では「時効」や「消滅時効(しょうめつじこう)」と呼びます。
時効によって被害者の権利が消滅することを「時効が完成する」といいます。
4種類の時効
不法行為には、4種類の時効があります。
下記の表に該当する場合は、時効によって損害賠償請求権が消滅します。
| 損害・加害者を知った時点から | 不法行為の時点から | |
| 生命・身体に関わる不法行為 | 5年 | 20年 |
| その他の不法行為 | 3年 | 20年 |
旧法との比較
不法行為の時効は、2017年5月に変更されました。
改正前と比較すると、下記のようになります。
| 損害・加害者を 知った時点から |
不法行為の時点から | ||
| 新ルール | 生命・身体に関わる不法行為 | 5年 | 20年 |
| その他の不法行為 | 3年 | 20年 | |
| 旧ルール | 全ての不法行為 | 3年 | 20年 |
この点は、専門家でも間違えやすい部分です。
新しいルールは2020年4月1日から施行されましたので、上記の表をしっかり確認しておきましょう。
不法行為の立証責任
不法行為の立証責任は、誰にあるのでしょうか?
「立証責任」とは
立証責任とは、「証拠を提出して真実であることを証明する責任」のことです。
「証明責任」や「挙証責任(きょしょうせきにん)」と呼ばれることもあります。
立証責任は被害者側にある
先ほど説明したとおり、不法行為の責任を追及するためには、4つの条件が必要です。
この4つの条件については、被害者が立証責任を負います。
つまり、被害者が損害賠償請求をする際には、下記の4つを全て立証しなければいけません。
不法行為責任の4つの要件
②加害者の行為が違法なものであること
③被害者が損害を被ったこと
④加害者の行為と損害の間に因果関係があること
4つの条件を全て正確に立証するためには、法的な専門知識が必要となります。
被害者の方が自分一人で立証しようとすると、大きな負担となってしまいます。
弁護士に依頼すれば、弁護士が事例を専門的に分析したうえで、個々のケースに応じた最適な立証計画を立ててくれます。
さらに、不法行為の立証には膨大な証拠が必要となりますが、弁護士が専門家としてのノウハウを生かして効率的に証拠を集めてくれます。
4つの条件の全てをきちんと立証するためには、法的な専門スキルが不可欠です。
不法行為の損害賠償請求をご検討されている方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
不法行為と債務不履行との違い
不法行為と混同されやすいものとして「債務不履行(さいむふりこう)」があります。
不法行為と債務不履行は、どのような点が違うのでしょうか?
両者はよく似た制度ですが、大きな違いがあります。
「債務不履行」とは
債務不履行は、加害者と被害者の間に契約がある場合など「加害者が被害者に義務を負っている場合」に問題となります。
債務不履行の代表的なケースは、病院での手術ミスです。
医師と患者は手術の金額や内容について、あらかじめ契約を結んでいます。
手術を担当する医師は、この契約に基づいて「手術を安全に行う義務」を負います。
医師が手術中にミスをすると、この義務に違反することになります。
これが「債務不履行」です。
「不法行為」と「債務不履行」の違い
これに対して、不法行為は「突発的に生じた事件や事故」を指します。
加害者と被害者が、あらかじめ契約を結んでいることはありません。
不法行為の場合は、加害者と被害者の間には何らの関係もありません。
不法行為は、無関係の当事者間で生じます。
つまり、不法行為と債務不履行の大きな違いは「加害者が被害者に対して何らかの義務を負っているかどうか」です。
| 不法行為 | 債務不履行 | |
| 意味 | 故意・過失によって損害を与えること | 契約等に基づく義務違反によって 損害を与えること |
| 具体例 | 交通事故 | 病院での手術ミス |
| ケンカで怪我を負わせる | 家賃を滞納する | |
| SNSでの誹謗中傷 | 借金を返済しない |
もちろん、不法行為の加害者と被害者が友人であることもあります。
しかし、事件や事故について、前もって契約をしていることはありません。
最後に
今回は、不法行為の基本的なルールについて解説しました。
不法行為のルールは、2020年4月から新しくなりました。
うっかり間違えないためにも、新旧のルールを正しく理解しておきましょう。
私たちの日常生活には、交通事故やケンカやいじめなど、不法行為に巻き込まれる危険がたくさん潜んでいます。
不法行為に巻き込まれた場合に備え、あらかじめ弁護士保険に加入しておくと安心です。
弁護士保険に加入していれば、いざ不法行為に巻き込まれた場合に、すぐに弁護士に相談することができます。
不法行為に巻き込まれたときに慌てないためにも、一度弁護士保険への加入をご検討されてみてはいかがでしょうか。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
弁護士保険の保証内容について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
関連記事
-
-
【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく
「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …
記事を振り返ってのQ&A
Q:そもそも「不法行為」とは?
A:故意や過失によって誰かに損害を与えることです。
Q:不法行為が成立するための4つの条件とは?
A:①故意・過失があること②何らかの損害を受けたこと③因果関係があること④違法行為であること
Q:不法行為と債務不履行との違いはなんですか?
A:債務不履行は、加害者と被害者の間に契約がある場合など「加害者が被害者に義務を負っている場合」に問題となります。債務不履行の代表的なケースは、病院での手術ミスです。これに対して、不法行為は「突発的に生じた事件や事故」を指します。加害者と被害者が、あらかじめ契約を結んでいることはありません。
[/st-mybox]