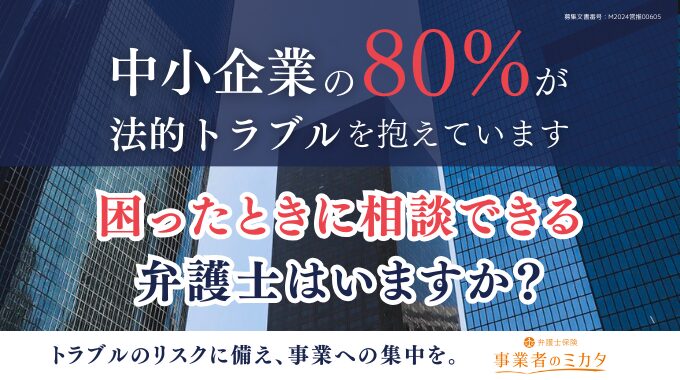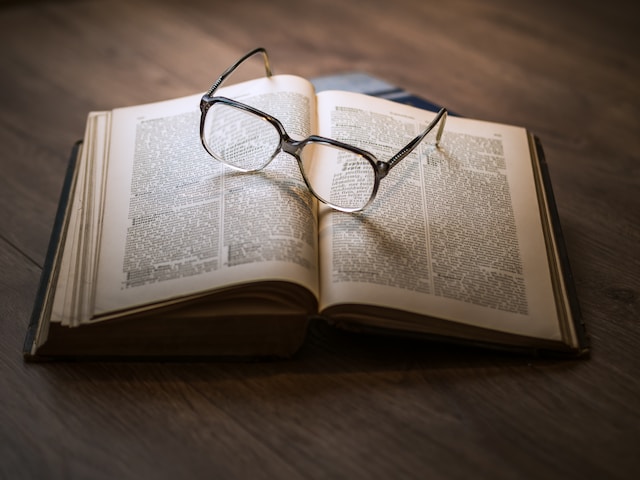ネット上の悪質な投稿や書き込みに対して、書き込んだ相手を「訴えたい」と感じる方も多いでしょう。
しかし、実際に「訴えてやる」と告げたとき、その言葉自体が脅迫罪となってしまうのか、発信者情報開示請求の対象になってしまうのか不安を持つ人もいるのではないでしょうか?
「訴える」という言葉自体は、脅迫罪に該当する可能性は低いといえます。
ただ、内容によっては、脅迫罪を含めて犯罪行為が成立するケースがあるため注意が必要です。
本記事では、脅迫罪に該当するケースと該当しないケースの違いや、発信者情報開示請求の対象になるかどうかの基準をお伝えします。
こんな疑問にお答えします
Q.ネットの書き込みが違法だと感じたので、「訴えてやる」と告知してしまいました。脅迫罪になってしまうのでしょうか?
A.脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。相手が行った不法・違法行為に対して法的手段を用いて解決を進めようとすることは、正当な権利といえます。実際に訴えなかった場合においても、正当な権利行使を告げただけでなので脅迫罪に問われる可能性も低いでしょう。
ただ、相手の権利を侵害したり犯罪行為に該当したりした場合は、法的措置の対象となる可能性があります。
自身の行為に不安な場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
「訴えてやる」という言葉を告げると脅迫罪になるのか?
「訴えてやる」という言葉を告げることは、脅迫罪にあたるものなのでしょうか。
結論からいうと、「訴えてやる」や「法的措置をとる」と伝えただけでは、脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。
オンライン上にしても対面にしても、相手が行った不法・違法行為に対して法的手段を用いて解決を進めようとすることは、正当な権利といえます。
また、「訴えてやる」と伝えて実際に訴えなかった場合においても、正当な権利行使を告げただけでなので脅迫罪に問われる可能性は低いでしょう。
ただし、相手の不法行為を追求して解決を図る目的ではなく、相手を脅して恐怖心を植え付けるために告知した場合は、脅迫罪が成立するおそれがあります。
ここで、どのようなケースが脅迫罪に該当するのか、判断が難しい部分もあるでしょう。
次の章で、脅迫罪が成立しやすいケースについて解説します。
そもそも脅迫罪とは?
脅迫罪とは、相手を怖がらせる目的で、相手やその親族の生命、身体、自由、名誉、また財産に対して危害を加える旨を告げることで成立する犯罪のことです。
日本の法律では、刑法第222条で規定されています。
第二百二十二条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
引用:e-Gov法令検索
脅迫罪は、対面のほか、手紙や電話、メール、ネット掲示板やSNSなどオンライン上でも成立する可能性があります。
たとえば、次のような言葉を告知したとします。
- 「痛い目にあわせてやる」
- 「お前のプライベートをすべて公開してやる」
- 「仕事帰りに待ち伏せして誘拐してやる」
このような言葉は、加害者が相手に対して「害悪の告知」をしていると判断されます。
害悪の告知とは、相手や相手の親族に害を加える旨を告げることを指します。
そのため、相手の不法行為・違法行為に対して「訴えてやる」「告訴する」だけでは害悪の告知にはならないため、脅迫罪にはあたりません。
しかし、訴えるという言葉に加えて危害を加える旨を告知した場合は、脅迫罪に問われる可能性があることを覚えておきましょう。
インターネットの普及に伴い、ネット上でのトラブルは増加傾向にあります。ネット上の脅迫行為もそのひとつです。
脅迫罪の成立要件や問われる責任については、こちらの記事で詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
関連記事
-
-
【判例つき】脅迫罪はどこから?脅迫罪の成立要件・構成要件、脅迫罪になる言葉、慰謝料、証拠について
他人を脅すと脅迫罪が成立しますが、具体的にどのようなケースで脅迫罪が成立するのかについては、正確に理解されていないことが多いようです。 たとえば、どのようなことを言ったら脅迫罪になるのか、電話やメール、ネット上の投稿など …
「訴えてやる」と告げた相手から発信者情報開示の対象にされる可能性は?
「訴えてやる」という言葉自体は、脅迫罪に問われる可能性が低いことがわかりました。
とはいえ、刑罰に処されることがなくとも、訴えると告げた相手から「発信者情報開示請求」をされて自身の個人情報が分かってしまうのではないかと不安な方も少なくないでしょう。
結論からいうと、「訴えてやる」という言葉だけでは、発信者情報開示請求の対象にはなりにくいといえます。
発信者情報開示請求は、すべての請求に対して認められるわけではないからです。
まず、発信者情報開示請求とは、発信者の情報をサイト運営者やプロバイダに開示請求する手続きのことです。
開示することで、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害に該当する違法な書き込みをした人の身元を特定し、慰謝料請求や民事責任を問うことができます。
では、どのような場合に発信者情報開示請求が認められるのか解説します。
どのような場合に発信者情報開示請求が認められるのか
発信者情報開示請求が認められるには、何らかの犯罪行為や権利侵害を行ったことが明らかであることが重要となります。
たとえば、以下のものが挙げられます。
- 侮辱罪
- 名誉毀損罪
- 誹謗中傷
- プライバシーの侵害
- 強要罪
- 脅迫罪
- 肖像権の侵害
- 営業権・業務遂行権の侵害
このように、他者の権利を侵害する行為や具体的な犯罪行為を立証できなければ、開示請求の対象になる可能性は低いといえます。
さらに、発信者情報開示請求が認められるには、開示を求める正当な理由が必要となります。
たとえば、以下のような理由です。
- 発信者を特定して慰謝料請求をしたい
- 謝罪を求めたい
- 刑事罰を与えたい
従って、「訴えてやる」「法的手段をとる」といった発言自体は、犯罪行為や権利侵害に該当しづらく、開示請求の対象にもなりにくいでしょう。
自分の言動が権利侵害にあたると開示請求の対象となる可能性も
一方で、「訴えてやる」という言葉以外にも相手の悪口を書き込んだ場合は、侮辱罪や名誉毀損罪に問われる可能性があります。
その場合、発信者情報開示請求の対象となることがあるでしょう。
たとえば、以下のような行為です。
- 「この発言をした人はバカでまぬけだ。訴えるぞ」
- 「〇〇は多額の借金を抱えて社会から見放されてるのに、こんな行為は許されない。法的手段で罰してやる」
違法行為を指摘するだけでなく、他者の評価を落とすような発言を述べた場合、侮辱罪や名誉毀損罪に問われるかもしれません。
ほかにも、相手を怖がらせるような発言や身の危険を感じさせるような予告をした場合は、開示請求の対象となりやすくなります。
侮辱罪や名誉毀損が成立する要件や、問われる責任についてはこちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事
-
-
侮辱罪が成立する要件は?告訴の方法と注意点も解説!
侮辱罪とは、公然の場において人を侮辱し、人格を軽視する行為する言葉や言動によって処罰される犯罪のこと。 昨今ではSNSの普及から、ネット上での侮辱行為も多発しやすく、侮辱罪は多くの人が被害に遭いやすい犯罪となりました。 …
-
-
根も葉もないありもしない悪口を言いふらされた!嘘をいいふらされたら罪になるのか?名誉毀損で慰謝料をとれるかも?
私たちが日々生活していくうえで、切っても切れないご近所付き合い。 ご近所さんが集まると、ついつい噂話や悪口……なんてこともあるでしょう。 もしかしたら、ご近所さんからのいわれない陰口に悩まされている、なんて人もいるかもし …
ネット上で権利侵害をしたかどうかで悩んだら弁護士へ相談しよう
相手の不当行為・違法行為に対して法的手段を用いて対応しようとする行為は、正当な権利行使となり、処罰される可能性は低いでしょう。
しかし、相手を脅したり権利侵害を行ったりと犯罪行為に発展した場合は、発信者情報開示請求の対象となりやすく、処罰の対象となる可能性が高くなります。
ネット上でのトラブルは複雑なものが多く、法的措置の対象になるのか判断が難しいもの。自分が他者の権利侵害をしてしまったかどうか不安な場合は、ネットトラブルに強い弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士へ相談するメリット
ネットトラブルに強い弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 相談者がどのような状況なのか聞き取りを行ってもらえる
- トラブル解決方法について法的な視点でアドバイスをもらえる
- 脅迫行為をしてしまった場合、本人の代わりに被害者と示談交渉を行ってもらえる
- 勾留されてしまった場合も、不起訴処分を獲得できる可能性が高まる
弁護士に相談することで、状況確認を含めて今後の対策に関するアドバイスをもらうことができます。
自分の行為に不安を持つ方は、ぜひ早めに弁護士に相談してみてください。
弁護士に相談できる窓口は、こちらの記事で紹介しています。
関連記事
-
-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
弁護士保険の保証内容について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
関連記事
-
-
【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく
「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …
記事を振り返ってのQ&A
Q.ネットの書き込みが違法だと感じたので、「訴えてやる」と告知してしまいました。脅迫罪になってしまうのでしょうか?
A.脅迫罪が成立する可能性は低いでしょう。相手が行った不法・違法行為に対して法的手段を用いて解決を進めようとすることは、正当な権利といえます。また、実際に訴えなかった場合においても、正当な権利行使を告げただけでなので、脅迫罪に問われる可能性も低いでしょう。
Q.脅迫罪にならずとも、発信者情報開示請求の対象になる可能性は?
A.「訴えてやる」という言葉だけでは、発信者情報開示請求の対象にはなりにくいといえます。発信者情報開示請求が認められるには、相手が何らかの犯罪行為や権利侵害をされたと明らかであることが重要となります。「訴えてやる」という言葉自体は、犯罪行為や権利侵害にはあたらず、開示請求の対象となる可能性は低いでしょう。
Q.相手に対して訴える以外の発言をした場合はどうなりますか?
A.内容によります。他者の評価を落とすような発言を述べた場合、侮辱罪や名誉毀損罪に問われるかもしれません。ほかにも、相手を怖がらせるような発言や身の危険を感じさせるような予告をした場合は、開示請求の対象となりやすくなります。