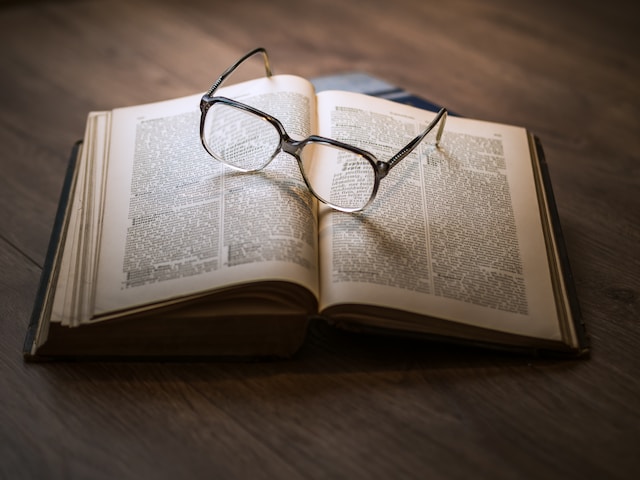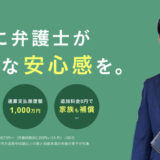たとえば、
「相手が調停の場になかなか来てくれない」
「話し合いが難航してしまった」
「精神的苦痛に耐えられなくなってしまった」
といったように、基本的にはどのような理由でも構いません。
また、調停期日に裁判官の前で「取り下げをします」といえば、担当書記官がそのように対応してくれますし、たとえ期日でなかったとしても、「調停取り下げ書」という書面の提出で簡単に取り下げることが可能です。
こんな疑問にお答えします
A.離婚調停は、一度取り下げても再度の申し立てが可能です。離婚調停を取り下げること自体に大きなデメリットはありません。ただし、取り下げ後から再度申し立てをする際は、目安として1年程度の期間を空けるようにしましょう。
また離婚調停取り下げ後、離婚訴訟への移行を検討しているのであれば必要書類の準備等が必要になります。スムーズな解決を目指すためにも、早めに専門家に相談へ行くようにしましょう。
いったん取り下げても再度の調停申立は可能
離婚調停は、いったん取り下げをしたとしても、再度の調停申立をすることができます。
「今度は事前に調停に出頭するように相手方によく伝えた」
「やはりもう一度話し合いがしたいと感じた」
など、理由はさまざまでしょうが、離婚調停は1回きりのものではありません。
極端な話をすれば、何度でも離婚調停を申し立てることが可能なのです。
ただし、前回の申立から再度の申立の期間が短すぎるような場合は、調停手続きを不当に取り扱ったと判断されてしまうような可能性もありますので、期間はほどよく空けるようにしましょう。
目安としては1年程度が常識の範囲内とされているようです。
取り下げでも調停前置を満たす場合もある
離婚には「調停前置主義」という原則規定があります。
簡単にいえば夫婦間における離婚問題は、いきなり訴訟による争いをするのではなく、まずは調停によって話し合いをしなさいというものです。
これが前提条件となっていますので、裁判所が介入する離婚問題は、必ず調停を経由してから、離婚訴訟へと移行することになります。
では、取り下げをした場合、調停前置を満たすことにはなるのでしょうか?
この答えは、取り下げた理由によるといえます。
たとえば、一度も期日が開かれないまま取り下げをすれば、それは調停前置を満たしたとはいえません。
話し合いをした結果、調停成立が見込めそうになかったので取り下げをした、といったものであれば問題はないでしょう。
その他、相手が数回の期日に一度も顔を出さなかった、というのも取り下げの理由としてはもっともなので、こちらも調停前置は満たされたと考えられています。
しかしながら、裁判所によっても若干運用は違います。
取り下げをする際は、担当の裁判官や書記官に、今取り下げをして調停前置を満たすのかどうか、ということ確認しておくようにしましょう。
相手に調停を取り下げられた場合

まだ話し合いをしたかったのに、突然取り下げをされてしまった・・・。
このような場合は、こちらから再度の調停を申し立てることもできますし、離婚訴訟へと移行することもできます。
調停前置は、申立人だけでなく相手方、つまり申し立てられた側にも当てはまることなので、今度はこちらから離婚訴訟を提起することも可能というわけです。
相手が調停を取り下げてきた場合、いくらもっと話し合いをしたいと感じていたとしても、取り下げた以上は、今度はこちらから再度の調停を申し立てたとしても、話し合いに応じてくれるとは到底思えません。
どちらにしても、離婚調停が取り下げによって終了したということは、一つの節目になります。
今後、再度の協議、再度の調停をするのか、はたまた離婚訴訟へと移行するのか、なにも変わらず現状維持となってしまうのか、こちらに関しては本人達次第といえるでしょう。
離婚調停を取り下げたらデメリットはあるのか?
ここまで離婚調停の取り下げについて解説してきましたが、取り下げることで発生するデメリットはあるのでしょうか。
結論、離婚調停を取り下げること自体にデメリットはありません。理由としては、「取り下げること=調停不成立」とはならず、別の方法で解決を目指せると判断できるからです。
従って、取り下げることで何かが不利になることはありません。
離婚訴訟へ移行させたいときの注意点
離婚調停取り下げ後、離婚訴訟への移行を検討しているのであれば、必ず裁判所にて「事件終了証明書」の申請と取得をしておきましょう。
調停と訴訟では、管轄となる裁判所が異なる場合もあるため、調停前置を証明する書面が必要になってしまうのです。
こちらは、取り下げでなく、調停不成立となった場合も同様のことがいえるので注意しましょう。
また、上記したように、取り下げをした経緯によっては、自分だけでなく相手方も調停前置の条件を満たしている場合がありますので、管轄となる裁判所には注意しましょう。
離婚訴訟の場合、自身の住所地の裁判所に訴え提起することが可能ですので、相手が遠方にいる場合、遠方の裁判所で審理をせざるを得なくなってしまうこともあります。
管轄裁判所については、複雑な規定も多々ありますので、もし離婚訴訟を検討しているのであれば、早めに専門家に相談へ行くようにしましょう。
調停前置は何年間有効となるのか?
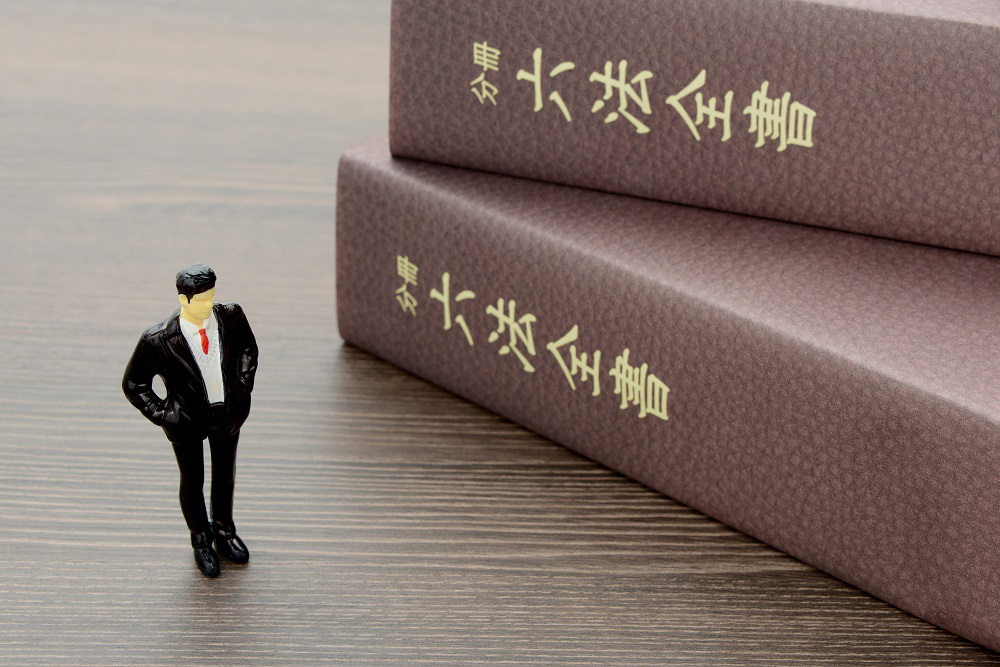
実は、こちらには法律上の規定がありません。
ただし、夫婦の様態というのは期間の経過によっても変わっていくものなので、あまりにも長期間が経過してしまっている場合は、再度の調停のやり直しを命じられてしまう可能性が高いです。
離婚問題というのは、夫婦によってケースバイケースといえますので、調停前置の有効期間についても裁判所と相談のうえ、裁判所の指示に従うようにしましょう。
離婚に関するトラブルは弁護士への相談がおすすめ
離婚調停を取り下げた後に離婚訴訟へ移行する場合は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談するようにしましょう。
離婚問題は長期化するケースが十分にあり、たとえ自分が有利な立場であっても1人で挑んでしまうと最悪敗訴になる可能性も考えられます。
離婚問題に強い弁護士に依頼することで、豊富な経験実績から早期解決をサポートしてもらえます。
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用を負担してくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
弁護士保険について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
関連記事
-
-
【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく
「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …
記事を振り返ってのQ&A
Q.離婚調停を一旦取り下げたら再度の申し立ては可能なのでしょうか?
A.可能です。離婚調停を取り下げても、何度でも申し立てられます。
ただし、再度申し立てを行うには1年程度の期間を空けるようにしましょう。
Q.離婚調停を取り下げた場合、調停前置を満たすことになりますか?
A.取り下げた理由によります。満たされる場合は、相手が期日に一度も現れなかった、話し合いをしても調停成立が見込めなかった、という理由は調停前置は満たされたと判断されます。しかし一方で、一度も期日が開かれないまま取り下げたとすれば、調停前置を満たしたことにはなりません。
Q.相手に離婚調停を取り下げられた場合は、再度の申し立ては可能ですか?
A.可能です。また、離婚訴訟へ移行することもできます。
Q.離婚調停を取り下げることでデメリットはありますか?
A.特にありません。「取り下げること=調停不成立」とはならず、別の方法で解決を目指せると判断できるからです。
Q.離婚訴訟へ移行する際の注意点はありますか?
A.必ず裁判所で「事件終了証明書」の申請と取得をしておきましょう。調停と訴訟では裁判所が異なる場合があるため、調停前置を証明する書面が必要になるからです。また、事件終了証明書は調停不成立になった場合も必要です。