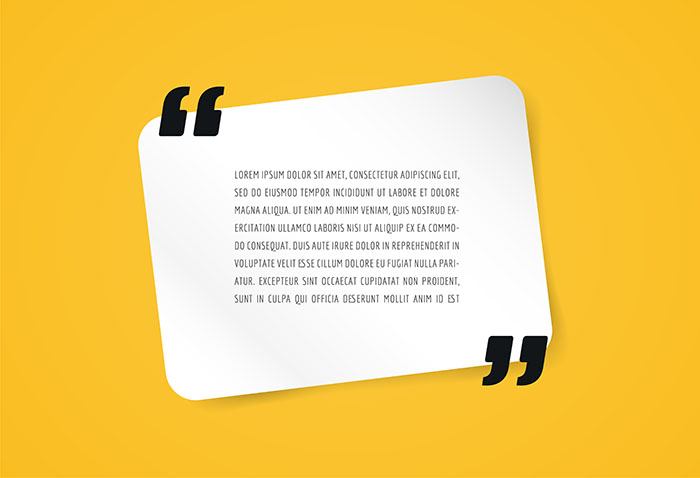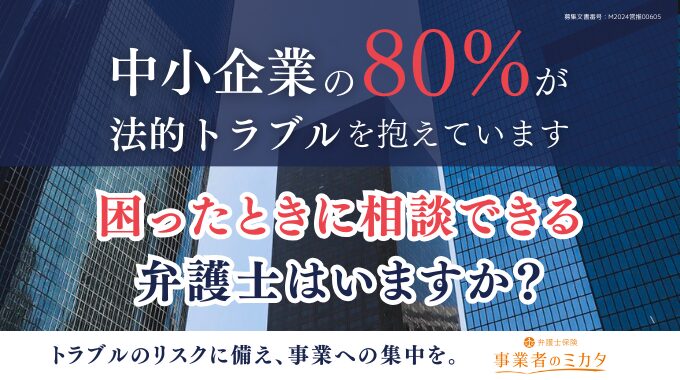近年、「ネット上の著作権侵害」が問題になった事件等をよく耳にするようになりました。
例えば、未成年の少年がテレビアニメを録画し、海外の動画保存サイトにアップロードしたり、企業のWeb担当者が自社のサイトに個人の撮影した写真を無断で使用した結果、著作権違反が問われた事案などがあります。
このような事案だけでなく、ネット上での著作権に関する問題は、至るところで日々起きています。
これには、ひと昔前までは考えられなかったFacebookやTwitterなど、SNSの普及がどうやら大きく影響しているようです。
記事の内容を動画でチェック
こんな疑問にお答えします
Q: 著作権を侵害してしまうとどうなる?
A:藤井 寿(弁護士・公認会計士)
著作権の侵害は立派な違法行為になるので、民事上の請求や刑事罰を受けることになります。
民事事件の場合には、著作権の侵害行為の差し止めや、無断で転用・転載されたことで失われた収益、またそれを行うことによって不当に得ていた収益を算出し、加えてその行為に対する精神的苦痛などへの慰謝料などを含んだものが請求される可能性が高いです。
刑事事件の場合、故意の著作権侵害には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人の代表者や従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられる可能性があります。
情報化社会の到来
インターネットは、誕生してから気付けばあっという間に現在のように普及し、それに伴って多くの情報もデジタル化され、とても便利になりました。
わからないことはインターネットで検索すれば、それに関する内容が大量に出てきますし、手軽に画像や動画や音楽を楽しむこともできます。
しかし、裏を返せば、そのような著作物を容易くコピーすることもできてしまう世の中になったということでもあります。
少し昔の大学生が、レポートのために写経をするかのごとく、ひたすら本の文章を何時間もかけて手書きでコピーしていたのに比べ、現在では範囲を選択してコピー&ペーストという数秒の作業で、一言一句間違うこともない転載が可能なのですから、時代は変わりました。
さらに今ではブログや、Twitter・Facebook・InstagramなどのSNSで、個人が色々な情報を発信できるようにもなり、文章や画像の投稿だけでなく、色々な物を多くの人と共有する機会も増えています。
そして、そんな時代だからこそ、知らず知らずのうちに著作権を侵害してしまい、それを指摘され思いがけないところから訴えられる……なんてことも、起こりうるでしょう。
そうなってしまう前に、SNS上の著作権についてしっかりと知っておくことは、これからの情報化社会を生きるには必要不可欠になりそうです。
そこで、まずは著作権に関する基礎知識からみていきましょう。
著作権って何?著作権の基礎知識
そもそも著作権とは、一体どんなものなのでしょう。
著作権の定義としては、著作権法において、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術又は音楽の範囲に属する」ものと著作物に対して発生する知的財産権と、著作権法において定義がなされています。
そして、著作権法においては、この著作物を創作した者が原則として著作者であるとされており、著作者には著作権と著作者人格権という権利が与えられると規定されています。
この著作権とは、著作財産権ともいい、著作物から得られる財産的利益を保護するためのもので、複製権・上演権・演奏権・公衆送信権・口述権・頒布権・展示権・譲渡権・貸与権・翻訳権・翻案権などから構成されます。
著作者人格権とは、作者の人格的な利益を保護するためのもので、公表権・氏名表示権・同一性保持権から構成されます。
少々難しい言葉で理解しにくいと思いますので、わかりやすく言うと「人が創作した、世の中に存在する様々なオリジナルの表現」が著作物であり、それらを利用する権利が著作権であり、その権利を持つのはそれを生み出した人である著作者である、ということです。
そのため、このような誰が創作した著作物を、その著作者の許可なしに勝手に利用してしまうことが、昨今問題となっている著作権の侵害となるのです。
著作権を侵害してしまうとどうなる?
では、こうした著作権を無視して、著作権を侵害、いわゆる著作権法に違反してしまった場合は、いったいどうなるのでしょうか。
著作権の侵害は立派な違法行為になるので、民事上の請求や刑事罰を受けることになります。
民事事件として請求されたり訴えられた場合
民事の場合は、裁判外での請求や裁判所への訴えの内容によるため、ケースバイケースではあります。
しかし、主な内容としては、著作権の侵害行為の差し止めや、無断で転用・転載されたことで失われた収益、またそれを行うことによって不当に得ていた収益を算出し、加えてその行為に対する精神的苦痛などへの慰謝料などを含んだものが請求されるでしょう。
刑事事件として告訴された場合
そして、著作権者による告訴があった場合の刑事罰では、故意の著作権侵害には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人の代表者や従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられるというものになっています。
また、著作権を侵害された者による民事上の請求と、著作権を侵害したことによる国家からの刑事罰は別個の制度ですので、民事上・刑事上の両方の責任を追及されることもあり得ます。
複製の私的な使用目的であっても・・・
さらには平成24年の法改正により、あくまで私的な使用目的であったとしても、無断アップロードされているものだと知っており、その著作物が有償で提供・提示されていることも知っていたうえで、それを自動公衆送信によってデジタル録音・録画をした場合、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられることになりました。
また、懲役刑と罰金刑は、併科されることがあります。
そのため、実際にも以下のような例があります。
ニコニコ動画の公開動画をMP3ファイルに変換してダウンロードやストリーム配信を行っていたサイト「にこ☆さうんど♯」の運営者が、著作権法違反の罪で起訴されていた訴訟で、札幌地方裁判所は7月16日、懲役3年(執行猶予4年)罰金500万円の有罪判決を言い渡した。引用元:引用元:知財情報局
もちろん内容の悪質さなどによって刑罰の重さも決まるため、すべてがこの刑罰のような重罪に問われるとは限らないのです。
しかし、著作権法違反は軽い気持ちで犯してしまいがちな犯罪であり、場合によっては非常に罪の重いものとなり得るのです。
正しい引用をしよう
著作権法違反のリスクが怖いし、他者の著作物は何もかも利用できない!……ということはなく、形式的には著作物の複製であっても、例えば批評や報道、対象の紹介などのために必要になる正当な引用は、もちろん認められています。
ただし、正当な引用と認められるためには、
・引用される著作物が公表された著作物であること
・引用する側の著作物と引用される側の著作物が明瞭に区別できること
・引用する側の著作物が主で、引用される側の著作物が従の関係があること
・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること
……といった条件が必要になってきます。
当然、どれか一つだけでも欠けてはいけませんし、オリジナルの著作物やそれを生み出した著作者へのリスペクトや配慮があれば、誰でも行えることです。
そのため、たとえ自分のSNSで友人に広めるだけだから……と言うレベルであっても、面倒くさがらずに、きちんと引用をするように配慮しましょう。
気を付けよう!うっかりやってしまいがちなSNS上の著作権侵害
ここまで著作権について学んできましたが、この情報化社会の中で、みなさんも気付かないうちにうっかり、または意図と反して著作権を侵害している可能性があります。
実際に、私自身もインターネット上のブログや、Twitter・Facebook・InstagramなどのSNS上で、これはまさに……というものをよく見かけますので、うっかり簡単にやってしまいがちな、著作権侵害となる行為を最後にまとめてみました。
是非ご自身のインターネットや、SNS上での振る舞いと照らし合わせてみてください。
プロフィールのアイコン
一つ目は、好きな人物やイラストの画像を、SNSなどのトップ画像やアイコン画像に使うことです。
いわゆるアニメや漫画のキャラクターなどの画像が挙げられます。アニメや漫画のキャラクターにアレンジを加えて投稿した場合でも、著作権の侵害になる可能性が高いです。
基本的には人気商売だからと放置され気味ですが、違法とされない「私的利用」の範囲を超えるおそれがありますし、とりわけインターネット販売などの商売に使う場合は、著作権侵害とされるおそれが大きいので気を付けましょう。
二次創作
二つ目は、漫画の1コマを使った二次制作です。
よくブログのトップにアイキャッチとして漫画の1コマが使われていたり、漫画の1コマを使った笑いをとったり、といったSNS投稿などを見かけますが、これも著作権侵害となることがあります。
翻訳
三つ目は、海外の書籍や記事を翻訳などすることです。
もちろん前述のように正当な引用であれば全く問題はありませんが、無断であったり、内容を新たにアレンジしてしまったり、なども著作権侵害にあたるので注意が必要です。
自分のものとして投稿
四つ目は、人気だったり面白かったりした文章や画像を自分のものとして投稿することです。
SNS上で人気のフレーズや面白かった話、画像などを自分のものとして拡散したくなる気持ちはわかりますが、どんな短文でも他者の投稿や画像にはしっかりと著作権が存在するため、これも著作権侵害にあたります。
他人が撮影した風景写真をあたかも自分のもののように投稿した場合も著作権を侵してしまう点に注意してください。
著作権を侵害せずにコンテンツを制作する方法
では著作権侵害にならないコンテンツを作成するにはどういう方法があるのでしょうか。以下、3つの方法を紹介します。
一つ目は、コンテンツを自作することです。
自作のコンテンツであれば著作権も自分にあるため、心配するようなことはありません。例えば自身で制作したイラスト、自身で撮影した写真などが該当します。
ただ、既存のキャラクターに類似したイラストを制作してアイコンなどに使った場合は、著作権の侵害となる可能性もあります。そのため、既存のキャラクターをモチーフにしたようなアイコンを制作しないように注意しましょう。
二つ目は、著作権フリー素材を使うことです。
著作権フリー素材は、利用規約を遵守すれば自由に使用できます。
著作権フリー素材を掲載するサイトからダウンロードして、アイコンにするのも良いでしょう。
三つ目は、デザイナーに制作を依頼することです。
現在はフリーで活躍しているデザイナーも多く、コンテンツ制作も気軽に依頼できる環境が整っています。
ただし、依頼した場合でも基本的にコンテンツの著作権は依頼者ではなく制作者が持つことは頭に入れておきましょう。依頼者は制作物を利用可能範囲で使用するのは認められますが、制作物をその他の用途で使う権利は持ち合わせていません。
著作権も譲渡してほしい場合は、後のトラブルを予防するためにも予め発注時に制作者へ相談しておきましょう。
最後に
SNSの登場により、誰もが自分で文章を書いたり、独自の画像をアップしたりと著作者になる時代がやってきました。
しかし、今の世の中では、未だに多くの人が何気なくSNSを使っていることにより、気付かないままに著作権を侵害され、また反対に著作権を侵害してしまっていることが少ないのかもしれません。
新たなSNSの文化を秩序立てるためにも、今後私たち一人ひとりが著作権について正しい知識を持つことが、非常に大切なことだと思います。
SNSはさまざまなトラブルが起きやすいもの。トラブルに巻き込まれてしまったら、弁護士へ相談してサポートを受けるのも一つの手です。
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
法人・個人事業主の方で法的トラブルにお困りの場合には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
今回の記事を参考にして、上手に弁護士保険を利用しましょう。
記事を振り返ってのQ&A
Q:著作権って何?
A:わかりやすく言うと「人が創作した、世の中に存在する様々なオリジナルの表現」が著作物であり、それらを利用する権利が著作権であり、その権利を持つのはそれを生み出した人である著作者である、ということです。
そのため、このような誰が創作した著作物を、その著作者の許可なしに勝手に利用してしまうことが、昨今問題となっている著作権の侵害となるのです。
Q:著作権を侵害してしまうとどうなる?
A:著作権の侵害は立派な違法行為になるので、民事上の請求や刑事罰を受けることになります。
民事の場合:
著作権の侵害行為の差し止めや、無断で転用・転載されたことで失われた収益、またそれを行うことによって不当に得ていた収益を算出し、加えてその行為に対する精神的苦痛などへの慰謝料などを含んだものが請求されることが多いです。
刑事の場合:
著作権者による告訴があった場合の刑事罰では、故意の著作権侵害には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人の代表者や従業員等が著作権侵害行為をしたときは、行為者のほか、当該法人も3億円以下の罰金に処せられるというものになっています。
Q:正しい引用とは何ですか?
A:正当な引用と認められるためには、
・引用される著作物が公表された著作物であること
・引用する側の著作物と引用される側の著作物が明瞭に区別できること
・引用する側の著作物が主で、引用される側の著作物が従の関係があること
・報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内であること
……といった条件が必要になってきます。
Q:うっかりやっていしまいがちなSNS上の著作権侵害とは?
A:①プロフィールのアイコン②二次創作③翻訳④自分のものとして投稿
・【事例で学ぶ】SNSでの誹謗中傷による刑事告訴~投稿者と示談が成立したケース
2021年8月、コロナ禍で開催されたオリンピックでは日本選手が大活躍する一方で、SNS上において誹謗中傷されていることが話題となりました。卓球混合ダブルスで金メダルを獲得した水谷隼選手は、自身のツイッターアカウントにおいて、自身に届いた誹謗中傷DMの具体的な内容を告白しています。
その内容は「死ね!」「くたばれ!」「消えろ!」といった直接的な暴言から、「お前不倫してるの?」「人間やめたれよ」といった根拠のないもの、「消せばいいじゃん」といった水谷選手に責任転嫁するものなど、さまざまであったようです。
さらに、すぐさま然るべき措置を取るとして、毅然とした対応を行うとしています。
近年、SNSなどネット上での誹謗中傷が社会問題としてクローズアップされ、対策が進んでいることもあり、さまざまな相談窓口が設置されるようになりました。今回ご紹介する事例は、「はるかぜちゃん」として親しまれてきた春名風花さんに対するSNSでの誹謗中傷によるものです。2010年、9歳の頃からSNSでの情報発信を行っており、その頃から誹謗中傷に悩まされていたのです。
当時はそのような判例もなかったことから、刑事告訴を経て、示談金による告訴の取り下げに応じるまで、すでに誹謗中傷が始まってから10年が経過していました。ここでは、この事例の経過と共に、SNSの誹謗中傷に対する刑について考えてみたいと思います。
・【事例で学ぶ】リツイートで名誉毀損が認められた!?リツイートに損害賠償リスクはあるの?
ツイッターなどのSNSには「リツイート」と呼ばれる便利な機能があって、他人のツイートを自分のアカウントから再発信することができます。他人がつぶやいた共感できる内容、好きな芸能人の投稿などをはじめ、ブックマークのつもりでリツイートしている方も多いのではないでしょうか。
しかし、そのような便利な機能であるリツイートによって、損害賠償が命ぜられたとしたらどうでしょう。実は、リツイートが損害賠償の対象になったという事例はいくつかあります。
先日ご紹介した記事『【事例で学ぶ】元市議会議員が事件とは無関係の人をSNSで拡散~デマ情報に対し損害賠償請求が認められたケース』では、デマがSNSによって拡散されてしまったというものですが、被害にあった女性はリツイートに対しても法的措置を取る意思を表面したことで注目されました。
ここでご紹介する事例は、現在はテレビタレントとしても活躍する弁護士の橋下徹氏が、第三者によるネガティブな投稿をリツイートする行為は、名誉毀損にあたるとして訴えをおこしたものです。
この訴えに対して、一審では名誉毀損を認定して33万円の支払いを命じ、二審においても判決を支持して控訴を棄却しています。
果たして、このリツイートがなぜ名誉毀損に該当するのか、事例を踏まえながら解説していきたいと思います。