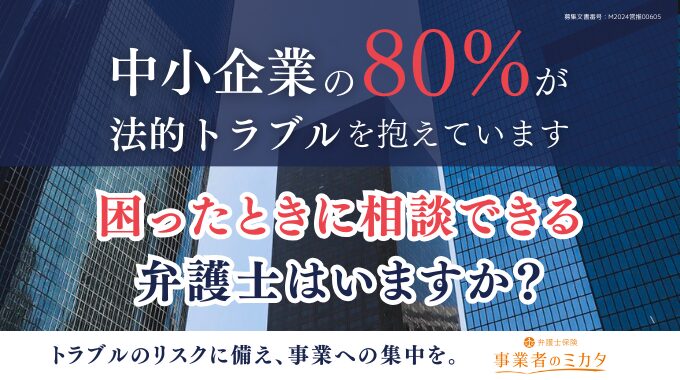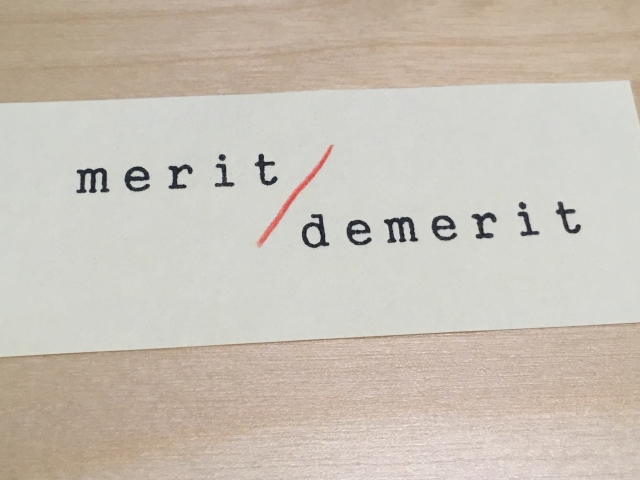訴状を無視してもよいのでしょうか?
裁判を欠席するとどうなるのでしょうか?
今回は、裁判所から訴状が届いた場合に、訴状を無視して裁判を欠席するとどうなるのかについて、法的な観点から分かりやすく解説します。
※関連記事→「内容証明を無視したら・無視されたらどうなるのか」
こんな疑問にお答えします
A.初回の裁判に欠席しても問題ありません。ただし、欠席する場合は「答弁書」を提出するようにしましょう。「答弁書」とは、あなたの言い分を伝えるための書類です。ただ、答弁書の提出をせずに2回目以降の裁判も欠席をすることで、あなたが不利な状況になってしまいます。どうしても裁判に出席できないという正当な理由がないのであれば、2回目以降の裁判には必ず出席するようにしましょう。
答弁書の書き方や、裁判に関して不安が少しでもある場合は、弁護士のサポートを借りることも視野に入れてみてください。
そもそも「訴状」とは何か
「訴状」とは、裁判所から届く手紙のことです。
訴状には「◯◯さんがあなたに対して裁判を起こしました」ということが記載されています。
訴状が届いたということは、「既に裁判が始まっている」ということを意味します。
裁判は、裁判所に訴状が提出されることによって始まります。
裁判所に訴状が提出されてからあなたの元に訴状が届くまでに、通常、1週間ほどかかります。
つまり、あなたが訴状を受け取った時点で、裁判が始まって既に1週間ほどが経過しているということです。
「既に裁判が始まっている」といっても、慌てる必要はありません。
訴えられた人がきちんと準備できるように、第1回目の裁判の期日は、およそ1ヶ月後に設定されています。
訴状をよく見ると「第1回口頭弁論期日(こうとうべんろんきじつ)」という言葉が書かれています。
その日時が、第1回目の裁判が行われる日時です。
この1ヶ月の間に、弁護士を探したり、事件の関係者に相談をしたりするなど、第1回目の裁判に向けて準備をすることになります。
準備をする期間は1ヶ月ほどありますので、落ち着いてゆっくり方針を検討しましょう。
初回の裁判に欠席するとどうなるのか
訴状には、第1回目の裁判の日時が書かれています。
この日時は裁判所が決めた日時です。
平日のビジネスアワーが指定されますので、お仕事などで忙しい方は、出席することが難しいかもしれません。
仮にあなた自身が出席できる場合であっても、あなたが依頼した弁護士がその期日に別の予定が入っている可能性があります。
このように、第1回目の裁判については、出席できない方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、心配する必要はありません。
第1回目の裁判に出席できない方のために、欠席しても不利にならないための制度が設けられています。
この制度を「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」といいます。
第一回口頭弁論期日に認められる例外|擬制陳述について
それでは、擬制陳述とはどのような制度なのでしょうか?
訴状が届けられた封筒には「答弁書(とうべんしょ)」という書類が同封されています。
この「答弁書」をきちんと提出しておけば、欠席しても不利に扱われることはありません。
「答弁書」とは、あなたの言い分を伝えるための書類です。
相手が訴えた内容に間違いがあったり、事実と異なる内容が含まれていれば、答弁書にその旨を記載することができます。
答弁書にあなたの言い分をきちんと記載しておきさえすれば、第1回目の裁判に欠席しても不利になることはありません。
答弁書を提出しておけば、「第1回目の裁判に出席して、答弁書に書いてあるとおりに発言したもの」と扱ってもらえるのです。
以上のように「裁判を欠席したにも関わらず、裁判に出席して発言したものと扱ってもらうこと」を、擬制陳述といいます。
答弁書の提出方法
ここで、答弁書の提出方法について解説します。
答弁書を裁判所に提出する際は、以下のことを記載します。
- 事件番号
- 事件名
- 当事者名
- 裁判所から書類を受け取る場所
- 訴えられた内容について、その請求の認否
- 反論があればその主張も記載
作成した答弁書は、裁判所と原告側に渡すことになるためコピーを2部作成し、合計3部用意してください。
直接持参しても構いませんが、郵送する場合は内容証明郵便を利用して、相手が受け取ったことを確認できるようにしましょう。
答弁書の提出に不安を覚える場合は、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
また、内容証明郵便の書き方については、こちらの記事を参考にしてみてください。
関連記事
-
-
【弁護士に任せる?自分でできる?】内容証明郵便の出し方と費用
契約の取り消し、金銭の請求などの、自分の意思を伝えたことを証明したいとき。または、パワハラセクハラ、配偶者の不貞行為などの、被害事実を主張したことを証明したいとき。このようなトラブルに巻き込まれた場合は、内容証明郵便を使 …
答弁書を提出しないまま欠席するとどうなるのか
前述の通り、答弁書にあなたの言い分をきちんと記載しておけば、第1回目の裁判に欠席しても不利になることはありません。
それでは、答弁書を提出しないまま第1回目の裁判に欠席すると、どうなるのでしょうか?
答弁書を提出することなく第1回目の裁判を欠席すると、「相手の言い分が全て正しい」と認めることになってしまいます。
裁判所からすれば、訴状を無視して裁判を欠席するということは「争う姿勢が無い」「反論が無い」ということになります。
当事者に争う意思が無い以上、裁判所が積極的に事実関係を調査することはありません。
このように「裁判を欠席した人について、相手の主張を全面的に認めたものとみなすこと」を、「擬制自白(ぎせいじはく)」といいます。
よって、訴状の内容に不備が無ければ、原告の請求をそのまま認める形で判決が出されてしまいます。
これを「欠席判決」といいます。
裁判に欠席した人は、相手と争うチャンスを自ら放棄したといえるのです。
つまり、「欠席判決」という制度は、裁判を欠席した人物へのいわばペナルティーという意味を持ち合わせています。
訴状に書かれている期日に必ず出席しなければいけないのか

しかし、「自分の知らないところで裁判が進むのは心配である」という方がいらっしゃるかもしれません。
このような場合、裁判所に連絡をすれば、第1回目の期日を変更してもらえることがあります。
第1回目の裁判の日時は、裁判所が決めた日時です。
もし予定が合わなければ、裁判所に連絡をして、日程を変更してもらうようにお願いしてみましょう。
スケジュールの調整については、相手の弁護士ではなく、裁判所に連絡します。
裁判所に連絡をすると、裁判所から相手方に連絡をしてくれます。
裁判所の連絡先は、訴状の中に記載されています。
訴状の中には、裁判を起こした相手の名前や相手の弁護士の連絡先なども書かれているので、間違えないように注意しましょう。
なお、日時を変更してもらえるかどうかは、ケースバイケースです。
裁判所の空き状況によっては、変更してもらえないことがあります。
しかし、第1回目の期日に限っては「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」の制度がありますので、日時を変更してもらえなくても心配する必要はありません。
2回目以降の裁判を欠席するとどうなるのか
それでは、第2回目以降の裁判を欠席すると、どうなるのでしょうか?
あなたが「相手の主張が間違っている」ということを答弁書で主張すると、あなたが指摘した箇所について、第2回目以降の裁判で証拠調べをすることになります。
証拠調べは、裁判所で行われます。
裁判に欠席し続けると、あなたから証拠を出すことができないうえに、相手方がどのような証拠を提出したのかを正確に把握することができないため、大きな不利益となります。
また、正当な理由がないまま裁判を欠席し続けていると、裁判官からの印象が悪くなるというデメリットもあります。
このように、2回目以降の裁判に欠席し続けると、あなたにとって不利な結果となってしまいます。
反対に、相手方にとっては相当に有利な状態になります。
あなたが欠席すればするほど、相手方が勝訴をする確率が高くなっていきます。
よって、どうしても裁判に出席できないという正当な理由がないのであれば、2回目以降の裁判には必ず出席するようにしましょう。
なお、証拠調べに出席しないからといって、それだけで裁判に負けてしまうとは限りません。
相手方が適切な証拠を提出しなければ、裁判所が相手の請求を認めない可能性もあります。
ただし、相手方にとって有利な証拠ばかりが提出されて、あなたの主張を支える証拠が一つも無ければ、相手方が勝訴する確率は格段に高くなります。
弁護士に依頼した場合は出席しなくてよい

弁護士が裁判に出席すれば、「本人が出席したもの」と扱われますので、欠席判決となるおそれはありません。
弁護士が答弁書を作成して提出してくれるため、擬制自白の心配もありません。
答弁書を提出していなくても、弁護士があなたの代わりに第1回目の裁判に出席すれば、不利に扱われるリスクはありません。
弁護士が裁判に出席すれば、本人が出席するのと同じ効果がありますので、あなた自身が裁判に出席する必要はありません。
このため、弁護士に依頼している方のほとんどは、裁判に出席することはありません。
なお、離婚調停のような家事事件に限っては、弁護士に依頼している方であっても、当事者本人が出席することが必要とされています。
離婚するかどうかは身分を大きく左右する出来事なので、代理人に一任することはできず、裁判所が本人の意向を直接確認することが必要とされているからです。
最後に
突然裁判所から訴状が届いたとしても、慌てる必要はありません。
第1回目の裁判までには、1ヶ月ほど時間があります。
落ち着いてゆっくり準備をしましょう。
訴状に書いてある日時に出席できない場合は、きちんと答弁書を提出しておきましょう。
答弁書の書き方がわからない場合は、弁護士に相談しましょう。
第1回目の期日に出席できなかったとしても、あらかじめ答弁書を提出しておけば、不利に扱われることはありません。
反対に、答弁書を提出しないままに裁判を欠席すると、相手の請求を全て認めたことになってしまいます。
どうしても裁判に出席できない場合は、弁護士に依頼して対応をお願いしておきましょう。
弁護士が裁判に出席すれば、本人が出席するのと同じ効果があるため、あなた自身が裁判に出席する必要はありません。
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。
保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』

弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
記事を振り返ってのQ&A
A.初回の裁判に欠席しても問題ありません。ただし、欠席する場合は「答弁書」を提出するようにしましょう。答弁書とは、あなたの言い分を伝えるための書類です。答弁書をきちんと提出しておけば、欠席しても不利に扱われることはありません。
Q.答弁書を提出しないとどうなりますか?
A.答弁書を提出しないまま裁判を欠席してしまうと、相手の言い分が全て正しいと認めることになり、あなたが不利な立場になってしまいます。
Q.そもそも、裁判の日程を変更してもらうことはできないのですか?
A.裁判所に連絡をすれば、第1回目の期日を変更してもらえることがあります。スケジュールの調整については、裁判所に連絡します。裁判所に連絡をすると、裁判所から相手方に連絡をしてくれます。日時変更が通るかどうかはケースバイケースですが、もし初回の裁判に都合が合わない場合は変更依頼を出してみるといいでしょう。
Q.2回目以降の裁判を欠席するとどうなりますか?
A.欠席を繰り返すことで、あなたが不利な状況になってしまいます。裁判に欠席し続けると、あなたから証拠を出すことができないうえに、相手方がどのような証拠を提出したのかを正確に把握することができません。どうしても裁判に出席できないという正当な理由がないのであれば、2回目以降の裁判には必ず出席するようにしましょう。