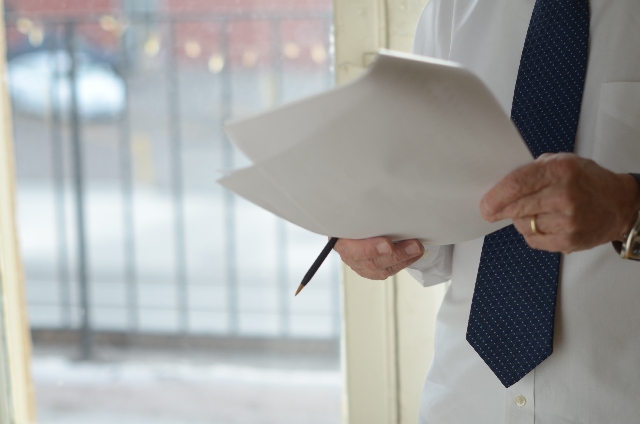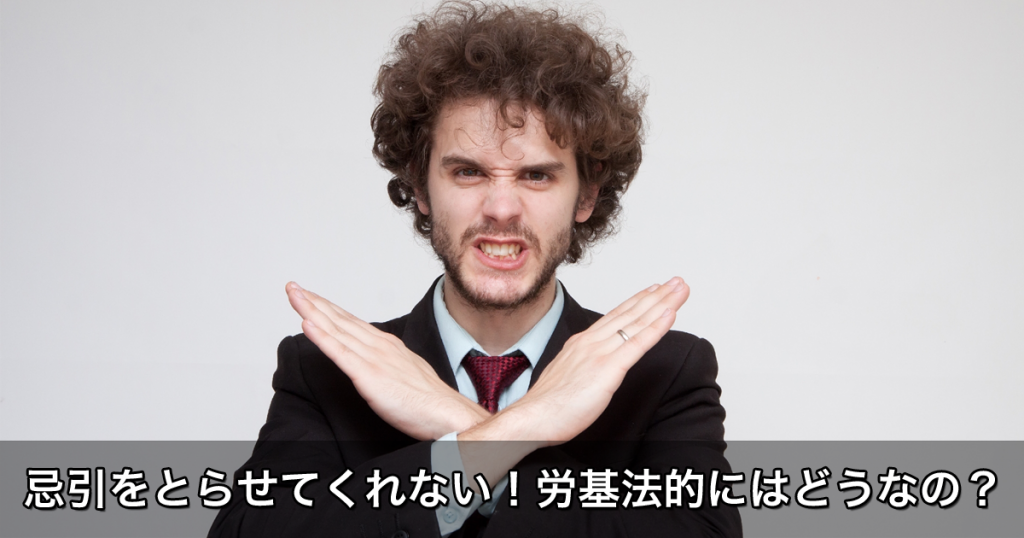
今日は、慶弔休暇の忌引についてお話したいと思います。
休みとはいっても、葬儀の何から何までを手配しなければいけなかったり、遠方の親類の葬儀に泊まりがけで参列したりと、逆に気の休まるヒマもないのが本当のところでもあります。
今日は、会社における忌引きの実態に迫ってみましょう。
記事の内容を動画でチェック
こんな疑問にお答えします
Q: どうしても休ませてくれない会社に対して、どうすればいいの?
A:平賀 律男(パラリーガル)
私見ですが、忌引きのような正当な理由があるのに、会社が欠勤を頑なに拒むことは、社会通念に照らして適切な行為だとは到底いえません。
「この会社もブラック企業かもしれない」と考えるきっかけは、日常のちょっとしたところにも転がっています。
おかしいなと思ったことがあっても、会社という組織の中ではなかなか口には出しにくいものですが、そういうときに誰かに相談できる環境を整えておくことが、自分を守るためにも大切なことだといえます。
※弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
Q: 忌引きがない会社・職場は法律上、許されるのでしょうか?
A:平賀 律男(パラリーガル)
はい、法律上は許されます。
日本の労働基準法には、忌引き休暇に関する明確な規定はありません。そのため、忌引き休暇を設けるかどうかは企業の裁量に委ねられています。多くの場合、就業規則や企業の慣習に基づいて忌引き休暇が設定されていますが、これがない場合でも、法律に違反しているわけではありません。
Q: 忌引きに関する法律はどのように規定されていますか?
A:平賀 律男(パラリーガル)
労働基準法には忌引き休暇に関する規定がありません。
ただし、多くの企業では慶弔休暇として忌引き休暇を就業規則に盛り込み、労働者に一定の休暇を提供しています。これが有給か無給かは企業の判断次第ですが、就業規則に明記されている場合は、その内容に従う必要があります。また、忌引き休暇がない場合でも、労働者は年次有給休暇を利用して休むことが可能です。
労基法には規定がない
いつもなら、「まずは労基法の規定を見てみましょう」と入るところですが、忌引きについては労基法に何の規定もされていません。
休暇として労基法が定めているのは、1週1休の原則と年次有給休暇、産前産後休業、それに生理休暇くらいです。
しかし、実際には、親族の葬儀による忌引き制度がある会社は全体の9割にのぼっており(東京都産業労働局の調査による)、忌引きがとれることはもはや日本の常識になっているといえます。
それらの企業はどうやって忌引きの制度を導入しているのでしょうか。
労働条件といえばやっぱり就業規則
会社が労働条件を定めるのにもっとも一般的に利用するのは「就業規則」です。
就業規則は、労基法やその他の法律に抵触しない限りは、基本的には会社が自由に内容を定めることができます。
毎度お決まりの展開ですね。
会社は、その就業規則のなかで、年次有給休暇とは別に、労働者に対する福利厚生の一環として慶弔休暇や病気休暇などの制度を設けている、というのがよくあるパターンです。
このように、会社が特別に与えている休みを「特別休暇」ともいいます。
よく聞く「リフレッシュ休暇」などの仲間だと思ってください。
厚労省のモデル就業規則でも、以下のとおり、慶弔休暇や病気休暇を設ける際の例が示されています。
第26条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき ○日
② 妻が出産したとき ○日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき ○日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき ○日
第27条 労働者が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、病気休暇を○日与える。
※関連ページ→「就業規則の周知義務。見たことがない規則に効力はある?」
忌引きの規定がある=有給というわけではない
モデル就業規則の第26条のように、会社が就業規則に忌引きの規定を設けた場合には、会社は労働者からの忌引きの申し出を拒むことはできません。
しかし、忌引きの規定があるからといって、それが必ずしも有給で休めることとはイコールではないことに注意が必要です。
モデル就業規則の第26条には有給か無給かが記載されていませんが、例えば第26条のあとに「ただし、慶弔休暇は有給とする。」と定められていれば、会社は忌引きの労働者に賃金を支払わなければなりません。
逆に、「無給とする」とあれば、労働者は給料なしでただ休む権利だけがあることになります。
そして、モデル就業規則のように、どちらとも定めのない場合には、その会社の慣習によることになるでしょう。
忌引きの規定がないときは?
会社が忌引きの制度を定めていないからといって、会社が「忌引きを認めない!」と突っぱねることはできません。
労働者は年次有給休暇を使えば会社を休むことはできますし、会社が年休の利用目的によってその申請を拒否することは原則できないからです。
では、すでに年次有給休暇を使い切っているとか、雇入れ後すぐでまだ付与されていないとかいう場合はどうでしょうか。
労働契約によって、労働者には会社に対して労務を提供する義務がありますが、「欠勤権」みたいなものが認められているわけではないので、理由はどうあれ勝手に休むと、その日の賃金が支払われませんし、それどころか査定や契約更新などに影響する可能性もあります。
ですから、かなり癪ではありますが、会社にしっかりと事情を説明して理解を得たうえで、無給での欠勤をするのがベストな選択になるのでしょう。
それでも会社が休ませてくれない
それでも会社が欠勤にウンと言わなければ……。
私見ですが、忌引きのような正当な理由があるのに、会社が欠勤を頑なに拒むことは、社会通念に照らして適切な行為だとは到底いえません。
いくら会社には労働者からの労務提供を受ける権利があるからといっても、労働者は会社のあらゆる命令に従わなければならないわけではないからです。
会社が「絶対に休ませない」と言って出勤を強要するのは労働者の人格権に一切の配慮がありませんので、そのような指揮命令は権利の濫用として不法行為に該当するものと私は考えます。
「この会社もブラック企業かもしれない」と考えるきっかけは、日常のちょっとしたところにも転がっています。
おかしいなと思ったことがあっても、会社という組織の中ではなかなか口には出しにくいものですが、そういうときに誰かに相談できる環境を整えておくことが、自分を守るためにも大切なことだといえます。
忌引きに関する職場のトラブルに見舞われたら弁護士へ相談を
忌引きという理由で休ませてくれないという事例のほかにも、職場トラブルで泣き寝入りするケースは少なくありません。
職場でのトラブルを早期解決するのであれば、労働トラブルに強い弁護士への相談も視野に入れてみましょう。
弁護士へ相談するにあたり、気になるのは弁護士費用の負担でしょう。
そこでおすすめしたいのが、弁護士保険です。
弁護士保険は、日常生活の個人的トラブルや事業活動の中で発生した法的トラブルに対し、弁護士を利用した時にかかる弁護士費用を補償する保険サービスです。
通常、弁護士を通してトラブルを解決しようとすると、数十万から数百万単位の弁護士費用がかかる場合があります。
弁護士保険に加入しておくことで、法的トラブルが発生した場合に弁護士に支払う費用を抑えられます。
職場におけるトラブルを早期解決するためには、弁護士保険を視野に入れましょう。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
・見たことがない就業規則に効力はない?周知義務や方法について解説!?
みなさんは、ご自身が所属している会社の就業規則を閲覧したことがありますか?入社時に少し見て以来閲覧したことがないという方がほとんどではないでしょうか?
普段仕事をする際には特に気にすることもないかもしれませんが、休暇や給与などをめぐって万が一会社と揉め事になった際、この就業規則が焦点になることはあります。
この記事では、就業規則がどういう条件下で効力を持つのかについて、主に周知義務やその方法に焦点を当ててご説明していきます。
寒波が訪れ、ぐっと寒くなってきましたね。寒くなるといつも、この短歌を思い出します。冬はなんとも人恋しい季節です。もしかしたら皆さんにも経験があるかもしれない「社内恋愛」について、今日は考えてみましょう。