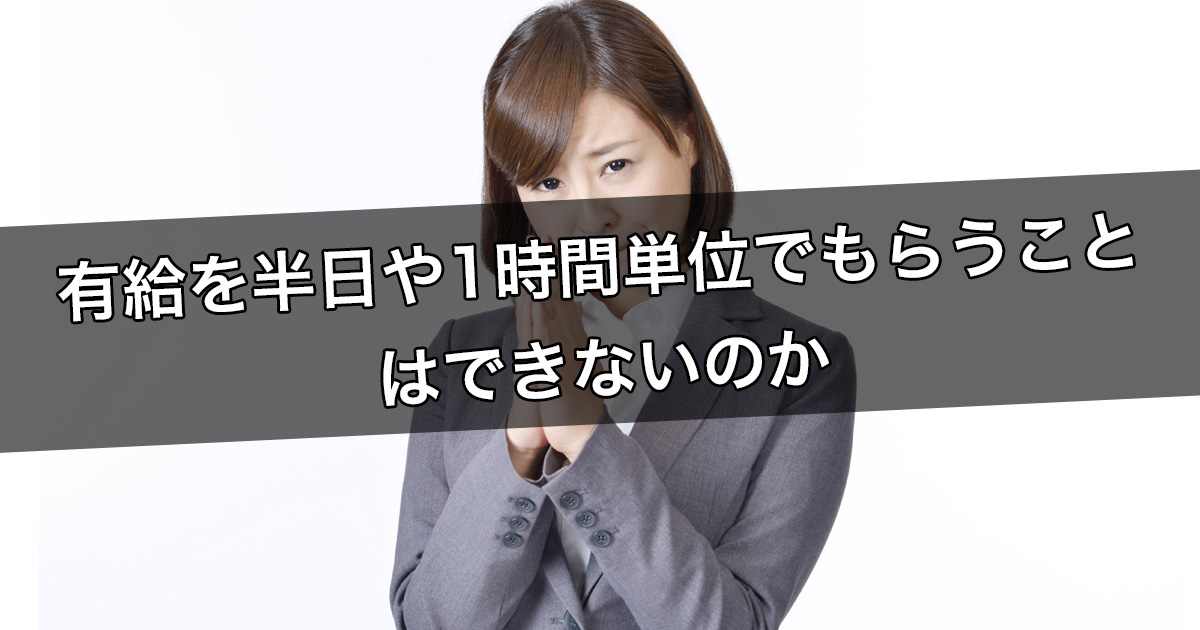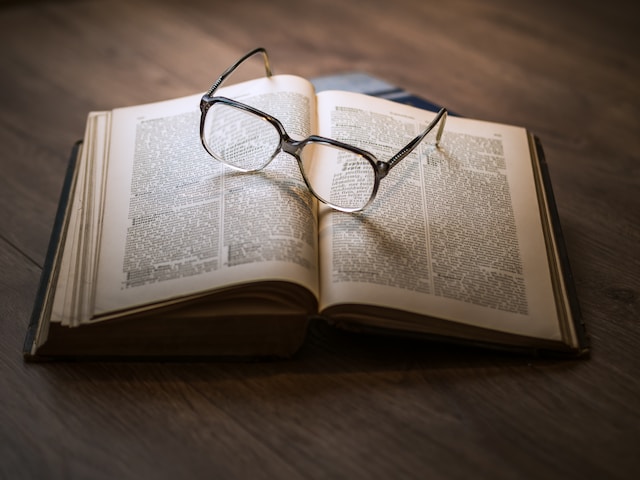コロナが流行する前ですが、少しお休みをいただいて、道東の阿寒湖温泉というところまで旅行してきました。
全国どこの観光地にも言えることですが、以前は、アジアからの観光客がとても多かったですよね。
札幌でも稼働率が連日90パーセントを超えるホテルが多かったそうで、出張のサラリーマンが部屋を押さえるのにも苦労するような状態だったとか。
また、そのような日常が戻るのが、待ち遠しいですね…
さて、今日は、観光には欠かせない「年次有給休暇」の、ちょっと変わった使い方について見ていきましょう。
記事の内容を動画でチェック
こんな疑問にお答えします
A.可能です。平成22年に労働基準法が改定され、時間単位での年次有給休暇が取得できるようになりました。事前に労使協定を締結することにより、年5日以内に限り時間を単位として年次有給休暇を与えることができると規定されています。また、半日単位の年次有給休暇については、この制度とは関係なく運用できます。
会社が半休(有給)を認めてくれない
皆さんが仕事をしているなかで、よく「半休」という言葉を耳にすることと思います。
午前中に病院に行きたいとか、午後から銀行や役所の用事を済ませたいとか、丸1日休むほどでもないけどちょっと会社を抜けたい、というニーズはあるものです。
そもそも半休とは何か?
半休とは、半日休暇の略を指します。法律で定められた従業員の権利で、リフレッシュを目的とします。
半休は、法に規定されていないため、必ずしも半休制度を設けるべきという義務はありません。
会社によって異なる半休制度
では、会社は労働者から半日単位で年次有給休暇をとりたいという申し出があった場合、これに応じなければならないのでしょうか。
この点、実は、会社には半日単位で付与する義務はないとされています。
日未満の単位での年次有給休暇(年休)を認めると、会社が使用目的を聞いて(それ自体違法ではありますが)、その所要時間に限ってしか休みを認めないという弊害が起こりえますし、そもそも、年次有給休暇の趣旨は心身のリフレッシュのためにあるのですから、原則として年次有給休暇は1労働日を単位としてとらせるものと考えるのが行政解釈となっています(昭63.3.14基発150号)。
ただし、この行政解釈は、単に半日単位で与える「義務がない」と述べているだけで、労働者が半日単位でとりたいいう申し出をしたときにそれを「認めてはいけない」と述べているのではありません(のちにそれを確認する内容の通達も出されています)。
そのため、法的には、「会社が許してくれさえすれば、半日単位で年次有給休暇をとることができる」という、何とも煮え切らない結論となります。
「半日」ってどれくらい?
ここで、突然ですがヒラガ問題です。
ある日、ヒラガは病院に行くため、午前に半休をとりました。
さて、この日、ヒラガは何時に出勤したでしょうか?
おそらく、答えは「13時」と「13時30分」のどちらかになったのではないでしょうか。
これは、法的にはどちらでも正解です。
先ほど述べたとおり、半休というもの自体、会社が認めてくれたらオールオッケーというファジーな制度ですので、半休の境目を昼休みとするか、それとも労働時間のちょうと半分の時刻とするかは、会社と労働者との間の取り決め次第となります(多くは就業規則で定められているものと思います)。
なお、私の事務所は半休の境目が昼休みなので、ヒラガ問題の正解は「13時」でした。
半休を午前にとると3時間半しか休めませんが、午後にとると4時間半休めますので、午後半休のほうが若干オトクな制度となっています。皆さんの会社はいかがでしょうか。
半休を取得するメリットとデメリット
半休の目的は、心身のリフレッシュだとお伝えしました。もう少し具体的に、半休を取得するメリットとデメリットを紹介します。
半休と取得するメリット
半休を取得するメリットは、従業員が柔軟に働ける環境が整い、ワークライフバランスの実現につながる点です。
例えば、夕方に家庭の用事があるとします。この場合、業務を丸一日休むことは難しいと悩む方もいるでしょう。
半休を取得することで丸一日休むというハードルは軽減され、午後からの用事に出向けるようになります。
働きやすい職場であることは、従業員の定着にもつながります。採用においても良い人材が集まり、人材確保も期待できるでしょう。
半休を取得するデメリット
半休制度のデメリットは、会社側の負担が増えることです。
半日分の給与計算や、休暇残数の管理など手間が生じやすくなります。
このような場合は、勤怠管理システムツールを利用することで管理負担が減るでしょう。
勤怠管理システムでは、給与計算や従業員の有給休暇の管理を自動化する機能が備わっています。
半休をとって残業したらどうなるの?
さて、またまたヒラガ問題。
今度はちょっと難問です。
さて、ヒラガは定時を超えて残業した2時間について、残業代をいくらもらえる(もらえない)のでしょうか?
なお、ヒラガは1時間あたり2000円の給料で働いているものとします。
答えは「もらえない」「4000円」「5000円」のどれかになりましたか?
それ以外になった方はもう一度計算しなおしていただきたいところですが、法的には「4000円」が正解です。
残業した2時間については、働いているのですから当然4000円分の給料は発生します。
あとは、労基法上の時間外割増賃金(25パーセント)も発生するかどうかがポイントになりますが、この割増賃金はあくまで「実労働時間」が8時間を超えたときにのみ発生します。
今回、ヒラガは13時から19時30分までの6時間半しか働いていないので、時間外割増賃金は発生しないことになるのです。
労使協定を締結すれば1時間単位で有給がとれる

わが国では年次有給休暇の取得率が5割前後という低い水準にあることが問題視されており、その有効活用が求められています。
また、先ほどもお話をしたとおり、労働者側としても年次有給休暇を細かく使いたいというニーズがあるところです。
そこで、平成22年に労働基準法が改定され、時間単位での年次有給休暇が取得できるようになりました。
改正労基法39条4項は、使用者は、事前に労使協定を締結することにより、年5日以内に限り時間を単位として年次有給休暇を与えることができる、と規定されています(なお、この労使協定とは、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定を指します)。
この改正で注意したいのは2点。
まずは、これまで述べてきた半日単位の年次有給休暇については、この制度とは関係なく運用できます。
つまり、労使協定を結ぶ必要もありませんし、「年5日以内」にもカウントされません。
そして、時間未満の単位での取得は認められていません(逆に「2時間」や「4時間」を単位にすることは可能です)。
会社も管理が大変ですし、年次有給休暇のもともとの趣旨からいえばあまり細切れにしすぎるべきではないという意識が働いたものともいえるのではないでしょうか。
そのような意味でも、この時間単位付与という制度はかなり特殊なものですので、会社としてはこの制度の運用に特別の注意を払う必要があるでしょう。
半休をめぐる労働トラブルが生じた際は弁護士へ相談してみよう
半休制度は、うまく活用すれば従業員のワークライフバランスを実現する方法のひとつになります。
ただ、半休を取得しても就業時刻を超えて残業をした際に、適切な残業代が支払われなかったというトラブルも少なくありません。
残業代の計算は会社によって細かな規定も多く、正確な金額を算出するためには労働基準法に通じていないと難しい場合もあります。
半休をめぐるトラブルが生じた場合は、労働問題に強い弁護士に相談してみてください。
弁護士への相談は、無料で行っているところがあります。おすすめの窓口は、こちらの記事で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事
-
-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
弁護士費用に不安をお持ちの方は、弁護士保険もおすすめです。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
弁護士保険の内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事
-
-
【2025年最新】弁護士保険の人気3社を徹底比較!補償内容や保険料、注意点を詳しく
「弁護士保険はいろいろあるけれど、何を基準に比較したらいいのか分からない」 弁護士保険に加入しようとしている方は、どこの保険会社を選んだらいいのか悩む方もいるでしょう。 本記事では、個人向けの弁護士保険を販売している人気 …
記事を振り返ってのQ&A
Q.会社が半休(有給)を認めてくれません。これって違法ですか?
A.会社には、半日単位で休暇を付与する義務はないとされています。ただ、労働者が半日単位でとりたいいう申し出をしたときにそれを「認めてはいけない」と述べているのではありません。法的には、「会社が許してくれさえすれば、半日単位で年次有給休暇をとることができる」という結論となります。
Q.半休が示す半日は、具体的に決まっていますか?
A.半休というもの自体、会社が認めさえすれば、何時からでもOKです。半休の境目を昼休みとするか、それとも労働時間のちょうど半分の時刻とするかは、会社と労働者との間の取り決め次第となります。
Q.半休をとって残業したら残業代はもらえるの?
A.残業として働いた分は、法的には残業代がもらえます。ただ、労基法上の時間外割増賃金(25パーセント)も発生するかどうかがポイントになりますが、この割増賃金はあくまで「実労働時間」が8時間を超えたときにのみ発生します。