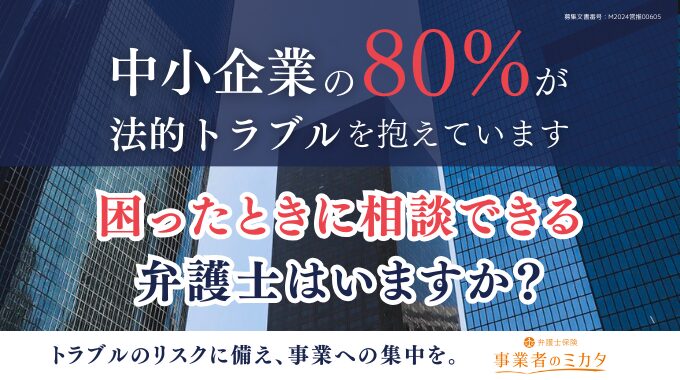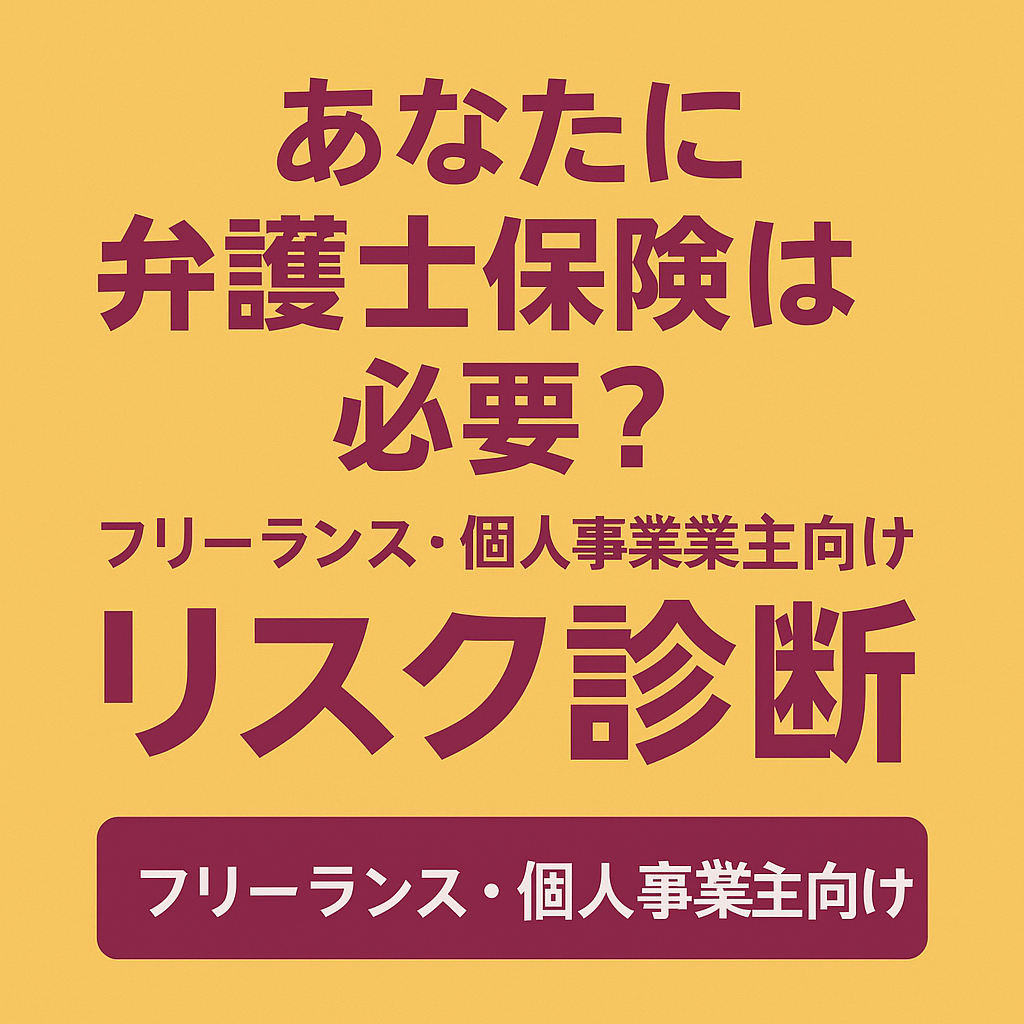個人事業主(フリーランス)として働く人が増える中、トラブルに遭遇するケースが増えてきています。
とはいえ、いざトラブルに遭遇してしまうと「どこに相談したらいいの?」「相談したらいくらかかるんだろう?」と悩みを抱える方は少なくないでしょう。
そこで本記事では、個人事業主(フリーランス)のトラブルに応じた相談先を紹介します。無料で利用できる窓口もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
こんな疑問にお答えします
A.代表的な相談窓口として、以下を利用できます。
- フリーランス・トラブル110番
- 公益財団法人日本税務研究センター
- 下請かけこみ寺
- よろず支援拠点
- 弁護士
個人事業主(フリーランス)が安心して事業を行うためには、気軽に相談できる体制をつくることが重要です。
個人事業主(フリーランス)が抱えるトラブルの状況
個人事業主(フリーランス)が仕事上のトラブルに直面する割合は、年々増加傾向にあるといわれています。
厚生労働省の委託事業である「フリーランス・トラブル110番」の調査(※)によると、2022年に相談を受けた件数は6,884件。月平均にすると約570件ものトラブルが発生している状況です。
相談内容でもっとも多いのは「報酬の支払い」に関するトラブルで、報酬の全額不払いや支払遅延、一方的減額などが含まれます。
(※)参考:フリーランス・トラブル110番について
個人事業主(フリーランス)はなぜトラブルに巻き込まれやすいのか
なぜ、このような状況が起きているのでしょうか。
個人事業主(フリーランス)がトラブルに巻き込まれやすい理由のひとつに「雇用者としての立場が弱いから」というものが挙げられます。
個人が仕事を得るには、企業や他の個人事業主(フリーランス)、もしくは一般消費者から仕事を得るというパターンが多いでしょう。
しかし、相手が企業の場合は、こちらが下請け側になることが一般的。雇用者としての立場は弱くなりやすく、発注者に対して対等な立場で対応することが難しい場合があります。
トラブルが発生した際に自ら交渉しようとしても、仕事を失うリスクを考えると強く主張できず、泣き寝入せざるを得ないという状況になることが少なくありません。
ここで、個人事業主(フリーランス)の立場を保護する法律はないのか?という疑問が浮かびます。
個人事業主(フリーランス)に関する法律については、下請法や独占禁止法があります。2023年には、新たに「フリーランス保護新法」が成立しました。
しかし、法制度が整い始めているとはいえ、個人事業主(フリーランス)はまだまだ不利な立場にあるという現状なのです。
フリーランス保護新法については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧くださいね。
関連記事
-
-
フリーランス保護新法とは?発注者に求められる実務対応をわかりやすく解説
フリーランスの権利を守る法律として、2023年4月28日に成立した「フリーランス保護新法」。個人で事業を営む事業者が、安定して仕事に取り組めるよう環境を整える目的があります。 フリーランス保護新法の施行開始に向けて、どう …
個人事業主(フリーランス)が直面しやすいトラブル内容
ここからは、個人事業主(フリーランス)がどのようなトラブルに直面しやすいのか具体的にみていきましょう。
報酬に関すること
個人事業主(フリーランス)がもっとも直面しやすい代表的なトラブルが、報酬に関するものです。「フリーランス・トラブル110番」の調査結果においても、報酬の支払いトラブルが全体の3割弱を占めるほど、多くの方が巻き込まれやすい傾向があります。
報酬に関するトラブル事例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 報酬の未払い
- 支払い遅延
- 一方的な減額
報酬未払いや一方的な減額に関しては「納品が遅れた」「期待通りの成果ではなかった」などの理由で、発注者から不当な扱いを受けるケースが少なくありません。
ほかにも、発注者の資金繰りを理由に報酬の支払いが遅れているといったケースもあります。
これらのトラブルを防ぐためには、報酬の支払方法や納期、成果物の範囲などを明確に定めておくことが重要といえるでしょう。
契約書に関すること
契約書に関することも、個人事業主(フリーランス)が直面しやすいトラブルです。
具体的なトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 契約内容の不備
- 契約書に関する解釈の違い
契約書に「報酬の支払方法」や「納期」などが明確に定められていない場合、発注者との間で認識の違いが生じやすくなります。記載されていない状況に陥ると、どうしても立場が強い側の主張が通りやすくなってしまうという傾向があるでしょう。
契約書に関するトラブルに巻き込まれないためには、発注者との間で十分に話し、双方が納得したうえで契約を締結することが重要です。
取引先からの過度な要求
取引先からの過度な要求も、個人事業主(フリーランス)が抱えやすい悩みのひとつです。
具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 契約内容を超えた業務の追加
- 無理矢理な納期の短縮
- 一方的な報酬の減額
- 突然の契約解除
双方が納得する形であれば、契約書にない業務の追加については問題ありません。しかし、明らかに強制的といえる過度な要求に対しては、断る勇気を持つことも大切です。
ハラスメント(パワハラ・セクハラ)
パワハラやセクハラなどのハラスメントも、個人事業主(フリーランス)が受けやすい被害のひとつ。ハラスメントと聞くとどうしても会社内の話をイメージするかもしれませんが、個人事業主(フリーランス)も被害を受ける可能性が十分にあり得るのです。
「フリーランス・トラブル110番」に寄せられるトラブル内容によると、ハラスメントに関する相談件数は全体の5.3%を占めています。
具体的な事例としては、以下が挙げられます。
- 精神的な攻撃(脅迫や名誉棄損、侮辱、暴言等)
- 過大な要求
- 容姿に対するからかい
- 無視
- プライベートの詮索
- 卑猥な話や質問を持ちかける
個人事業主(フリーランス)は、個人で業務を請け負っている方が多いため、取引先と対等な関係が築きにくく主従関係になってしまいがちです。
ハラスメント被害を放置してしまうことで、精神的に大きなダメージを負いかねません。
ひとりで悩まずに、弁護士やフリーランス支援団体などに相談するようにしてみてください。
損害賠償請求に関すること
個人事業主(フリーランス)側の不注意で、著作権侵害や情報漏洩が発生し取引先に損害が生じた場合は、損害賠償を請求されることがあります。
損害賠償請求をされるケースとして、次の行為が挙げられます。
- 取引先の情報を無断で公開した
- 納品した成果物が他人の著作権を侵害していた
- 納品した成果物が他人の社会的評価を傷つけるものだった
上記のような場合、取引先から責任を課されることは決して珍しくはありません。問題がエスカレートしないためにも、「契約書に明確な禁止行為が記載されているか?」「本当に法律違反に該当するかどうか?」を、専門知識を持って判断する必要があるでしょう。
法的な問題が絡んでくると、ひとりで解決することは非常に困難なもの。悩んだ場合は、専門家に相談することをおすすめします。
個人事業主(フリーランス)におすすめ4つの相談窓口(無料もあり)
個人事業主(フリーランス)がトラブルに巻き込まれてしまった際は、ご自身や事業を守るためにも適切に対処しなければなりません。
ここからは、個人事業主(フリーランス)が利用できる相談窓口を4つご紹介します。
フリーランス・トラブル110番
まず最初に利用したいのが、「フリーランス・トラブル110番」です。
「フリーランス・トラブル110番」は、厚生労働省の委託事業で運営され、個人事業を営む方の事業上のトラブルを無料で相談できる窓口です。
個人事業に関する法律問題に詳しい弁護士が相談を受け、解決に向けたアドバイスやサポートを行ってくれます。
相談方法は、電話・メール・対面・オンライン通話が可能です。匿名でも構いません。
トラブルの内容によっては、担当者が当事者の間に入って和解を進めてくれることもあります。何らかのトラブルが起きたら、まずは問い合わせてみるといいでしょう。
公益財団法人日本税務研究センター
公益財団法人日本税務研究センターは、個人事業主(フリーランス)が利用できる相談窓口です。
税理士会が運営しており、税に関する疑問や悩みを相談することができます。
個人事業主(フリーランス)にとって、税に関するトラブルが起きやすいのは財務処理や確定申告のときでしょう。
同センターでは、税に関する講座やセミナーを開催しているため、参加することで税に関する知識や手続きの方法を身に付けることができます。
税務相談の利用に関しては、公益財団法人日本税務研究センターのホームページから行ってみてください。
下請かけこみ寺
下請かけこみ寺は、中小企業庁の委託事業として全国48か所に設置されている個人事業主(フリーランス)が利用できる相談窓口です。
下請取引の適正化を推進することを目的としており、下請事業者の取引上の悩み相談や企業間取引、下請代金法などに詳しい相談員や弁護士が応じてくれます。
相談、和解に向けての手続きは無料。必要に応じて、行政や専門機関への連携も行ってくれます。
相談方法は、電話・オンライン・対面のいずれでも可能です。相談者の情報や内容が表に出ることはありません。
トラブルに巻き込まれた際は、下請かけこみ寺に相談してみるといいでしょう。
よろず支援拠点
よろず支援拠点は、全国47都道府県に設置されている経営相談窓口です。
中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者の方、これから起業予定の方に向けたあらゆる悩みに対応してくれます。
各拠点には経営に関する専門家が在籍しており、相談内容に応じて経営計画の策定やマーケティング、財務、人材育成など、さまざまなアドバイスやサポートを受けられます。
利用料金は無料で、何度でも相談できます。
必要に応じて、行政や専門機関への連携も行ってくれるため、個人経営の方にとって心強い味方となるでしょう。
弁護士
弁護士もまた、個人事業主(フリーランス)がトラブルに巻き込まれた際の強いサポーターになってくれます。
個人事業主(フリーランス)は、権利侵害やハラスメントといった一人では解決できそうにないトラブルが起きる可能性があります。中には、裁判に発展してしまうケースも珍しくありません。
法律上の判断が必要な場合や裁判を検討する場合は、弁護士に相談することでより有利な条件で解決に導ける可能性が高くなります。
弁護士に相談する際は、労働トラブルに強い弁護士に相談するようにしましょう。法律事務所によっては、初回相談を無料で行っているところもあるため、まずは相談だけでも行ってみることをおすすめします。
弁護士に相談できる窓口は、こちらの記事でまとめています。
関連記事
-
-
弁護士の無料相談のおすすめの窓口は?対応できる範囲や事前準備を解説!
離婚や相続、労働問題や交通事故など、トラブルに巻き込まれることは少なくありません。 そんなときにおすすめなのが、弁護士への無料相談です。 弁護士へ無料相談することで、トラブルの全体的な見通しや解決策のアドバイスを受けられ …
トラブルを早期解決するなら弁護士への相談が有効?
個人で相談できる窓口はいくつかありますが、中でも弁護士に相談することは非常に有益であるといえます。
弁護士と聞くと、訴訟や慰謝料請求といったイメージが強いかもしれません。しかし、事業上のどのような小さな困りごとや疑問点でも、気軽に相談できる存在なのです。
労務トラブルや不当なクレームが発生した場合に自ら解決するよりも、弁護士へ委任した方が早期解決を図れるようになるでしょう。
個人事業主(フリーランス)が弁護士に相談するメリット
個人事業主(フリーランス)が弁護士に相談するメリットには、以下のものが挙げられます。
- 法律上の判断を適切に行うことができる
- 取引先との交渉を有利に進めることができる
- 裁判を起こすための準備や手続きをサポートしてくれる
- トラブルを未然に防ぐアドバイスにのってくれる
個人事業主(フリーランス)として仕事をするうえで、法的対処が必要になることがあるでしょう。
たとえば、成果物の権利侵害やハラスメント、損害賠償請求など、法律上の判断が必要なトラブルが発生した場合です。
法的措置を個人で進めるのは難しく、法律のプロである弁護士のサポートは欠かせません。
取引先との交渉が難しい場合でも、弁護士に代理交渉を依頼することで相談者の立場を守りながら解決に導ける可能性があります。
もちろん、弁護士に相談しなくても解決できるケースもありますが、それなりの時間と労力を要してしまいます。弁護士に一任することで、事業をストップすることなく解決を進められます。
顧問弁護士に依頼するという選択肢もある
弁護士へ依頼するという点でいうと、個人事業主(フリーランス)は顧問弁護士に依頼するという選択肢もあります。
顧問弁護士とは、事業上で直面する法的な問題やリスクに備えて日頃から継続的に相談に乗ってくれる弁護士のこと。契約書の作成やリーガルチェック、社内の人事労務の問題や顧客とのトラブルにも対応してくれます。
顧問弁護士と聞くと、企業のサポートをするというイメージが強いかもしれません。しかし、個人であっても依頼することができます。
一般的な弁護士と異なる点は、顧問弁護士は継続して関わることから日頃の相談をしやすいことです。毎月の顧問料は発生しますが、日常的なコンサルや法的書類のチェックを希望する場合は顧問弁護士をつけた方が安心といえるでしょう。
大きなトラブルになる前にサポートしてほしいという方は、顧問弁護士の利用を検討してみてもいいかもしれませんね。
顧問弁護士と弁護士の違いや選ぶ際の基準については、こちらの記事でまとめています。
関連記事
-
-
顧問弁護士と弁護士の違いって?顧問弁護士を選ぶ際のおすすめの基準は何?
企業の運営において、『顧問弁護士』を活用するケースが増えています。 『顧問弁護士』とは、企業の顧問として法務関係のアドバイスを行う弁護士のことで、法的トラブルの対処や業務に潜んでいるリスクを未然に防いでもらうことができま …
顧問弁護士の費用相場は?
顧問弁護士の費用相場は、月に3〜5万円といわれています。年間にすると36万〜60万円程度を考えていいでしょう。
ただ、上記の費用はあくまで相場であるため、顧問内容によっては高くなる可能性があります。
顧問弁護士に依頼する際は、自社の目的や予算に合ったサービスを依頼しましょう。
顧問弁護士のメリットや具体的な費用相場に関しては、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。
関連記事
-
-
中小企業の法務は顧問弁護士に依頼すべき?具体的なメリットや費用相場を解説!
中小企業では、法律トラブルが発生する可能性は決して低くはありません。 自社の法務を顧問弁護士に依頼しようか検討している方もいらっしゃるでしょう。 とはいえ、顧問弁護士と聞くと、「毎月いくらかかる?」「依頼しない場合は、ど …
弁護士に気軽に相談できる体制を整備しよう
個人事業を営む方にとって、法的リスクは避けたいものです。しかし、普段からいくら気をつけていてもトラブルが発生する可能性はゼロではありません。
顧問弁護士を利用するにしても、月に数万円はかかってしまいます。
トラブルが生じたときの備えとしてお得に安心を得たいという方は、法人・事業者向けの弁護士保険の利用がおすすめです。
法人・事業者向けの弁護士保険とは、事業者が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用や裁判費用を補償してくれるサービスのこと。いざというときの費用負担を大幅に軽減してくれます。
事業者が抱えるリスクは多岐に渡ります。事業の安定を図るためにも、弁護士保険を視野にいれてみてくださいね。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
まとめ:万一のトラブルに対応できる体制を整えておこう
個人事業主(フリーランス)のトラブルにはさまざまな側面がありますが、まずは専門家が在籍する窓口に相談することで解決への第一歩を踏み出せます。
ご自身の立場や事業を守るためにも、万一の備えをもっておくことは非常に大切です。
今後の備えとしてトラブル発生時の費用負担を抑えたい場合は、弁護士保険も有効に活用していきましょう。
記事を振り返ってのQ&A
A.巻き込まれやすいトラブルとして、契約書・報酬に関することや取引先からの過度な要求、ハラスメントがあります。また、下請け側の不注意によって損害賠償を請求される可能性もあります。
Q.個人事業主(フリーランス)がトラブルに巻き込まれたらどこに相談したらいいですか?
A.代表的な相談窓口として、以下を利用できます。
フリーランス・トラブル110番
公益財団法人日本税務研究センター
下請かけこみ寺
よろず支援拠点
弁護士
Q.早期解決を目指すなら弁護士への相談が有効ですか?
A.起きてしまったトラブルを解決するには、弁護士に相談することでスムーズな解決を目指せるといえます。また、普段の業務からサポートしてほしいという場合は、顧問弁護士の利用を検討してみてもいいかもしれません。
Q.トラブルが起きたときに費用負担を抑える方法はありますか?
A.無料で利用できる窓口であれば、無料相談が可能です。今後の備えとして費用対効果を図るのであれば、いつでも弁護士へ依頼できる弁護士保険を利用しておくといいでしょう。