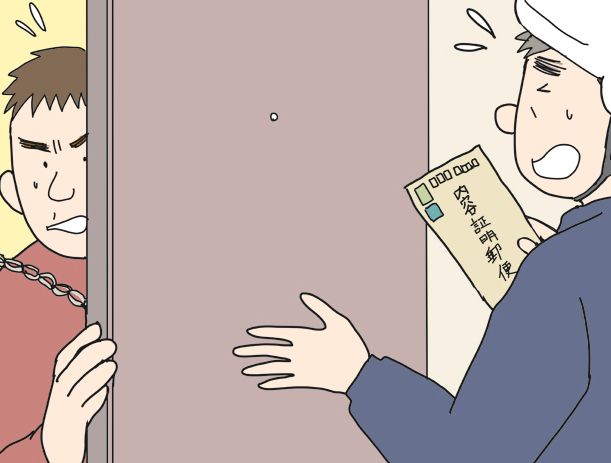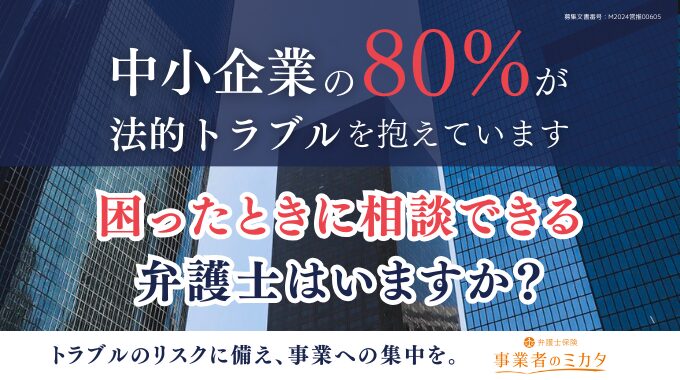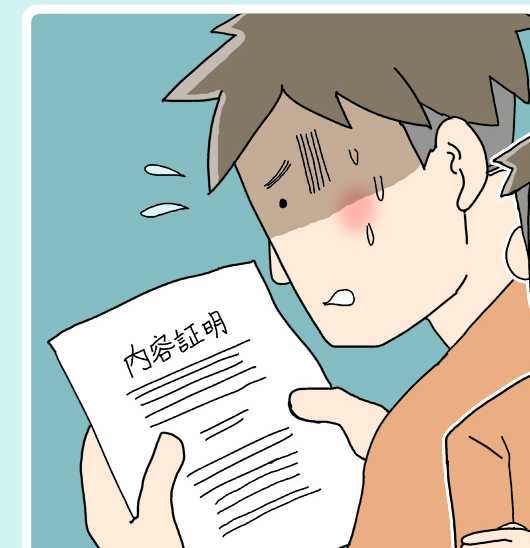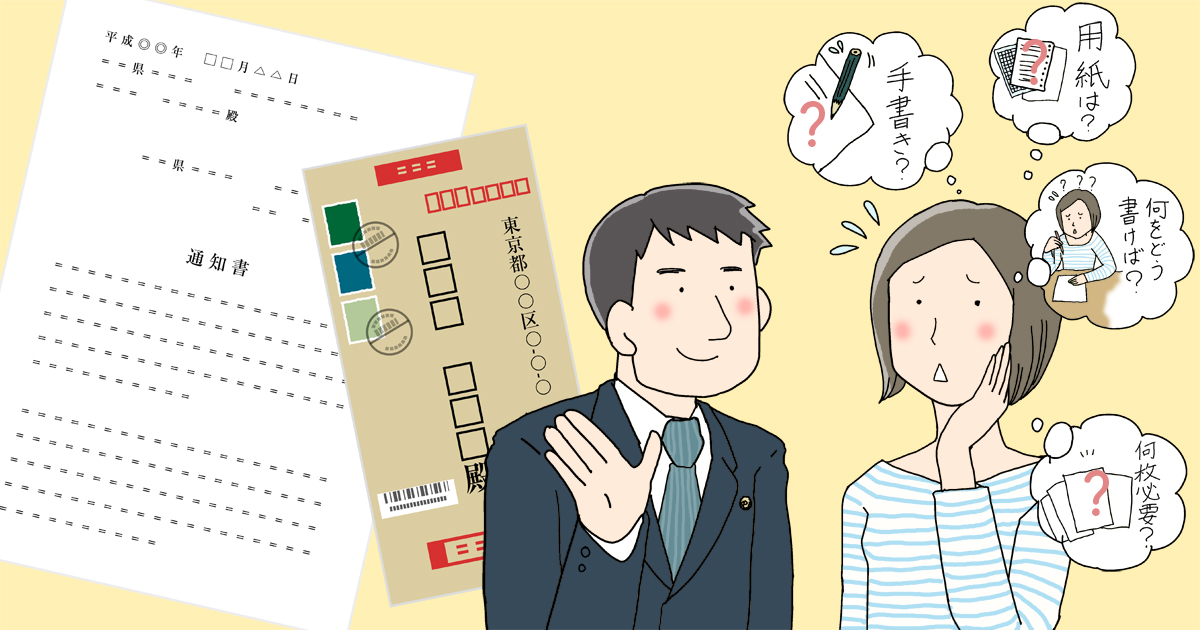内容証明は、書留郵便(※)で郵送されますが、送った相手方が受け取りを拒否した場合、どうしたらよいのでしょうか?受け取りを強制することはできるのでしょうか?
今回は、内容証明を受け取り拒否された場合の法的効果や対策法について解説します。
※)書留郵便とは、配達までの郵便物等の配達過程を記録しているサービスのことです。内容が証明できたとしても、その文書が配達されたことも証明できなければ意味がないため、一般書留郵便物等を配達した事実を証明する「配達証明」のサービスを併せて利用するのが一般的です。
記事の内容を動画でチェック
こんな疑問にお答えします
A:「弁護士保険の教科書」編集部
相手方の返事が不要なケースでは、内容証明によって「こちらの意思を伝えること」が主な目的である場合は、次なる手段を検討する必要はありません。
返事が必要なケースでは、以下の3つを検討する必要があります。
- 弁護士名で新しい内容証明を送付する
- 勤務先宛てに内容証明を送付する
- 訴訟を提起する
※弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
内容証明郵便とは
まず、内容証明郵便とは何かを確認しておきましょう。
内容証明郵便とは、郵便物の内容文書を郵便局にて保管し、証明するサービスです。具体的には、「誰が」「誰に」「どのような内容で」「いつ送付したのか」を証明できます。
主に、裁判が必要になりそうな証拠として活用されます。
自分の主張を記載した文書が客観的に示されるため、「そんな郵便は届いていない」「そんな文書は書かれていなかった」という言い逃れを防止する効果があります。
関連記事
-
-
【弁護士に任せる?自分でできる?】内容証明郵便の出し方と費用
契約の取り消し、金銭の請求などの、自分の意思を伝えたことを証明したいとき。または、パワハラセクハラ、配偶者の不貞行為などの、被害事実を主張したことを証明したいとき。このようなトラブルに巻き込まれた場合は、内容証明郵便を使 …
内容証明の受け取り拒否対策①そもそも「受け取り拒否」とはどういうことか?
内容証明は、郵便局の配達員によって相手方の手元に直接届けられます。
郵便局の配達員は、内容証明を手渡す際に、受取人から受領印かサインをもらいます。
このとき、相手方が「これは自分宛ての郵便ではない」「サインはしない」などと言った場合、配達員は内容証明を渡すことはできません。
相手方が受け取りを拒否する姿勢を示した以上、配達員が受け取りを強制することはできないからです。
相手方が受け取りを拒否した場合、配達員は内容証明を持ち帰り、差出人の元に返送します。
このとき、「◯月◯日に受け取りを拒否した」というメモ書きが付いていることがあります。
相手方が居留守を使って受け取りを拒否した場合も、同様の流れとなります。
相手方が玄関まで出てこない以上、配達員が勝手に内容証明を置いて帰ることはできません。
居留守を使われたケースでは、配達員は「不在通知」を投函して、内容証明を持ち帰ります。
内容証明は、その後7日間は郵便局で保管されます。
その間に相手方から連絡が来なければ、内容証明は差出人に返送されます。
このとき、メモ書きには「相手方不在」や「留置期間経過」などと書かれます。
内容証明の受け取り拒否対策②相手方が受け取らないのはどういう場合か?
内容証明は、封筒に入れたままの状態で相手方に届けられます。
つまり、相手方は受け取る前に内容を知ることはできません。
自分にとって不利なことが書かれているかどうかは分からないため、一般的には、内容証明が受け取り拒否されるケースは多くはありません。
しかし、例えば離婚の話し合いで揉めている夫婦の場合は、相手方から内容証明が届くと、「この手紙には離婚に関することが書かれているのだろう」「受け取ると不利になるかもしれない」と予想することができます。
このような場合は、相手方が受け取りを拒否する可能性が高くなります。
また、日頃からクーリングオフの通知をたくさん受け取っているような問題のある会社の場合、「この内容証明はクーリングオフに違いない」と推測して、一律に受け取りを拒否することがあります。
内容証明の受け取り拒否対策③受け取らない場合も言い逃れはできない?
相手方が受け取りを拒否した場合、相手方は「そのような手紙は知らない」と言い訳をすることができるのでしょうか?
相手方の意志で受け取りを拒否したにも関わらず、このような言い逃れをすることは許されるのでしょうか?
この点について、最高裁判所が判断を示したケースがあります。
このケースでは、相続のトラブルに関する内容証明を、相手方が居留守を使って受け取りを拒否しました。
この受け取り拒否の法的効果について、裁判所は下記のように判断しました。
この判決を分かりやすくまとめると、「相続のトラブルに関する大事な書類であると分かっていたのに、自分の意志であえて受け取らなかったのだから、法的には『その手紙は届いたもの』と同視することができる」ということです。
つまり、相手方が「そのような手紙は知らない」と言い逃れをすることは許されないということです。
内容証明の受け取り拒否対策④言い逃れを防ぐ2つの条件
裁判所の判決によると、相手方は「手紙は届いていない」と言い逃れをすることはできません。
しかし、判決の内容をよく読むと、2つの条件が付いています。
(1)相手方がさしたる労力を伴うことなく内容証明を受け取ることができたこと
この判決では、「相手方が受け取ろうと思えばいつでも受け取ることができたのに、あえて受け取らなかった場合」という条件が付いています。
例えば、相手方がケガや病気で入院している場合は、簡単に受け取ることはできません。
このような場合は、この判決のルールは適用されません。
他にも、相手方が長期で他県に出張している場合や、海外旅行に出かけている場合などは、「容易に受け取ることができた」とはいえないので、この判決のルールは当てはまりません。
(2)相手方が手紙の内容を推測することができたこと
上記の判決では、「相手方が内容証明の中身を十分に予想できた場合」という条件が付いています。
内容証明は、一般の人には馴染みのある郵便物ではありません。
そのため、大事な書類であると気が付かず、うっかりして受け取りをしないという人も中にはいます。
このため、相手方が内容証明に大事なことが書かれていることに気が付かず、うっかり受け取りをしなかった場合については、上記の判決のルールは当てはまりません。
例えば、何年間も音信不通の親戚のケースでは、突然内容証明が届いたとしても、何が書かれているのかを予想することはできません。
特に、一度も会ったことがない親戚である場合は、差出人の名前を見ても、親戚ということにすら気が付かないかもしれません。
このような場合は、相手方が受け取りを拒否しても、上記の判決のルールが適用されることはありません。
反対に、何ヶ月も前から離婚について話し合いを重ねている夫婦間のケースでは、内容証明が届いた場合に、「この手紙には慰謝料や親権について大事なことが書かれているだろう」と推測することができます。
このような場合は、相手方が受け取りを拒否すると「そのような手紙は知らない」と言い逃れをすることができなくなります。
内容証明の受け取り拒否対策⑤受け取り拒否された場合の対策法
内容証明の受け取りを拒否されたとしても、上記の判決によれば、相手方は「受け取っていない」と言い訳をすることはできなくなります。
それでは、内容証明を受け取りを拒否されたとしても、何もしなくてよいのでしょうか?
それとも、次なる手段を検討しなければいけないのでしょうか?
以下では、トラブルの種類別に対応策を紹介します。
相手方の返事が不要なケース
内容証明によって「こちらの意思を伝えること」が主な目的である場合は、次なる手段を検討する必要はありません。
上記で紹介した判決の2つの条件を満たしていれば、法的には「手紙は届いたもの」と同視することができるからです。
例えば、時効援用通知を内容証明で送る場合は、「時効を援用するのでお金は支払いません」というこちらの意思を伝えることが主要な目的です。
このようなケースでは、相手方が実際に内容証明の中身を読んでいないとしても、「手紙は相手方に到達した」と裁判所で認めてもらうことができます。
よって、相手方が内容証明を受け取り拒否したとしても、心配する必要はありません。
実際にこちらの意思が伝わっていないとしても、法的には手紙は届いたものと認定されます。
相手方からの返事が必要なケース
相手方からの返事が必要なケースでは、次なる手段を検討しなければいけません。
相手方からの返事が必要なケースとは、相手方からのアクションが必要となるケースのことです。
例えば、借金の返済を催告する場合は、相手方に金銭を振り込んでもらうことが必要となります。
内容証明によって借金の返済を催告した場合、相手方に金銭を振り込んでもらわなければトラブルは解決しません。
このように、相手方が何らかのアクションを取ることが必要となるケースでは、相手方が内容証明を受け取らない以上、いつまで経っても解決の方向に進むことはありません。
トラブルの種類によって対応策は様々ですが、下記に3つの対処法を紹介します。
①弁護士名で新しい内容証明を送付する
第一に、自分の名義で送付した内容証明を拒否された場合は、「弁護士名で新しい内容証明を送付する」という方法があります。
一般の方からの内容証明を受け取らない人であっても、弁護士の名前で内容証明が届いた場合は、「何か重要なことが書かれているかもしれない」「これを受け取らないと裁判沙汰になるかもしれない」と考えて、内容証明を受け取ることがあります。
弁護士に内容証明の作成を依頼した場合の費用については、以下の記事にてご確認下さい。
関連記事
-
-
【弁護士に任せる?自分でできる?】内容証明郵便の出し方と費用
契約の取り消し、金銭の請求などの、自分の意思を伝えたことを証明したいとき。または、パワハラセクハラ、配偶者の不貞行為などの、被害事実を主張したことを証明したいとき。このようなトラブルに巻き込まれた場合は、内容証明郵便を使 …
②勤務先宛てに内容証明を送付する
第二に、自宅宛ての内容証明の受け取りを拒否された場合は、「勤務先宛てに内容証明を送付する」という方法があります。
勤務先であれば、受け付けの方が受領したうえで、本人に手渡してくれることがあります。
また、勤務先では周囲の目が気になるため、何も言わずに本人が受け取りをするという可能性もあります。
③訴訟を提起する
第三に、上記の方法によっても内容証明を受け取らない相手方に対しては、「訴訟を提起する」という方法があります。
特に、慰謝料や借金返済などの金銭を請求するケースでは、早期に訴訟を提起することが得策です。
内容証明にこだわっているうちに長期間が経過してしまうと、消滅時効によって金銭を請求することができなくなるリスクがあるからです。
内容証明は、あくまで手紙の一種です。相手方から強制的に金銭を徴収する手段ではありません。
相手方が内容証明の受け取りを拒否する以上、自発的に金銭を支払ってくれる可能性は低いといえます。
このようなケースでは、弁護士に相談して訴訟や支払督促などの法的手段を取ることが必要となります。
裁判によって相手方の支払い義務が確定されれば、強制執行によって相手方の財産を差押えをすることができます。
相手方が頑なに内容証明を受け取らない場合は、弁護士にご相談して訴訟や支払督促などの法的手段を検討しましょう。
内容証明郵便の拒否に対する適切な手段は弁護士へ相談しよう
内容証明を受け取り拒否された場合でも、最高裁判所が示す2つの条件を充たしていれば、法的には「手紙は到達した」と認められます。
この場合、相手方は「手紙は受け取っていない」と言い逃れすることはできなくなります。
ただし、相手方のアクションが必要なケースでは、次なる手段を検討することが必要です。
訴訟や支払督促などの法的手段が必要となりますので、内容証明の受け取り拒否でお悩みの方は弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談する場合には、弁護士保険がおすすめです。保険が弁護士費用の負担をしてくれるので助かります。
弁護士保険なら11年連続No.1、『弁護士保険ミカタ』
弁護士保険なら、ミカタ少額保険株式会社が提供している『弁護士保険ミカタ』がおすすめです。1日98円〜の保険料で、通算1000万円までの弁護士費用を補償。幅広い法律トラブルに対応してくれます。
経営者・個人事業主の方は、事業者のための弁護士保険『事業者のミカタ』をご覧ください。顧問弁護士がいなくても、1日155円〜の保険料で弁護士をミカタにできます。
また、法人・個人事業主の方には、法人・個人事業主向けの弁護士保険がおすすめです。
経営者・個人事業主には『事業者のミカタ』がおすすめ!
『事業者のミカタ』は、ミカタ少額保険株式会社が提供する、事業者の方が法的トラブルに遭遇した際の弁護士費用を補償する保険です。
個人事業主や中小企業は大手企業と違い、顧問弁護士がいないことがほとんど。法的トラブルや理不尽な問題が起きたとしても、弁護士に相談しにくい状況です。いざ相談したいと思っても、その分野に詳しく信頼できる弁護士を探すのにも大きな時間と労力を要します。
そんな時、事業者のミカタなら、1日155円~の保険料で、弁護士を味方にできます!
月々5,000円代からの選べるプランで、法律相談から、事件解決へ向けて弁護士へ事務処理を依頼する際の費用までを補償することが可能です。
内容証明に関する関連記事
-
-
【弁護士に任せる?自分でできる?】内容証明郵便の出し方と費用
契約の取り消し、金銭の請求などの、自分の意思を伝えたことを証明したいとき。または、パワハラセクハラ、配偶者の不貞行為などの、被害事実を主張したことを証明したいとき。このようなトラブルに巻き込まれた場合は、内容証明郵便を使 …
-
-
内容証明を無視したら?されたら?次の手は?内容証明の効力・効果を弁護士が解説!(弁護士執筆記事)
ある日突然、内容証明郵便が届いた場合、どうしたら良いのでしょうか? 内容証明は、無視しても良いものなのでしょうか?もし無視した場合、どうなるのでしょうか? 今回の記事では、「内容証明を無視したらどうなるのか」について、内 …
-
-
内容証明郵便の書き方と出し方のルール【文例テンプレート付き】
内容証明郵便は、明確な証拠を残したい場合など、トラブルの予防や解決において、とても有効な手段となることがあります。 われわれ弁護士も、相談者のトラブルの予防や解決のために動き出す時、内容証明郵便の作成から始めることが多い …
-
-
【テンプレート付き】電子内容証明郵便(e内容証明)の書式とメリット・デメリット
紛争の相手方に対して請求書を送ったり、時効援用通知や遺留分減殺請求書を送ったりするとき「内容証明郵便」が非常に役立ちます。 中でも「電子内容証明郵便(e内容証明)」を利用すると、わざわざ郵便局に行かなくて済みますし、厳格 …
ケース別内容証明のテンプレート集
記事を振り返ってのQ&A
Q:そもそも「受け取り拒否」ってどういうこと?
A:内容証明は、郵便局の配達員によって相手方の手元に直接届けられます。郵便局の配達員は、内容証明を手渡す際に、受取人から受領印かサインをもらいます。このとき、相手方が「これは自分宛ての郵便ではない」「サインはしない」などと言った場合、配達員は内容証明を渡すことはできません。
Q:内容証明の受け取り拒否の言い逃れに使用される条件は?
A:基本的には、裁判所の判決によると、相手方は「手紙は届いていない」と言い逃れをすることはできません。ただし、「相手方が受け取ろうと思えばいつでも受け取ることができたのに、あえて受け取らなかった場合」という条件が付いています。例えば、相手方がケガや病気で入院している場合は、簡単に受け取ることはできません。このような場合は、この判決のルールは適用されません。また、相手方が内容証明に大事なことが書かれていることに気が付かず、うっかり受け取りをしなかった場合については、上記の判決のルールは当てはまりません。
Q:受け取り拒否された場合、何をすると良いですか?
A:内容証明によって「こちらの意思を伝えること」が主な目的である場合は、次なる手段を検討する必要はありません。相手方から返事が必要な場合には、①弁護士名で新しい内容証明を送付する、②勤務先宛てに内容証明を送付する、③訴訟を提起するという手段が取りえます。
弁護士費用や訴訟費用に関する関連記事
-
-
訴状を無視して裁判も欠席するとどうなるのか
ある日突然裁判所から訴状が届いた場合、どのように対応したらよいのでしょうか? 訴状を無視してもよいのでしょうか? 裁判を欠席するとどうなるのでしょうか? 今回は、裁判所から訴状が届いた場合に、訴状を無視して裁判を欠席する …
-
-
民事訴訟費用(弁護士費用)や裁判費用を相手に請求できるケースとは?(元弁護士作成記事)
普通に日常生活を送っていても、法的なトラブルに巻き込まれることは多いです。 たとえば貸したお金を返してもらえない場合、賃貸住宅を人に貸している場合に賃借人が家賃を払ってくれない場合、離婚トラブル、交通事故など、さまざまな …
-
-
弁護士費用の相場が知りたい!弁護士の相談費用・着手金・成功報酬など詳しく紹介(弁護士監修記事)
弁護士に対して、「客から高い報酬を貰って儲けすぎ」というイメージを持たれている方は、多いのではないでしょうか? しかし弁護士は弁護士で、一定の報酬を貰わないと弁護士事務所が経営できないという切実な事情も存在 …
・内容証明郵便の書き方と出し方のルール【文例テンプレート付き】
内容証明郵便は、明確な証拠を残したい場合など、トラブルの予防や解決において、とても有効な手段となることがあります。われわれ弁護士も、相談者のトラブルの予防や解決のために動き出す時、内容証明郵便の作成から始めることが多いです。とはいっても、内容証明郵便は弁護士のように法的な専門家だけが作成できるものではありません。簡単な書き方・出し方のルールやポイントを押さえれば、あなたも作成できるものです。この記事では、内容証明郵便の書き方・出し方を紹介するとともに、文例のテンプレートについてもご紹介していきます。現在、内容証明郵便をトラブルの相手に送ろうと考え始めているものの、「内容証明郵便の細かい書き方や出し方などのルールがイマイチわからない」「自分が遭遇しているトラブルで内容証明郵便が使えるのかを知りたい」とお考えの方の参考になれば幸いです。
・一人でもできる!少額訴訟(少額裁判)の流れや費用、訴状の書き方を解説
「裁判」というと、、弁護士ではない一般の人が1人で手続きを進めるのは、ほとんど不可能だと思われている方が多いのではないでしょうか?ただ、「少額訴訟制度」という制度を利用すれば、弁護士に依頼せず、一般の方が1人で手続きを進めることも十分に可能です。では、少額訴訟とはどのような制度なのでしょうか?どのようなトラブルでよく利用されるのか、通常訴訟や支払督促との違いはなんなのか、手続きの流れやリスクなど、知っておくべきことは多々あります。今回は、知っておくと役立つ「少額訴訟」について、図解イラストつきで詳しく解説します。